一級建築士 学習のポイントを知ろう
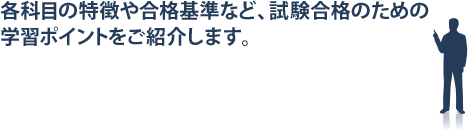
学科試験の合格基準点と合格率
学科試験に合格するためには、科目基準点(それぞれの科目の合格ライン)と、合格基準点(全科目合計の合格ライン)の双方をクリアしなければなりません。
平成21年には試験の見直しが行われ、合格基準点も改められました。国土交通省は「各科目は過半の得点、総得点は概ね90点程度を基本的な水準として想定」と発表していましたが、平成21〜25年、平成27年、平成29年は、想定していた合格率と実際の得点水準に乖離(かいり)が生じたため、合格基準点が補正されました。
また前述の通り、合計で合格基準点を上回った場合であっても、1科目でも科目基準点を下回ることがあれば不合格となるので、全科目それぞれをバランス良く学習する必要があり、苦手科目の存在は命取りになります。一般的に「構造力学」を苦手とする受験生が多く、「構造」に関しては基礎からしっかり学習しなければなりません。
なお、「法規」に関しては、試験実施機関が許可している「法令集」を試験会場に持ち込むことが認められており、試験中に閲覧することが可能です。高得点をねらうためには、事前に「法令集」を引きやすくするための見出し(インデックス)や、アンダーラインに工夫を加え、使いこなせるようにしておくことが必要です。もちろん、法令集自体が見やすく引きやすいものであることは絶対条件です。
さらに、建築基準法は毎年改正されているため、古い法令集をそのまま利用することは非常に危険であり、受験年度に合った最新の法令集が必要となります。
| 年度 | 科目基準点 | 合格
基準点 |
合格率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科I | 学科II | 学科III | 学科IV | 学科V | |||
| 平成21年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 97 | 19.6% |
| 平成22年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 88 | 15.1% |
| 平成23年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 87 | 15.7% |
| 平成24年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 94 | 18.2% |
| 平成25年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 92 | 19.0% |
| 平成26年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 90 | 18.3% |
| 平成27年 | 11 | 10 | 16 | 16 | 13 | 92 | 18.6% |
| 平成28年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 90 | 16.1% |
| 平成29年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 87 | 18.4% |
| 平成30年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 91 | 18.3% |
| 令和元年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 97 | 22.8% |
| 令和2年 | 11 | 10 | 16 | 16 | 13 | 88 | 20.7% |
| 令和3年 | 10 | 11 | 16 | 16 | 13 | 87 | 15.2% |
| 令和4年 | 11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 91 | 21.0% |
計画のポイント
計画は、出題範囲が非常に幅広く、時間をかけて学習しても、なかなかその効果が表れにくいので、上位者と下位者の得点差がつきにくいという特徴があります。出題内容は、環境工学のように原理、原則に基づいた問題ではなく、建築的な常識で判断する問題が多く、また、文章の読解力を必要とする問題も出題されます。
環境・設備のポイント
環境の出題は、光・熱・空気などの自然条件が建築物に与える影響や、人体にとって快適な室内環境を計画する上での基本的な知識を問う出題が多く、学習の成果が得点に表れやすい科目です。しっかりとした知識を身につけて得点源にしてください。
また、設備では快適な建築空間をつくるための空気調和設備、給排水設備、電気設備などや、安全に生活するための防災設備などから出題されます。法適合確認に関する、実務的な内容も出題されますので、高得点を狙いにくい科目といえますが、まずは、機器の目的、特徴などを問う基本的な問題は、とりこぼししないことを心掛けてください。
法規のポイント
法規は唯一、試験会場内へ法令集の持ち込みが認められている科目です。また、例年の出題傾向は他の科目と比べ最も明確ですから、合格者の多くは確実に得点を挙げています。問題集や各種テスト等で各項目ごとの問題をしっかり学習すれば、高得点が望めます。
是非とも法規を得意科目にして、総合点アップをめざしてください。
構造のポイント
構造の特徴は、上位者と下位者の得点の差がつきやすい点です。一般的に各種構造と建築材料の文章問題で得点を稼ぎ、構造力学でプラスαの得点を狙う受験生が多いようですが、このやり方は非常に危険です。
近年の傾向として、耐震設計に関する出題が目につき、特に耐力壁に関しては、木質構造や鉄筋コンクリート構造において毎年のように出題されます。全体としては、構造設計の実務に関する出題が増えています。そのため、各種構造と建築材料の文章題で確実に得点を稼ぐことは難しい傾向にあります。高得点者はやはり、構造力学に強いようです。
構造力学で得点を取るためには、まず公式や解法を覚えて問題を数多くこなすことです。繰り返し学習して、解き方を自分のものにしてください。
施工のポイント
現場実務経験のない方や初受験の方が必ず戸惑ってしまうのが施工です。まず何を見ても聞いてもイメージがわかず、何をどう理解してよいか分からない……といった具合かと思われます。
施工を克服するためには、ディテール(納まり)から入ってはいけません。まず、工事全体の流れ、個々の工事の流れ、工事の進め方等を大きく捉えイメージすることが重要です。そして克服への第2の壁は、難しい施工特有の専門用語の理解です。重要な用語の解説、用語集等を丁寧に調べ理解していくことが必要です。
施工の学習の難しさは、建物を建築するための実務的な知識や技術を机上のみで身につけるところにあります。建築現場に足をはこび、実際に見て確認してイメージさえつけてしまえば、こちらのもの。意外と現場経験のない初受験等の方が、高得点で合格されていることもまた事実です。
設計製図試験のポイント
設計製図試験は、あらかじめ発表されている設計製図課題に基づき、図面及び記述を完成させる試験です。設計条件の詳細等は試験当日まで確認できないため、課題から想定される様々なパターンの準備をしておく必要があります。
試験時間は、6時間30分です。設計製図試験に合格するためには、この試験時間内に、与えられた内容及び条件を満たす図面と記述を完成させなければなりません。
| 設計製図
試験 |
試験時間 | 6時間30分 |
|---|---|---|
| 出題形式 |
あらかじめ公表される課題の建築物についての設計図書の作成 |
|
| (学科試験合格後)学科試験免除回数 |
1)令和元年度以前の学科試験に合格: 2回の試験のうち2回の学科試験を免除(学科試験合格後の有効期限は3年間) 2)令和2年度以降の学科試験に合格: 4回の試験のうち2回の学科試験を免除(学科試験合格後の有効期限は5年間) |
※詳細は必ず 試験実施機関のホームページでご確認ください。
設計製図試験の合否判定基準は?
| 年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|
| 設計 課題 |
事務所ビル | |
| 採点結果の区分 |
○採点結果については、ランクI、II、III、IVの4段階区分とする。
|
|
|
○なお、採点の結果、ランクI、II、III、IVのそれぞれの割合は、次のとおりであった。
|
||
| 合格基準 | 採点結果における「ランクI」を合格とする。 | |
過去の「設計製図の試験」課題一覧
| 年 | 課題名 |
|---|---|
| H13 | 集合住宅と店舗からなる複合施設(3階建) |
| H14 | 屋内プールのあるコミュニティ施設 |
| H15 | 保育所のある複合施設 |
| H16 | 宿泊機能のある「ものつくり」体験施設 |
| H17 | 防災学習のできるコミュニティ施設 |
| H18 | 市街地に建つ診療所等のある集合住宅 |
| H19 | 子育て支援施設のあるコミュニティセンター |
| H20 | ビジネスホテルとフィットネスクラブからなる複合施設 |
| H21 | 貸事務所ビル |
| H22 | 小都市に建つ美術館 |
| H23 | 介護老人保健施設 |
| H24 | 地域図書館 |
| H25 | 大学のセミナーハウス |
| H26 | 温浴施設のある「道の駅」 |
| H27 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅 (基礎免震構造を採用した建築物である。) |
| H28 | 子ども・子育て支援センター(保育所、児童館・子育て支援施設) |
| H29 | 小規模なリゾートホテル |
| H30 | 健康づくりのためのスポーツ施設 |
| R01 | 美術館の分館 |
| R02 | 高齢者介護施設 |
| R03 | 集合住宅 |
| R04 | 事務所ビル |
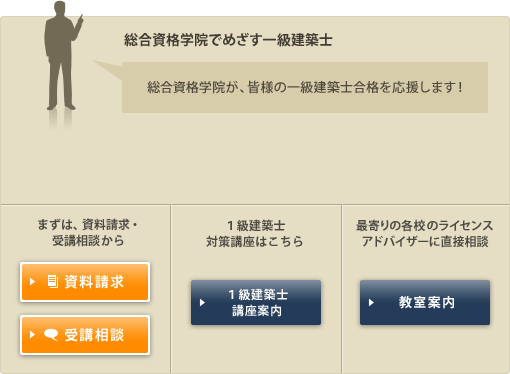
一級建築士受験に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、数多くの合格実例に基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒に一級建築士合格をめざしましょう!
関連リンク
一級建築士合格者の学習ノウハウをまとめて掲載。学科から製図、各合格者のタイムスケジュールまで、学習に役立つ情報を掲載しております。