二級建築士 建築士の主な業務
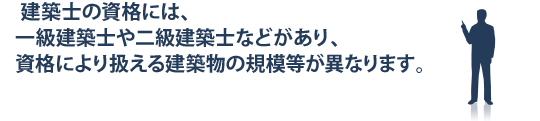
建築士の主な業務
昭和25年に「建築物の設計・工事監理などを行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、建築物の向上に寄与させる」ことを目的として建築士法が制定されました。
建築士法で定められている建築士が行うことのできる業務には、次のようなものがあります。
建築物の設計及び工事監理
施主から注文を受け、その目的やイメージに合う建築物を考え、図面としてまとめることを「設計」といい、図面どおりにきちんと工事が行われているかをチェック・確認することを「工事監理」といいます。
建築主に対する重要事項説明
設計・工事監理契約の締結前に、あらかじめ管理建築士その他の当該建築事務所に所属する建築士が、建築主について、書面を交付して説明を行うことが義務づけられています。
建築工事契約に関する事務
工事をするにあたって契約の締結に立ち会ったり、建築主に代わって各種手続きをします。
建築工事の指導監督
建築主の依頼により第三者的立場から建築工事の指導監督を行なうことができます。
-
※建設業法により1級建築士は「監理技術者(註1)」2級建築士は「主任技術者」として工事現場の指導監督をすることができます。
註1:監理技術者講習を修了して監理技術者資格者証の交付を受ける必要があります。
建築物に関する調査または鑑定
建築物の老朽度や耐用年数、耐震性などを調査し、建築物としての価値を鑑定します。
建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理
建築主がしなければならない、役所への計画書の届け出等の手続きを代行します。
建築士ができること
二級建築士
二級建築士は扱える建物の規模や、用途、構造等に制限がありますが、戸建住宅程度の規模であれば、木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の設計をすることが可能です。
※ニ級建築士は都道府県知事の免許を受け、ニ級建築士の名称を用いて、設計、工事監理などの業務を行う資格を有する者。
一級建築士
一級建築士は扱える建物の規模などに制限がありません。個人の住宅はもちろん、大規模なマンション、超高層ビルまで何でも扱えます。建物の用途、延べ面積、高さ、軒の高さ、階数について、制約を受けることなく、すべての建築物の設計・工事監理を行うことができます。
※一級建築士は国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理などの業務を行う資格を有する者。
※高度な専門能力を必要とする、一定の規模以上の構造設計・設備設計に関しては、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士の関与が義務づけられています。
建築士の仕事分類
| 構造別区分 | 一級建築士でなければ設計又は監理をしてはならない建築物 | 一級建築士又は二級建築士でなければ設計又は監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く) | 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ設計又は監理をしてはならない建築物(左欄に該当するものを除く) |
|---|---|---|---|
| すべての構造について | 学校、病院、劇場、映画館、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く)または百貨店の用途に供する建築物で延べ面積が500m2をこえるもの | − | − |
| 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分 | a)延べ面積が300m2をこえるもの | 延べ面積が30m2をこえるもの | − |
| b)高さが13mをこえるもの | |||
| c)軒の高さが9mをこえるもの | |||
| その他の構造で木造以外の建築物 | 延べ面積が1,000m2をこえ、かつ2階以上のもの | a)延べ面積が100m2をこえるもの | − |
| b)3階以上のもの | |||
| 木造の建築物 | a)延べ面積が1,000m2をこえ、かつ2階以上のもの | a)延べ面積が300m2をこえるもの | 延べ面積が100m2をこえるもの |
| b)高さが13mをこえるもの | b)3階以上のもの | ||
| c)軒の高さが9mをこえるもの |
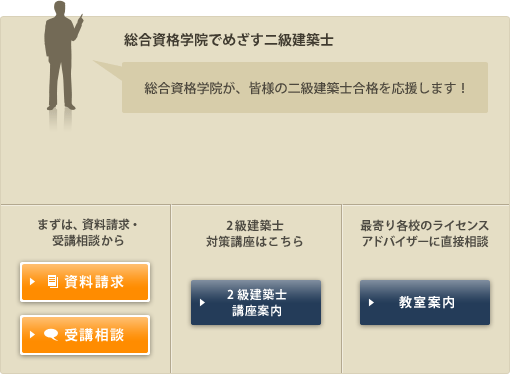
ニ級建築士受験に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、数多くの合格実例に基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒にニ級建築士合格をめざしましょう!
