令和5年度 2級建築士設計製図中期必勝コース
詳細は無料パンフレットをご覧ください!
総合資格学院は、令和4年度 2級建築士 設計製図試験終了後に、「製図試験 大検証2022」を実施いたします。Twitterを活用した受験生参加型のコンテンツや、当学院の製図試験分析等を公開いたしますので、製図試験終了後は、ぜひ当ページをご覧になってください!

試験終了後より、Twitterにて、令和4年度 設計製図試験の「気になるポイント総選挙」を実施いたします。1位に選ばれた項目については、本ページにて詳しく解説いたしますので、ぜひご参加ください!
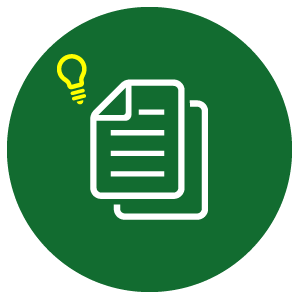
試験翌日に、本ページにて当学院の製図試験総評を公開いたします。製図試験の特徴やポイントになった項目を発表いたしますので、Twitter総選挙の結果と併せてご確認ください。
「気になるポイント総選挙」にご参加くださった皆様、たくさんのご投票ありがとうございました!そして大変お待たせいたしました!皆様にご投票いただいた結果、下記の通りとなりました!そして現在、4つのポイントについて当学院の詳細コメントを公開中です!当学院の解説を読んで、あなたが製図試験で気になったポイントをスッキリ解決しましょう!
設計条件の①で「乳児室、ほふく室及び保育室は、自然採光及び自然換気を積極的に取り入れる計画とする。」と明記がされています。また計画の要点等の①でも「乳児室、ほふく室及び保育室の自然採光及び自然換気について、配慮した点」を具体的に記述するように指示がされています。受験生の多くは、「自然採光と自然換気のために何か特別なことをやらなくてはならない」と読み取っているかもしれませんが、課題条件には特に記載がありませんので、基本に忠実に、「乳児室」「ほふく室」「保育室」の3室は、全室南面する配置として、かつ外部及び内部に複数開口部を設けることで「自然採光及び自然換気」を積極的に取り入れる計画とします。
建築物、屋外施設等の、安全・防犯については、乳幼児が敷地外に出ないようにすること、部外者が公園や前面道路から立ち入ることができないようにすることが求められるため、アルミフェンスを敷地周囲に設けるなどの計画をすることが必要となります。
建築物の環境負荷低減については、夏季の日射による室温上昇を低減するために、窓ガラスに「Low-E複層ガラス」を用いる他、新たに東京都の新築住宅で必須条件となった「太陽光発電システム」を搭載することも有効な手段となります。
令和4年度の課題は、特に2階要求室が少ないことにより、延べ面積の下限値以下になる懸念がありました。また設定された延べ面積は、これまでの木造課題と比べると、1割程度大きく設定されています。これらのことから、2階の各室は適度な大きさにする必要があると共に、延べ面積チェックで下限値を下回っていた場合に、エスキスを修正し、要求された面積を満たす修正力も必要となりました。
本映像では、令和4年度 2級建築士設計製図試験の特徴や採点のポイントとなる部分について解説いたします。
令和4年度試験の傾向と特徴
「保育所(木造)」
近年の試験では、設計の自由度を高めた課題が出題されていますが、令和4年度は、その点に加え、国の方針や社会情勢を踏まえた上で、「設計者として、正しく設計条件が読み取れるか」「整合性のとれた作図表現ができているか」が求められた試験でした。
令和4年度 設計製図試験のポイント
延べ面積指定
令和4年度の課題は、延べ面積の指定が「200 ㎡以上250 ㎡以下」と、これまでの木造課題からすると1割程度大きく設定されていたため、下限値違反とならないようしっかりとチェックを行う必要がありました。
室の配置
令和4年度の課題は、東側に公園のある敷地が出題されましたが、公園との関係は特に必要なく、通常通り保育室関係を南面させる事が重要でした。
課題文をしっかりと読み、課題文通りに計画
保育室関係の面積条件や所要室の条件等の読み飛ばし、設置する必要のない物を設置する等、課題文を深読みせず、課題文通りにしっかりと計画することが重要でした。
作図の精度と密度
まとめ
令和4年度 2級建築士 設計製図試験において、出題された課題は、サプライズ的な要素は特になく、多くの受験生が図面を「仕上げている」状況である事が想定されます。合格を勝ち取るためには、先にあげたポイントにしっかり対応できていることに加え、作図によるプレゼンテーション力が重要であると考えられます。