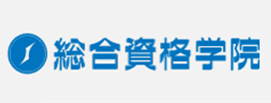試験内容について
 1級建築士になるためには、国土交通大臣が行う1級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
1級建築士になるためには、国土交通大臣が行う1級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
1 級建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」に分けて行われ、「設計製図の試験」は、学科の試験に合格しなければ受験することができません。
1 級建築士試験で「学科の試験」に合格し、残念ながら「設計製図の試験」に不合格となった方、又は受験しなかった方は、本人の申請により、「学科の試験」の合格翌年から4 回の試験のうち2 回( 合格年度の設計製図の試験を欠席する場合は3回)について「学科の試験」が免除されます(学科試験合格の有効期限は5年間)。
【TOPICS】令和2年度から新しい建築士試験がスタートしました。
- ●建築士試験の受験資格の変更
- ●学科試験免除の仕組みを変更
- ●建築士資格に係わる実務経験の対象実務の変更
学科試験はどのような試験ですか?
学科試験の出題科目は、学科Ⅰ「計画」、学科Ⅱ「環境・設備」、学科Ⅲ「法規」、学科Ⅳ「構造」、学科Ⅴ「施工」の5科目で、四肢択一式、出題数は合計125問で総得点が125点満点の試験です。試験時間は6時間30分となります。
また、合格をするためには、合格基準点(全科目合計の合格ライン)と科目基準点(それぞれの科目の合格ライン)の双方をクリアする必要があります。
合格基準について、国土交通省は「各科目は過半の得点、総得点は概ね90点程度を基本的な水準として想定」と発表していますが、想定していた合格率と実際の得点水準に乖離が生じた場合、合格基準点の補正が行われる場合があります。また前述の通り、合計で合格基準点を上回った場合であっても、1科目でも科目基準点を下回ることがあれば不合格となるので、全科目それぞれをバランス良く学習する必要があり、苦手科目の存在は命取りになります。
【各科目ごとの出題数】
・学科Ⅰ「計画」(20問)
・学科Ⅱ「環境・設備」(20問)
・学科Ⅲ「法規」(30問)
・学科Ⅳ「構造」(30問)
・学科Ⅴ「施工」(25問)
学科試験はどのような問題がでますか?
学科Ⅰ「計画」:計画は、計画以外にも建築士の職責、施設、建築史、積算、生産にいたるまで出題の幅が非常に広いのが特徴です。また、建築的な常識で判断する問題が多く、文章の読解力を必要とする問題も出題されます。
学科Ⅱ以降は、「もっと詳しくボタン」から!
学科Ⅱ「環境・設備」:環境は、光・熱・空気などの自然条件が建築物に与える影響や、人体にとって快適な室内環境を計画する上での基本的な知識を問う問題が多く出題されます。
また、設備では快適な建築空間をつくるための空気調和設備、給排水設備、電気設備などや、安全に生活するための防災設備などが出題されます。理論・公式・現象の理解など原理・原則の理解が特に重要です。
学科Ⅲ「法規」:建築基準法や関係法令が出題されます。なお、それらは法令集に記載がされています。法規は唯一、試験会場へ法令集の持ち込みが認められている科目ですが安心は禁物です。なぜなら、数百ページに及ぶ法令集のどこに何が掲載されているか素早く探し出せるようにしておくことに加え、条文の内容も正しく理解しておく必要があるためです。
学科Ⅳ「構造」:構造力学や各種構造、建築材料などが出題されます。近年の出題傾向として、全体では構造設計実務に関する出題が増えていることや、耐震設計に関する出題が目につきます。特に耐力壁に関しては、木質構造、コンクリート構造ともに毎年のように出題されています。
学科Ⅴ「施工」:施工計画他や、各部工事のディティールまで「実務的な」内容が出題されます。また、施工特有の専門用語も数多く出題されるため用語の理解が欠かせません。そのため、現場での実務経験がない方は、必ず戸惑う科目です。建物を建築するための実務的な知識を机上で学ばなくてはいけない点が難しい点であり、イメージを伴った学習が重要です。

設計製図試験はどのような試験ですか?
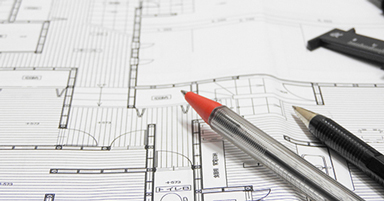
なお、採点結果は、ランクI :「知識及び技能」※を有するもの、ランクII :「知識及び技能」が不足しているもの、ランクIII :「知識及び技能」が著しく不足しているもの、ランクIV :設計条件及び要求図書に対する重大な不適合に該当するものに分類され、ランクIが合格となります。
設計製図試験は、どのような「課題」がでますか?
現在、課題分析をこちらで公開しておりますので、ぜひ、ご覧ください!
| 課題名 | |
|---|---|
| 令和5年度 | 図書館 |
| 令和4年度 | 事務所ビル |
| 令和3年度 | 集合住宅 |
| 令和2年度 | 高齢者介護施設 |
| 令和元年度 | 美術館の分館 |
| 平成30年度 | 健康づくりのためのスポーツ施設 |
| 平成29年度 | 小規模なリゾートホテル |
| 平成28年度 | 子ども・子育て支援センター |
| 平成27年度 | 市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅 |