�y�؎{�H�Ǘ��Z�m �������x��m�낤
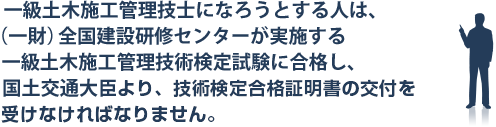
�ꋉ�y�؎{�H�Ǘ��Z�p����́A�u��ꎟ����v�Ɓu�����v�ɕ����Ď��{����܂��B�u��ꎟ����v�ɍ��i�����1���y�؎{�H�Ǘ��Z�m��A�����ɍ��i�����1���y�؎{�H�Ǘ��Z�m�̍��Ǝ��i���擾���邱�Ƃ��ł��܂��B
�������e
���L�͗ߘa5�N�x�̓��e�ł��B
1.��ꎟ����
��ꎟ����̏o�蕪��́A�u�y�؈�ʁv�u���y�v�u�@�K�v�u���ʍH�w�v�u�{�H�Ǘ��@�i�m���j�v�u�{�H�Ǘ��@�i���p�\�́j�v�ƂȂ��Ă���A����4�����[���ŁA���v96�₪�o�肳��܂��B���̂����A�I���肪61�� (61�⒆30����j�A�K�{��肪35�� (35�⒆35����j�ƂȂ��Ă���A���v96�⒆65�Ԃ����܂��B ���i��́w���_��60���ȏ� (65�Ԓ�39�Ԉȏ㐳���j������Ȗځu�{�H�Ǘ��@�i���p�\�́j�v�̓��_�� 60���ȏ�(15�⒆9��ȏ㐳���j�x�ƂȂ��Ă��܂��B
2.�����
�����͑��ꎮ�̑�ꎟ����Ƃ͈قȂ�A���ׂċL�q���ōs���邽�߁A���_�����ɂ́A���͂ŗv�_��I�m�ɕ\�����A�ł���悤�ɂ��Ă����K�v������܂��B�Ȃ��A���_��60���ȏオ���i��ƂȂ�܂��B �ߘa4�N�x�́A�K�{�ԑ肪3���A�I���肪8���́A�S����11��肪�o�肳��܂����B�I����Ɋւ��ẮA�u�I����(1)�Ƃ���4���A�I����(2)�Ƃ���4��肪�o�肳��A���ꂼ��2��肸�A���v4����I�����ĉ���v�Ƃ����`���ł����B �o���L�q�i���1)��2�N�A���Łu���S�Ǘ��v���o�肳��܂����B�u�ݖ�ŋ��߂��Ă�����e�ȊO�̋L�q�v ��u��̐����R�����v�Ƃ������ꍇ�́A�m���E�\�͂��s�����Ă���Ɣ��f�����\�������������߁A�ɍۂ��Ă͍אS�̒��ӂ��K�v�ł����B���2�E3�i�K�{���j�ł́A���ɖ��3�i�m�������̕��@�E���ʗ��p�j�̓�x�������������߁A�m���ƌo�����s�\�����Ɠ��_����̂���������ƍl�����܂��B���4�ȍ~�̑I����́A�m�H�A�R���N���[�g�A���S�Ǘ��A�i���Ǘ��A���ݕ��Y������̏o��ł������A���������_�ł���������ɂ߂ĉ��邱�Ƃ��|�C���g�ł����B���5�i�i���Ǘ��j�A���7�i�y�H�j�A���8�i�y�H�j�Ɋւ��ẮA���o��̓��e�����������A�����E�����̗������K�v�ȓ����肾�������߁A�ҊԂœ��_�����J���₷����肾�����ƍl�����܂��B
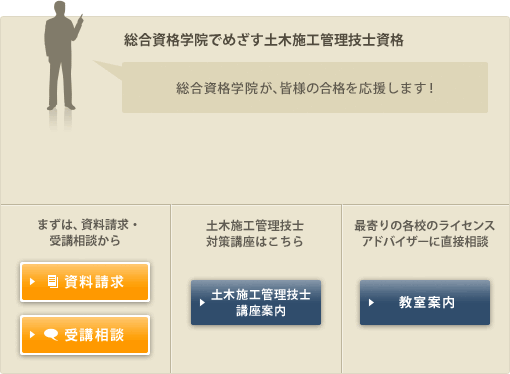
�ꋉ�y�؎{�H�Ǘ��Z�p����Ɋւ���^���s�����A�������i�w�@���������܂��B���w�@�̃��C�Z���X�A�h�o�C�U�[���A�������̍��i����Ɋ�Â��I�m�ɃA�h�o�C�X�������܂��̂ŁA���ЁA�������ƈꏏ�Ɉꋉ�y�؎{�H�Ǘ��Z�p���荇�i���߂����܂��傤�I
�������{�@��
- �������{�@�ցF �i����j�S�������C�Z���^�[
