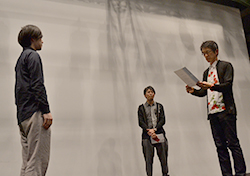赤レンガ卒業設計展2015「Over architecutured」
赤レンガ卒業設計展2015「Over architecutured」
| 名称 | 赤レンガ卒業設計展2015「Over architecutured」 |
|---|---|
| 日程 | 開催日:2015年3月26〜30日 講評審査会:2015年3月29日 13:15〜 |
| 会場 | 赤レンガ倉庫1号館 |
| 審査員 | 審査委員長 審査委員 |
| 主催 | 赤レンガ卒業設計展2015実行委員会 |
| 特別協賛 | 株式会社総合資格/総合資格学院 |
赤レンガ倉庫に関東の秀逸な卒業設計が集結!
関東の主要大学による合同卒業設計展「赤レンガ卒業設計展2015」が、3月26〜30日の5日間、横浜赤レンガ倉庫(横浜市中区)で開催された。
回を重ねるごとにその認知度、規模を拡大してきている同設計展。今回は16大学19学科から238作品が出展した。開催期間中は天候にも恵まれ、大学関係者にとどまらず、同施設を訪れた観光客など、多くの来場者が連日会場に足を運んだ。
今回のテーマは「Over architecutured」。「大学4年間の自らの過去の建築を超えていこう」という思いが込められた「Over architecuture+ed」、「赤レンガという場にとどまらず、広くこの建築を発信していこう」という思いが込められた「Over red bricks」という2つの思いが重なりあい、「Over architecutured」というテーマを構成する。
■参加大学
神奈川大学/共立女子大学/工学院大学/首都大学東京/昭和女子大学/東海大学/東京工業大学/東京電機大学/東京都市大学/東京理科大学/日本大学/日本女子大学/法政大学/前橋工科大学/明治大学/横浜国立大学
一次審査で選ばれた珠玉の10作品
3月29日(日)には、今回の最優秀作品を選出する講評審査会が開催された。当日10時より審査委員の会場巡回による一次審査がスタート。粒ぞろいの作品の中から5人の審査委員の目にとまった10作品が、同施設3階大ホールにて13時15分から行われる二次審査へと進んだ。
-

- 千葉学氏
-
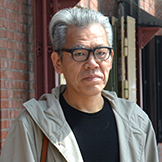
- 西沢大良氏
-
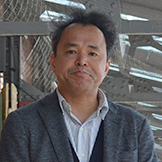
- 堀部安嗣氏
-

- 中山英之氏
-

- 門脇耕三氏
一次審査で選出された10作品は以下の通り。
■10選
| 名前 | 学校名 | 作品名 |
|---|---|---|
| 大村高広さん | 東京理科大学 | 淀橋のビル |
| 大岡晃さん | 神奈川大学 | Bhinneka Tunggal Ika |
| 加藤裕太さん | 日本大学 | 郊外の孔 |
| 齊藤佑樹さん | 日本大学 | 重層する借景 |
| 片嶋一裕さん | 東京都市大学 | 風土の器 |
| 福士貴仁さん | 東京都市大学 | 揺らぎ色づく風景 〜梨棚の下の寄合所〜 |
| 菅野凌さん | 前橋工科大学 | 人工の森を辿るケモノミチ |
| 茂住勇至さん | 明治大学 | 或る日、或る街。 |
| 鳥居希衣さん | 東京都市大学 | 炉辺談話 |
| 滝村菜香さん | 日本大学 | 水たまりを掬ぶ |
決戦投票の末、最優秀賞が決定!
選出された10作品を担当した学生たちのプレゼンテーションと審査委員の質疑応答による二次審査は、一次審査が時間的に押した影響で、予定より20分以上遅れて開始した。
学生たちに与えられたプレゼンテーションの時間は3分間。この限られた時間の中で、作品の概要から狙いまでを5人の審査委員の前で強く訴えた。質疑応答の時間には審査委員から、建築家として、そして社会人の先輩として、激励の意味を込めた暖かくも厳しい意見や質問が投げかけられた。
すべてのプレゼンテーション終了後、最優秀作品選出に向けて審査委員から味のあるコメントが寄せられた。
千葉氏:
どの作品案も着眼点はよいものの、建築的なソリューションがよくなかったり、またその逆のパターンであったりと、正直、最優秀賞の候補を選ぶのが大変でした。高度成長期のように、ただかっこいいものを建てるのではなく、「なんでそれを建てるのか?」というのが今の時代の建築には、強く求められてきています。それだけに建築についての感受性を養っていくことが重要であり、今後もより広い社会的な観点で建築に関わっていってもらえればいいなと思いました。
西沢氏:
どの作品も着眼点はよく、ここから名作は生まれたはずですが、言葉の使い方がおかしく、伸び悩んでいると感じました。特に成果品と乖離していながらも「正しく聞こえるような言葉を使いたい」という臆病な気持ちがあったようです。それはデザイナーにとって、もっとも不要な気持ちでしょう。それこそ度胸がなければ、クリエーションもイノベーションもできません。あと、言葉という点では、タイトルがポエムっぽく、自分のやったことを言い当てていない点も気になりましたね。
堀部氏:
10作品みんな、どんぐりの背比べで、その中から最優秀作品の候補は選びづらかったですね。社会的に問題とされているテーマを作品に取り入れたものが多かったようですが、本当にそれを問題だと感じているのか、こちらに伝わってこない表現が多い気がしました。表現が多様化しているように、問題も多様化しているわけで、自分が体感して「これは問題だ」と思える、それこそ身近なものから建築を紐解く作品がもっとあってもよかったのではないかと思いました。
中山氏:
建築のプレゼンテーションとして纏め上げられていませんでしたね。これはただ単純に文学的な力がまだまだ足りていないだけでしょう。そんな自分の作品を正当化するためのよくわからない前口上で多くの時間を費やしているプレゼンテーションを聞いた中では、自分の考えていることをなんとか既存の社会にある言葉に置き換えながら、言語化してやろうという試みが見える作品を選びました。
門脇氏:
みなさんは工学的な正しさにとらわれていると感じました。「こういう予感に導かれて、こう作り、そしてこういう情感だった」という、建築物が置かれたことによって見えてくる価値をもっとプレゼンテーションで力強く語ってもらってかまわないと思います。むしろそれが語れなければ個人の名前でやっている意味がないですよね。そんなことでは新しい価値は作っていけないですし、それが置かれる街もよくならないでしょう。もっと勇気を持って作品を語ってほしいと思いました。
審査は次のステージに進む。審査委員は各々、最優秀賞の候補を挙げていき、これらの作品について白熱した議論を展開。東京理科大学の大村高広さんの「淀橋のビル」と明治大学の茂住勇至さんの「或る日、或る街。」の2作品が最終審査に残った。審査委員は、この2作品について、それぞれの考えを述べ、その後、審査の最終結論を出す決戦投票を実施した。結果、3票を獲得した「淀橋のビル」が最優秀賞に輝いた。続いて審査委員個人賞が発表され、プレゼンテーションを含めて3時間超となった審査は結末を迎えた。結果は以下の通り。
| 最優秀賞 |
|---|
大村高広さん (東京理科大学) 淀橋のビル タワーマンションが建ち並ぶ東京都新宿区5丁目を敷地に選んだ同作品。まわりの環境に対して非常に暴力的な建ち方をしているマンション群に対し、オルタナティブを提案することを通して、雑多な都市環境の中で「いかにして巨大な建築を存在させればいいか」が考えられている。現実に相対する中で、もう一度建築を考え直したというアプローチが高く評価された。 |
| 千葉学賞 |
|---|
加藤裕太さん (日本大学) 郊外の孔 都心への一極集中によってもたらされた絶好の位置にあることから、郊外と定義づけられる地方都市「千葉県木更津市」。この均質化した都市において、昔から風景として存在していた貯木場を生活の場として、街との関係性を創りだした作品となっている。住居や工場、公共施設などを組み合わせたチャレンジが見える点が選出の推進力となった。 |
| 西沢大良賞 |
|---|
福士貴仁さん (東京都市大学) 揺らぎ色づく風景 里山を切り崩した港北ニュータウンと元々あった村との間に存在する放置された畑は都市の空白となっていた。その場所に地域で有名な梨園をヒントに「果樹園空間を活かした寄合所」を提案した作品となっており、テントにより内外をやわらかく仕切り、梨の木と建物が一体となって四季に応じた風景の創出を狙った。 |
| 堀部安嗣賞 |
|---|
片嶋一裕さん (東京都市大学) 風土の器 栃木県益子市の民芸品「益子焼」の体験工房を提案した作品。焼き物が並ぶ商店街から、里山の自然をつなぐ軸に手作りの工程とまちの風土的要素を一体に建築を考え、「手作りの温かみ」「人の暮らし」「町の催し」「益子焼と過ごす穏やかな時間」でまちの風景を提案した。緻密かつ誠実に手を動かしたことが明確な模型や、その取り組みによって生まれてくる「建築の確かさ」への期待が支持され、受賞となった。 |
| 中山英之賞 |
|---|
滝村菜香さん (日本大学) 水たまりを掬ぶ 川や雨といった「水」を拒絶し、見えない場所へと追いやってきた東京というまちは、それでもゲリラ豪雨などにより、水に襲われている。この現実に対して、水を拒絶しないまちづくりを提案した作品。ダイナミックなレンジで東京を捉えている点が特に評価された。 |
| 門脇耕三賞 |
|---|
菅野凌さん (前橋工科大学) 人工の森を辿るケモノミチ 空き家を編集し、日常生活を新たな視点から見るための建築群を提案した作品。空き家といった既存建築の持っている意味の変化を狙い、使われなくなったものに新たな意味を付加させ、建築都市公園を計画した。近年の空き家問題を街全体の資産として弁解していけるリアリティのある部分が受賞の決め手となった。 |
審査終了後、同会場にて授賞式および懇親会が開催された。懇親会では、審査委員から作品について改めて講評をもらう熱心な学生や、ひと段落ついた開放感から思う存分宴を楽しむ学生などが見られ、会場は終始熱気に包まれたまま幕を閉じた。