- 令和3年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 釜崎 日菜さん
SPECIAL INTERVIEW
目標をもって最後まであきらめない!
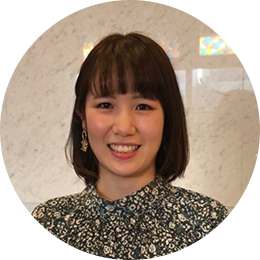
釜崎 日菜さん (22) 令和3年度 1級建築士合格
- 学歴:
- 大学
- 勤務先:
- 官公庁(行政)
- 教室:
- 長崎校
計画:12点、環境・設備:13点、法規:23点、構造:24点、施工:16点
受講講座
- 受験回数:
- 学科1回/設計製図1回
現在の仕事の道に進もうと思ったきっかけ
建築分野において長崎県のまちづくりに貢献したい
近年、長崎県は少子高齢化や県外流出によって人口が減少していることから、長崎県を魅力ある街、にぎわいのある街、暮らしやすい街にすることが課題だと考えます。そこで長崎のまちづくりに携わることができる長崎県庁に建築職として入庁しました。
1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
勉強する習慣が大事
公務員試験や大学院試験が終わったタイミングだったので、一度勉強しなくなると再度勉強する習慣をつけるのに時間がかかるため、このまま勉強を継続することが効果的だと考え、受験しました。1級建築士を受験することは県庁に採用が決まった時点で決めていました。ストレートでとることは非常に難しい試験だということは分かっていたので、初めは合格するのに何年かかるかとても不安でしたが、とりあえずがんばってみようという気持ちでした。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
実績から判断
まず1級建築士試験は、ストレートで簡単に合格できる試験ではないということは理解していたので、資格学校で集中的に勉強しようと決めていました。資格学校の中で一番実績があった総合資格学院に迷わず決めました。
ご自身と独学者を比べてみて、一番大きな違いは何だったか
何を勉強すればよいか総合資格学院が教えてくれる
学科試験において、合格に向けて計画的に勉強することができたのは総合資格学院のおかげです。1級建築士試験合格には膨大な勉強量を要する試験ですが、独学者では何をどのくらいのペースで勉強すればよいか分かりません。総合資格学院では毎週の講義を集中して受講し、出された課題と予習復習をすべて行えば合格できるという道標を作ってもらえます。それに従った結果、合格することができました。
合格したからこそ言える失敗談や反省点、受験期間中の印象に残るエピソード
最初の模擬試験でストレート合格をあきらめました
最初の模擬試験を受けたとき、分からない問題が多すぎて点数も教室内で下から5、6番目と悪い結果でショックを受けたのを覚えています。そのときストレートで合格するのは無理だろうと感じてしまいました。そのままの気持ちで勉強を続けていれば、合格はなかったと思います。しかし、一緒に勉強する仲間がいい点数を採っている姿を目の当たりにし、彼らに励まされたことをきっかけに、あきらめずにがんばろうという気持ちになりました。
周り(会社の同期や身近の先輩社員)の1級建築士に対する学習状況
上司は独学や他の資格学校に通っています
上司は独学で何年も受験している方もいれば、日建学院や通信の学校に通って合格している方もいます。独学の方は、業務の中で習得した知識で学科試験に挑んでいるように感じます。
当学院で学習した内容が、学校生活または就職活動などで活かせたエピソード
就職してすぐ役に立つ
行政職で、建築基準法や都市計画法等の法令を扱うのですが、就職してすぐに法規の知識が役に立ちました。大学ではほとんど勉強していない分野だったので、学院での勉強がなければ、法文の読み方も分かりませんでした。資格取得のために通っていると思っていましたが、結果的に仕事のキャリアアップにもつながる勉強でした。
得意科目と苦手科目
得意科目
苦手科目
得意にできた理由、もしくは苦手科目の克服法
語呂合わせをたくさん作る
私には現場の実務経験がないため、施工はイメージや興味がなかなか湧かず理解するのに苦労しました。無理にでも記憶に定着するために語呂合わせを作り、とにかく問題集を繰り返し解きました。そうすることで、本試験直前に点数を上げることができました。
学科学習時から正しく理解し、記述できるレベルまで実力を引き上げる指導で感じた効果
学科での指導は製図試験でとても役立つ
学科学習時、特に環境設備、法規、構造を正しく理解するまで勉強したことは、設計製図の記述でとても役に立ちました。ただ暗記しただけで学科試験に臨めば、製図試験のときに苦労すると感じました。
学科合格のポイント
最後まで絶対に諦めないことなかなか模試の点数が上がらなかったり、勉強するのが苦痛になったりしたときに、どれだけ踏ん張ることができるかが大事だと思います。私がそうすることができたのは、一緒にがんばる仲間やライバルと鼓舞し合い、協力することができたからです。自分ひとりの力では到底合格することはできなかったと思います。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
隙間時間に映像講義を滑油
講義で分からないことがあった時や復習したいときに、映像講義を活用しました。特に製図試験直前期では、エスキスの手順や考え方をすべての課題において理解しようと思い、隙間時間やお風呂の時間にも映像講義を見るようにしていました。その結果、エスキスの時にはあまり時間をかけすぎずにプランをまとめることができるようになりました。1回講義を受けても理解できないところを映像講義で補えることはありがたかったです。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
何度も練習すること
作図を学院の目標時間内で描き終えることは難しかったです。克服するためには何度も作図の練習をすること、製図道具をより使いやすいように工夫することで、より早く描けるようになりました。
学科対策期間中からやっておいてよかった、あるいはやっておけばよかったと感じたこと
学科の勉強に集中すること
学科対策期間中は、製図試験の対策について考えるよりも学科試験に集中することが大事だと考えます。学科試験でより高得点を獲得することで、学科の合格発表までの間に安心して製図の勉強に取り組むことができるため、製図合格の可能性が高くなると思います。
製図合格のポイント
最終チェック時間を確保すること私は本試験のときに、読解30分、エスキス1時間、記述1時間、作図3時間で描き終えました。そして最終チェックに1時間確保することができました。本来ならエスキスにもっと時間を費やすべきでしたが、プランがいつもより速くまとまったため、最終チェックに時間をかけ、問題文を隅々までチェックし、ミスを減らすことができました。法的に重大なミスを少しでも減らすことが合格のポイントだと考えます。

-
合格サイクル+継続学習
記憶の定着のための繰り返し学習は、暗記が得意ではない私にとってはとても効果的な学習方法だったと思います。課題だけでなく、復習テストや定着度テストのための勉強を毎週することで復習が十分にでき、点数を上げることができました。
詳細はこちら -
学科問題集
問題集を何周も解いて、過去問の全ての問題ができるようになれば合格には限りなく近づくという一つの目安がありました。直前期は新しい問題に取り掛かるのではなく、問題集を完璧にすることを目標にして勉強しました。
詳細はこちら -
教室マネージャー
スタッフの皆さんが、学習しやすい環境を作ってくださったおかげで、気持ちよく学習することができました。また、点数が思うように上がらないときには、激励の言葉をかけてくださいました。
詳細はこちら









