- 令和3年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 松島 功弥さん
SPECIAL INTERVIEW
自分にあった学習法を見つけよう
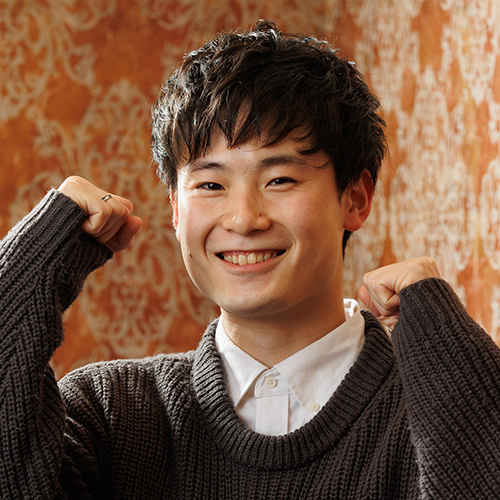
現在の仕事の道に進もうと思ったきっかけ
専門学校の設計課題が楽しかった
専門学校進学時に建設業界に進みたいという希望はあったのですが、さらに、設計という仕事を意識したのは、その専門学校で参加した、自由参加の設計サークルのようなものがきっかけです。さわりだけでしたが、設計についてのいろいろな話をきいたり、自分でも設計をしてみたりして、とてもおもしろいと感じました。
1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
お客様に安心してもらえる建築士になるために
仕事としては木造の注文住宅を扱うので、資格としては2級建築士だけでも良かったのですが、お客様からすれば1級建築士を持っている方が安心できるだろうと感じていました。会社からも応援してもらえたので、仕事量が増えて受験が難しくなってしまう前にと、受験を決意しました。1級建築士の資格を持つことで、深い知識を得られるとともに、勉強した分だけ仕事への誇りや自信を持てるのではないかと感じていました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
対面指導への期待
高校生のときは塾に通っていましたが、自習や映像がメインでした。なかなか集中できなくて、自習室でも寝てしまったという経験もあったので、自分一人では気が抜けるし、サボってしまうのではないかという不安がありました。集中して学習に取り組みたかったので、対面での講義がメインの総合資格学院を選択しました。
独学者と比べてみて、一番大きな違い
情報収集のしやすさ
独学の人と比べると、試験に関する様々な情報を得られると感じました。最新の試験の傾向は自分で情報を集めるのは難しいですが、学院では気軽に聞くこともできるし、教えてもらえるので助かりました。製図対策では他の受講生のミスなどから、自分が意識していなかった注意点などに気づくこともできたので、一人で学習するより得られる情報量は多かったと思います。
合格したからこそ言える失敗談や反省点、受験期間中の印象に残るエピソード
自宅学習の量が不足
講義ではそれなりに集中して取り組めたのですが、自宅学習ではサボってしまいがちになり、自分でエンジンをかけるのが大変でした。特に、製図対策では、家で座って学習する時間を取らなくてはいけないのですが、まとまった時間を確保するのに苦戦しました。アラームをつけて何時から学習するというように決めて取り組むようにしていましたが、集中という意味ではなかなか大変でした。
勉強時間のつくり方について、苦労した点・工夫した点
自宅で学習することの難しさ
自宅学習でサボりがちになってしまうのが課題で、時間を決めて取り組んでも集中が続かないなど、とても難しさを感じていました。そのため、個人的には講義できっちりやりきることを意識しました。講義では講師の方がその場で指導をしてくれますし、周りの受講生も真剣に取り組んでいるので、負けられないという気持ちになってがんばることができました。
当学院で学習した内容が、お仕事で活かせたエピソード
法規が役立つことが多い
自分の職場では木造の注文住宅を扱うので、延焼ラインや高さ制限など、法規については、仕事中でも、「学習したところだな」と感じることが多くありました。
講師によるライブ講義を受けて良かったこと
集中しやすく、効率的に学習できる
講師がその場にいることで、課題に集中して取り組むことができますし、わからないことがあればすぐに質問することができました。間違ったとらえ方をしたまま課題に取り組んでいるときにはすぐに「ここは違うよ」と指摘してくれるので、無駄なく効率的に学習できたと思います。また、周りに他の受講生がいることで考え方の幅を広げたり、自分が気づいていなかった注意点に気づくことができたりもしました。
(1)精度の高い図面を効率よくスピーディに描ける作図力、(2)作図時間の短縮によるエスキス/チェック時間の確保・表現豊かなプランニング、(3)ミスをなくすためのグループ添削採点実習など、講座の重点ポイントへの感想
エスキス時間短縮で心の余裕をつくる
作図のスピードがなかなか上がらなかったので、講師との相談の上、エスキスの時間短縮に注力しました。総合資格学院ではエスキスの手順が明確に決まっているので、ルーティンとして自分の中に落とし込み、無断な時間を無くしていくことで作図の時間を確保していきました。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
エスキスの時間と情報量
エスキスでは短い時間の中で、プランにどれだけの情報量を入れていくべきか悩みました。考えることが多すぎると自分でも処理しきれなかったり、時間がかかってしまったりしますし、逆に少なすぎると課題の要求を満たせていなかったりするので、ちょうど良い感覚をつかむのに苦労しました。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
作図スピードが上がらずに苦戦
昨年も製図試験にのぞんでいたのですが、その際は図面を描ききれず残念な結果となりました。そこで今年は一から作図の手順を見直して、作図時間を短縮することができました。ただ、それでも学院の中では作図が遅い方だったので、エスキスの時間短縮にも取り組んでいきました。講師からも「対策法は一人ひとり違うから、どう取り組むか考えよう」と言われていたので、相談して、自分なりの時間短縮ができたと思います。
設計製図試験において、学科対策期間中からやっておいてよかった、あるいはやっておけばよかったと感じたこと
高さ制限や延焼ラインなどの法規
法規で定められた基準はクリアできないと一発アウトになってしまう重要な部分ですが、学科対策の際にしっかり学習に取り組んで、製図対策に入る段階で十分に理解できていれば、気にしすぎることなく他のことに時間を取ることができると思います。あとは、設備に関わる範囲は、2級建築士ではそこまで取り組まないので、1級建築士受験の際には気をつけて覚えておいた方がいいと感じました。
製図合格のポイント
要求を満たした図面を描くあくまで試験なので、魅力的なデザインや設計の力よりも、どれだけ課題の要求を満たしているかが大切だと思います。また、記述が苦手で、本番のできも不安に思っていたのですが、結果的に合格できたので、やはりまずは図面がしっかりできていることが大切なんだろうと実感しました。

-
チューター
気軽に質問でき、レスポンスが早いので助かりました。講師の方とはまた違って、自分とも近い立場の方たちなので、チューターの方の受験経験などを聞くことで試験への対応力も身についたと思います。
詳細はこちら -
製図模擬試験
その理由:本番と同形式で自分がどこまでできるかを確認することができたので、今自分が何を学習すべきかがわかりやすくなりました。
-
グループ交換添削
グループ交換添削の際に、他の人のミスを通して、自分がたまたまミスしなかった箇所に気づくことが何回もありました。多くのミスを見ておくことで、本番で図面チェックをする際にも注意点を思い出すことができました。他の人のいろいろな作図を見ることで対応力を磨くことにつながったと思います。
詳細はこちら







