- 令和3年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 田中 望公さん
SPECIAL INTERVIEW
資格取得のための努力は最高の「自分磨き」
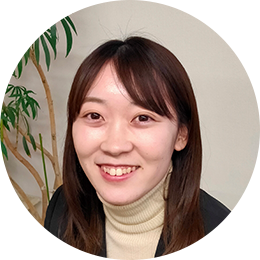
現在の仕事の道に進もうと思ったきっかけ
住宅の間取りをみることが好きだった
小学生のころ、住宅メーカーや不動産会社の広告を集めて住宅の間取りをよく見ていました。間取りを見て、「自分ならこの家に住みたい」「住んだらこんな生活がしてみたい」と考えることが好きでした。進路について考える時期に、自分の好きなことを仕事にできたら素敵だなと思い、「建設業界」へ進むことに決めました。
1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
会社と自分にとってプラスになるから
会社で取得が推奨されていたこと、自身のスキルアップに繋がると考えたため受験を決断しました。不安だった点は、実務経験のない新入社員が1級建築士試験を受験してもなかなか合格できないのではないかという点です。しかし、いつかは取得しなければならない資格だとわかっていたので、若いうちに挑戦することは決して無駄ではないと思い、覚悟を決めました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
合格実績がNo.1だったから
極力早く、効率的に資格を取得したかったので、合格実績No.1の総合資格学院に通うことにしました。また、総合資格はライブ講義のため、わからないところをすぐに講師に質問できる環境が整っています。私のように大学卒業してすぐ受験をめざす人にとっては、講義中にわからない単語や、理解するのに時間がかかる内容のものも多いと思うので、講師に質問しやすい環境が整っていることは大きなポイントでした。
ご自身と独学者を比べてみて、一番大きな違いは何でしたか。
「学習」を習慣化できるか、できないか
総合資格に通っていると毎週、講義・宿題・小テストをこなさなければならないため、学習することが自然と習慣化されます。1級建築士試験はやっつけ仕事でこなせる内容のものではないため、日々コツコツと学習することが大切です。この学習の習慣化が独学者との差になると思います。
合格したからこそ言える失敗談や反省点、受験期間中の印象に残るエピソード
時には息抜きも必要
受験期間中、どうしてもモチベーションが上がらない時期が何度かありました。モチベーションが上がらないまま勉強しても効率が悪いので、「今日は思いっきり休憩しよう!」と、家族で少し遠出して気分転換する日もありました。適度に息抜きをしていたから長期間の学習もがんばれましたし、気分転換に付き合ってくれた家族にはとても感謝しています。
勉強時間のつくり方について、苦労した点・工夫した点
長期間の学習はメリハリをつけること
私は「決まった場所で決まったことをする」ということを徹底しました。家では完全にオフモードになって勉強するスイッチがなかなか入らないので、資格の勉強は総合資格の自習室のみでやることにしました。自習室を利用することで、限られた時間のなかで集中して学習に取り組むことができました。1級建築士試験の学習は長期間に及ぶため、メリハリをつけることが大切だと思います。
当学院で学習した内容が、お仕事で活かせたエピソード
専門用語がわかる場面が増える
入社して様々な現場や打ち合わせに同行させていただく機会がありましたが、その際に上司や先輩が使う専門用語がわかる場面がいくつかありました。大学在学中から1級建築士試験の学習をしていたおかげで、新入社員ではありましたが専門用語がある程度わかったことは強みだと思います。
当学院指導の大きな特長である、講師によるライブ講義を受けて良かったこと
わからないことをすぐに質問できる
ライブ講義は疑問点をすぐに講師に質問できるので、講習日当日の理解度が高いと思います。わからないことをそのままにしておくと、その後の学習にも影響がでてくるので、すぐに質問ができる環境はとても良いと思います。また、他の受講生の質問から学ぶこともあるので、それもライブ講義の良い点だと思います。
(1)精度の高い図面を効率よくスピーディに描ける作図力、(2)作図時間の短縮によるエスキス/チェック時間の確保・表現豊かなプランニング、(3)ミスをなくすためのグループ添削採点実習など、講座の重点ポイントへの感想
学院が実施する学習は全て重要
作図の段階ごとに目安の時間が設定されていたので、自分がどこの段階で作図スピードが遅いのか把握しやすかったです。作図は時間との勝負なので、この時間設定はとても有効的だと思います。作図時間を学院の目標時間内に仕上げることが定着できたため、余った時間でチェックを十分に行えるようになりました。チェックをすることで、ミスの修正が可能になり、より精度の高い図面を描くことができるようになりました。グループ添削では他の人のミスを知ることで、一つの課題でいくつもの学びがありました。「明日は我が身」というように、次は自分がそのミスをするかもしれないという危機感を常に持つことができたので、グループ添削は有効的だと思います。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
物事を俯瞰してみることが大切
設計製図試験では、物事を俯瞰してみる力が試されていると感じました。夢中でエスキスをしていると、一見うまくプランができているようで大事なポイント(室の欠落、延床面積オーバー、不適切な構造計画等々)が抜け落ちているというのはよくあることです。そのミスが早期に発見できれば修正できますが、終盤で気づくともう手遅れ……というのは私も講義中に何度も経験しました。プラン全体を俯瞰するタイミングを意識して設けることで、ミスをひとつずつなくすようにしました。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
線種を変えるだけで、図面の印象が変わる
1年目は正しく作図手順を踏むことに精一杯で図面のクオリティはあまりよくなかったと思います。2年目は、図面のクオリティを上げることを意識しました。講師から「線種を変えると図面の印象がグッと変わる」とアドバイスをいただいたので、壁などの躯体は太い線、家具・什器は細い線、植栽等はやわらかい線で描くことを徹底しました。そのために自身が使いやすいシャープペンシルのメーカーや芯の濃さ、太さなども見つける必要があります。線種を使い分けて作図することを徹底していたため、本試験でどんなに急いで作図しても図面の印象度は1年目より確実に高かったと思います。
学科対策期間中からやっておいてよかった、あるいはやっておけばよかったと感じたこと
自分で説明できるレベルまで理解度を深めないと「記述」はできない
設計製図試験で一番苦労したのは設備・構造計画についての記述でした。学科ではマークシートで解くレベルでしか理解していなかったので、記述では手が止まったり、最後の行まで埋めることができないことが多々ありました。学科対策期間中から、自分で説明できるレベルまで理解度を深めておけばここまで苦労しなかったのではないかなと思います。
製図合格のポイント
設計製図試験の合否は試験開始30分で決まる設計製図試験の合否は試験開始30分で決まるというのを聞いたことがあります。つまり、課題文の読み取りが合否を分ける重要ポイントとなるといっても過言ではないということです。課題文の読み取りを誤ると出題者の要求に満たない図面ができあがってしまい、どんなに良いプランでも一瞬でランクⅣになります。講義で複数の課題文を読んでいると同じような条件の文章を何度も見て「またこの条件か」と軽く読んでしまいがちですが、そこに落とし穴が存在することもあります。課題文の内容に「いつも同じ」は存在しないため、丁寧に落ち着いて読むことが大切です。また、課題文は中間チェックや最終チェックのチェックリストとしても使用するので、わかりやすくマーカーで色分けをすると有効的です。それと、私の講師がよく言っていたのは、「人間は必ずミスをする生き物です。ミスをしても良いから、それを一つずつ解決すれば合格へ一歩近づく。」この言葉を胸に、本試験に臨みました。









