- 令和4年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 田口 将さん
SPECIAL INTERVIEW
気張らないでいつもの自分で
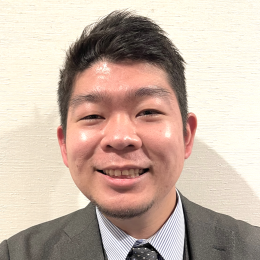
田口 将さん (28) 令和4年度 1級建築士合格
- 学歴:
- 大学
- 勤務先:
- 設計事務所(構造設計)
- 教室:
- 船橋校
計画:14点 環境/設備:15点 法規:25点 構造:28点 施工:17点
受講講座
- 受験回数:
- 学科2回/設計製図1回
現在の仕事の道に進もうと思ったきっかけ
大学での経験を活かしたい
私の大学は特殊で建築、土木、農業、機械など多岐にわたる分野の勉強ができました。専攻は建築で、以前は建設コンサルタントという職種で土木設計を生業としていました。大学で学んだ知識を活かしたいと考えるようになり、現在の設計事務所で構造設計をするようになりました。
1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
学院でできた友人と励ましあった
恥ずかしながら大それた理由はないのですが、1級建築士を持っていたらかっこいいなという理由で受験しました。一度学科試験で落ちてしましい2回目の受験のときは非常に不安に駆られましたが、総合資格学院でできた友人と励ましあったり、教務スタッフに相談したりすることで不安は解消できました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
2級建築士の受験の際に非常にわかりやすかった
2級建築士の受験の際にわかりやすい表現で講義してもらったため、1級建築士の勉強も学院に決めました。ライブ講義なので能動的な知識の詰め込みとはならず、講師も親身に対応してくれたのは今でも覚えています。
ご自身と独学者を比べてみて、一番大きな違いは何でしたか。
法規の理解度に違いがあった
ほぼ理系で占める建設業界にとって、法文の独特な読み回しや関係のある法文を引くのは苦手な人もいるのではないかと思います。独学で勉強している会社の同僚も苦手なようで、学院で学んでいる私とでは、法文への理解と法令集を引くスピードが明らかに違いました。また、仕事とのスケジュール調整がうまくできていなく、効率的な勉強ができていなかったように思えます。自分がわかった気になっていたものも講義によって明るみになるため、独学者にくらべ大きなアドバンテージがあると思いました。
合格したからこそ言える失敗談や反省点、受験期間中の印象に残るエピソード
モチベーションの維持
講義開始から本試験まで一年間ほどありますが、周りの友人の誘いを断って勉強するのが何よりつらかったです。一時期勉強を放り出して遊んでいたりもしましたが、学院に通う友人に正されて、再度勉強に励みました。
勉強時間のつくり方について、苦労した点・工夫した点
だらだら勉強するのではなく短期集中
私は集中力が長く保てない人間であると理解していたため、細かく時間を区切って勉強しました。例えば、夜に3時間やるのではなく、夜に1.5時間、朝早く起きて1.5時間勉強するスケジュールを組んでいました。また、学院から出される宿題は通勤の電車内ですべて終わらせて、法規などは机に向かって勉強しました。
当学院で学習した内容が、お仕事で活かせたエピソード
設計レビュー時での意見交換が以前よりできるようになった
構造計画を進めていくのに、職場では設計レビューを行うのですが、今までは聞くだけで終わっていた設計レビューも学院で学んだ地盤・基礎について意見を言えるようになりました。また、現場での検査時にチェックしなければならない数値などが施工の勉強で役に立ちました。
当学院指導の大きな特長である、講師によるライブ講義を受けて良かったこと
効率的な勉強
映像講義では自分がわかっている内容も一律して行わなければならず、効率的な勉強ができないと感じました。また、講師によっては独自で作成した教材を配布してくれたこともあり、受験者目線の資料がたくさんありました。すぐに質問ができる環境だったのは他の資格学校に比べて大きなアドバンテージになっていたと思います。
得意科目と苦手科目
得意科目
苦手科目
得意にできた理由、もしくは苦手科目の克服法
確実に取れるとこは確実にとる
計画の寸法関係や都市計画、建築作品など、私にとって苦手なものを寄せ集めたかのような科目でした。苦手な教科にたくさんの時間を割くことはせずに、得意な構造や施工でなるべく失点をしないようにしました。ただこの試験では足切りもあるので得意なものだけやっていればいいわけではないので、克服まではできませんでしたが過去問の問題は必ず失点しないように何度もトレイントレーニングを使って繰り返し学習しました。
設計製図試験を見据えた、学科学習時から正しく理解し、記述できるよう指導を行いましたが、感じた効果を教えてください。
スムーズに学習を遂行できた
学科講義時から、設計製図で使用する知識なのでしっかり覚えておくようにと講師から教えられており、設計製図時ではスムーズに講義に移れたように感じます。また、一部講義で製図を見据えた作図の講義もあり、作図についても同様にスピード感を持ってできたと感じています。
学科合格のポイント
土台をしっかりつくる学科試験を受けた際に感じたのは、驚くぐらい直前特別対策講座の内容が出ていたのを覚えています。苦手な計画は直前特別対策講座を受講することにより、模試でいつも足切りギリギリの点数だったのが14点まで上がったのはこの講座によるものだと思います。加えて問題文をしっかり読むことが重要になると思います。本試験では思いがけないひっかけ問題が出てくることもあります。勉強をたくさんすることで問題を思い込みで解き失点してしまったというありがちな話もよく聞きました。設計製図にもつながることで、基本中の基本ですが非常に大切なことだと思います。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
段階ごとの確認
はじめのころはやり方もわからず、手順を動画で確認したりして学習しました。通勤の電車内で確認し、仕事が終わり次第学校へ行き進めていくことで、できるようになっていきました。講義では学んだことを平日の自己学習でどれだけものにできるかがカギとなると思います。私の場合は1/1000で大方プランを決めてしまい、1/400の段階ではほぼすべての条件を詰め込むようにしていました。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
ひたすら描く
2級建築士の製図と違い、描く量が非常に多いため、最初のころはいつも時間オーバーしていました。どうすれば作図スピードを上げられるかを考えた結果、1/400のエスキス段階を作図用紙に移すだけのレベルまで完成させ、エスキスの内容は暗記して作図しました。
製図試験において、学科対策期間中からやっておいてよかった、あるいはやっておけばよかったと感じたことを教えてください。
エスキスで使用する法規、設備、構造の予備知識
学科試験だけでは設備の知識が薄かったため、実際設計製図の勉強をする際になにがなんだかわからなくなっていました。どういった形式の設備を求められていて、どういう室が必要になるかなど、そういった講義が前もってあれば良いと思いました。2カ月の期間ではあまりにも少ないと感じます。
製図合格のポイント
チューターの存在講師よりも受験生に近い存在で、受験生が躓きやすい、わかりにくいポイントなどを的確に教えてもらえました。また、メンタル面でのサポートもしていただき、試験前の不安なこともたくさん相談させていただきました。










