- 令和4年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 髙橋 克行さん
SPECIAL INTERVIEW
最後まであきらめない!!
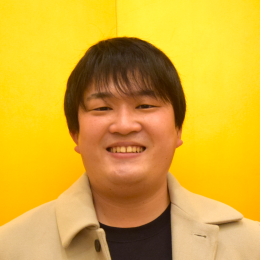
髙橋 克行さん (26) 令和4年度 1級建築士合格
- 学歴:
- 工業高校
- 勤務先:
- 建設会社(施工管理)
- 教室:
- 大分校
計画:14点 環境/設備:15点 法規:26点 構造:22点 施工:16点
受講講座
- 受験回数:
- 学科2回/設計製図1回
現在の仕事の道に進もうと思ったきっかけ
建設した建物が残る
祖父が大工をしており、中学生のときに建築について興味を持ったため、高校は建築科のある高校に進学しました。就職のときに先生方からつくった建物は何十年も形として残ると聞き、自分もそのような建物をつくりたいと思い、現在の現場の施工管理の仕事を選びました。
1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
挑戦
受験を決断した理由は、施工管理をしていても建設業界で働いていれば建築士を取れるということだったので、チャレンジしてみようと思い受験しました。また、2級建築士を勉強しているときに、さらに建築についての知識を増やしたいと思い1級建築士を受験しました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
総合資格学院は合格実績がNo1
一番初めに声を掛けてもらいライセンスアドバイザーの熱心なアプローチを受けたからです。また、声を掛けてもらった際に学院の実績を教えてもらい、合格実績がNo1と話を聞いたので、その場で学院に行こうと思いました。
ご自身と独学者を比べてみて、一番大きな違いは何でしたか。
仲間
同じ資格をめざすもの同士で、競争相手になったり、教えあったり、仲間がいるかいないかが一番の違いです。特に製図は、仲間がいることにより、今まで自分が持っていなかった知識や考え方を共有できたりするので、独学者と比べて知識の幅が広がります。
合格したからこそ言える失敗談や反省点、受験期間中の印象に残るエピソード
最後まであきらめない!!
自分は学科を2回、製図を1回受けました。実際学科は95点以上、製図はランクⅡ以上を取ったことがありませんでした。合格できたのは気持ちを切らさずに最後まであきらめなかったので合格できたと思っています。
勉強時間のつくり方について、苦労した点・工夫した点
休憩時間の有効利用
仕事の昼休みを利用して勉強していました。同僚と一緒の空間にいると、気持ちが負けてスマホを触ったり、昼寝をしてしまうので、昼休み中1人で現場の休憩所で勉強していました。1人でいると集中できるので効率良く勉強ができました。
当学院で学習した内容が、お仕事で活かせたエピソード
実際の現場に照らし合わせる
計画や環境・設備、法規、構造で、現場では知らないようなことを実際の現場に照らし合わせたときにイメージがつき、施工管理の仕事が楽しくなっていったことです。
当学院指導の大きな特長である、講師によるライブ講義を受けて良かったこと
苦手分野の発見
講義が終わってから、必ず講師と話をして1週間のスケジュールを立てていました。特に製図になってからはスケジュール管理を更に細かくしていき、講師と話をして苦手分野や自分のプランの傾向などを炙り出して克服していきました。
得意科目と苦手科目
得意科目
苦手科目
得意にできた理由、もしくは苦手科目の克服法
アプリを使用して過去問を何度も解く
施工は仕事で現場管理をしているため、立体的に想像ができたのでスムーズに覚えられたためです。構造の計算問題は毎日解いて、わからない問題はわかる人に聞いて克服していきました。文章問題は無料のアプリをダウンロードして通勤や休憩時間などの隙間時間に過去問を何十往復も解いていました。
設計製図試験を見据えた、学科学習時から正しく理解し、記述できるよう指導を行いましたが、感じた効果を教えてください。
簡単な図を描き立体的に想像する
簡単な図を描き、立体的に想像することで理解をしやすいように勉強しました。そのおかけで正しく理解できて記述もかけるようになりました。
学科合格のポイント
最後の1週間の使い方プラン通り勉強している人は、最後の1週間でどれだけ質の良い勉強をできたかで変わってくると思います。周りを見ていると最後の1週間で急激に伸びている人もいます。自分は昨年度の受験では最後自分の苦手な部分しか勉強をしなかったため、ほかの教科が疎かになってしまい落ちてしまいました。そのため最後は得意、不得意関係なく勉強したほうが良いと思います。そのうえで時間があるのであれば苦手分野を集中的に勉強したほうがいいと思います。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
復習を必ず行うこと!!
正直はじめて行うことばかりなので、わからないことだらけでした。しかも自分は体調不良で初回の講義に参加することができませんでした。そのため常に自分は周りより遅れていると自覚して、毎回講義に望んでいました。その際に、エスキスや記述は必ず復習を行って、特に学院から戻してもらった答案用紙は、時間があれば何度でも読み返していました。自分のなかでは、今できなくても最後には全部できるように復習を心掛けていました。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
字を丁寧に書く
自分は字がきれいではありません。人に見てもらうものなので丁寧に書くように心がけていました。ただ、字が汚いと怒られていました。(笑)
製図試験において、学科対策期間中からやっておいてよかった、あるいはやっておけばよかったと感じたことを教えてください。
字を書く練習
正直、字を書くことが一番苦労しました。字を書くことは仕事や勉強でも使うのでもっと丁寧に書けるように練習していればよかったです。
製図合格のポイント
スケジュール管理学科合格後すぐに製図試験までのスケジュールを決めました。具体的に8月盆休みまでに作図を2時間半で描けるようになり、9月末までにエスキス、記述を徹底的にやりこみ、10月からは苦手分野を中心に勉強していくというスケジュールです。あとは教務スタッフや講師と毎週話をして、今は自分が何をすれば良いのか、苦手な分野はどこなのか、1週間の勉強内容など、自分が納得するまで話をしてスケジュール管理をしていました。そのおかげで製図の試験も自信を持って受けることができました。

-
製図直前特別対策講座
単刀直入に言うとこの講座がなかったら合格できていませんでした。今までの課題になかった内容が出てきて、そういうことも可能性としてあるんだと思いながら受験に臨んだら、そのままの内容で出てきたのでこの講座のおかげで合格できたと思っています。
-
製図模擬試験
1回目の模擬試験の中間確認で大きなミスをしてしまっていることに気づき、そのときは時間もなくて無理矢理プランをずらして滅茶苦茶な図面ができてしまいました。この経験があったからこそ、製図は確認作業が一番大事な作業ということに気づけて、その時間を確保するために作図スピード、エスキスなどを速くできるように勉強していきました。ちなみに本試験では最後1時間以上余ったので5回最終チェックをしました。
-
教務スタッフ
毎週講義後に、1週間の勉強内容などを相談してもらったり、わからないところを丁寧に教えてもらったり、人生相談を聞いてもらったりなどと、本当に助けられました。
詳細はこちら









