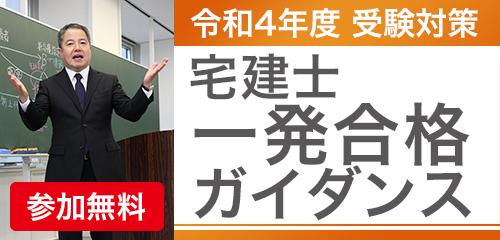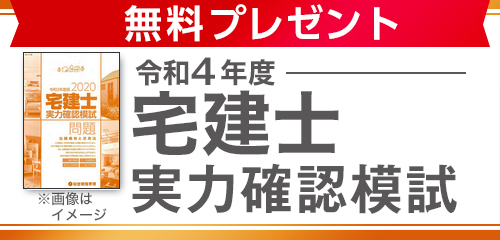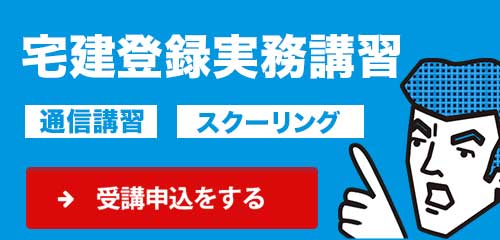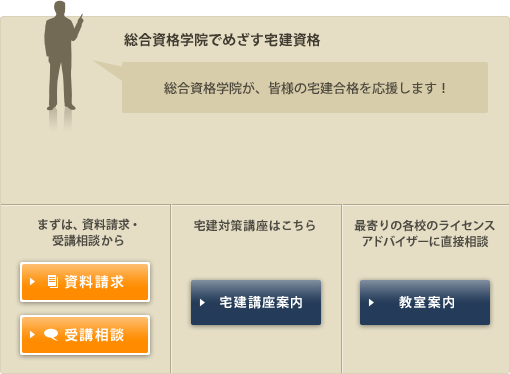令和3年度 宅地建物取引士資格試験 総評
総評
●出題内容
権利関係における改正民法等、例年同様に新規の出題が目立ちました。また、基礎知識や過去頻出項目であっても、切り口を変える等、応用力を問う問題が散見されました。
●出題形式
宅建業法の個数問題(※)は5問で、令和2年の10月実施試験の4問よりも1問増加しました。
また、権利関係でも個数問題が1問出題された。その他は例年通りであり、権利関係の判決文問題も1問出題されました。
全科目を通して、令和2年度と同様に、過去頻出項目やその周辺知識からの出題が多く見られた一方、改正民法等の改正法に関する知識や初出題項目が出題されたことに加え、細かい知識が出題されたりするなど、得点しにくい問題も散見されました。
また、内容的には基礎的なものであっても、切り口や表現を変えて出題する等、応用力を問う問題も出題されました。
一方、特に宅建業法を中心に、きちんと基礎知識や過去出題項目を学習することで確実に得点できる問題も例年通り出題されています。
全体を通して、過去出題項目やその周辺知識を確実にした上で、応用力が問われる問題や初出題項目について、得点をどれだけ積み上げられたかがポイントとなりました。
- ※個数問題とは、「正しいものは“いくつ”あるか」と問われ、「1 一つ」「2 二つ」というように、正しい(誤り)選択肢の数を答える出題形式です。全ての肢を検討しなければならないため、一般的に難易度は上がります。
各科目の出題状況
(1) 権利関係
●令和2年度の12月実施試験で出題されなかった判決文問題は、1問出題されました。また、昨年出題されなかった「抵当権」が今回も出題されなかった一方で、「相続」分野から2問出題されました。
●改正民法の知識が数多く出題されたのは令和2年と同様でしたが、出題分野に関しては「債権」分野の比重が高くなり、点数が取りにくい内容となりました。
民法改正により、多くの判例が条文化されましたが、令和2年度の10月実施試験と同様に、判決文問題は今年も1問(【問1】)出題されました。また、民法の出題10問のうち、意思表示、代理、不動産物権変動、抵当権等の、「民法総則」「物権」分野における頻出項目からの出題が影を潜め、「債権」分野から多く出題された点が特徴的でした。
内容的には、【問2】連帯債務、【問4】配偶者居住権、【問6】債権譲渡、【問7】売買、【問10】選択債権で改正民法に関する肢がちりばめられ、一部の肢では難解な内容も見られました。【問11】〜【問14】の特別法4問は、例年通りの難易度であったと思われる。
(2) 宅建業法
宅建業法の個数問題は5問と、令和2年度の10月実施試験の4問と比べて1問増加しました。
●近時の法改正の内容を深堀りした問題や、過去問にはなかった出され方により応用力を問う問題も散見されたため、令和2年度の10月実施試験と比べて若干難化したと考えらえます。
問題の形式面として、令和2年の10月実施試験で4問出題された個数問題は5問に増加しています。
その他、出題順が条文の順とは関係なくバラバラになって出題されている点は、近年の傾向であり、今後もこの傾向は続くと考えられます。
内容的には、令和3年度の法改正点である、いわゆる「水害ハザードマップ」が【問33】でまるごと1問出題されたり、重要事項説明であっても問い方が工夫された【問36】、頻出項目である“専任”媒介契約ではなく、“一般”媒介契約の切り口で出題された【問38】など、やや細かい知識や応用力を問う出題がされており、難解に感じた受験生も多かったものと考えらえます。
法改正に関する正確な知識や応用力が試験対策として重要であることが改めて証明されました。
(3) 法令上の制限
●例年通りの出題項目であり、「国土利用計画法」も昨年と同様に【問22】で出題されました。
●都市計画法や建築基準法で細かい知識が出題されたため、全体的には難化しました。
令和3年度も、令和2年度と同様に、都市計画法、建築基準法から各2問、宅地造成等規制法、土地区画整理法、農地法、国土利用計画法から各1問が出題され、その他の法令上の制限は出題されませんでした。
内容的には、都市計画法の2問と建築基準法の2問において、初出題の内容も含まれ、難解と感じた受験生が多かったと考えられます。
上記4問以外で得点を積み重ね、都市計画法と建築基準法で得点を上乗せできたかがポイントになったと考えられます。
(4)税・その他
●税と価格に関しては、国税では「所得税」が出題され、他は、令和2年度の10月実施試験と同じ「不動産取得税」「不動産鑑定評価基準」が出題されました。
●5問免除科目では、【問47】の公正競争規約で、やや細かい知識が出題されました。
税・価格は、【問23】所得税、【問24】不動産取得税、【問25】不動産鑑定評価基準が出題されましたが、どれも、細かい内容や初出題の内容が含まれ、全体的に難しく感じた受験生も多かったと推察されます。 5問免除科目は、【問47】で若干細かい内容が問われたものの、その他は比較的解答しやすい問題が多く、確実に得点すべき内容であったといえます。
令和4年度に向けた学習対策
権利関係の分野では、例年よりも分野の偏りが見られ、内容的にも新規出題が含まれるなど、若干傾向の変化が見られました。
その他の科目でも新規の内容が出題されたり、応用力を試す問題が増加するなど、令和2年度と比べて難化の傾向にあります。
このため、今後の宅建試験は、基礎知識や過去出題項目を早い段階で押さえた上で、法改正の正確な知識を押さえ、アウトプットを通じて様々な応用問題・新規問題を解きこなすことが要求される試験と言えます。
この点で、法改正の情報量やアウトプット量に劣る独学では、ますます合格が困難な試験になっていると言えます。
令和3年度 宅建本試験 『解答・解説書』

【先行予約受付中】
令和3年度宅建本試験を丁寧に解説した当学院オリジナルの「解答・解説書」。解答だけではなく、
全問題に専門指導校ならではの詳細な解説を掲載。正誤の根拠と本年度試験の出題傾向が正しくわかる教材を
応募頂いた方全員に無料でプレゼントします!
- ※プレゼントの発送は11月上旬以降となります。
- ※解答・解説書は当学院が独自に作成するもので試験実施機関とは一切関係ありません。
- ※写真は前年度版です。
2022年度版 『宅建実力確認模試』

【先行予約受付中】
【令和4年度対策教材】令和4年度 合格のために厳選した問題で構成されたオリジナル模擬試験です。本試験と同様の形式で構成された模擬試験なので、初受験の方は宅建試験を知るために、受験経験のある方は、実力確認に最適です。
詳しい解説書付きで、正誤の根拠がしっかり理解できます。
- ※発送は、11月中旬以降となります。
- ※写真は前年度版です。