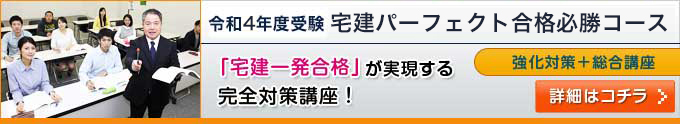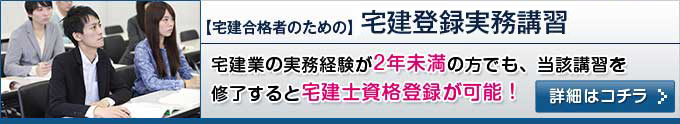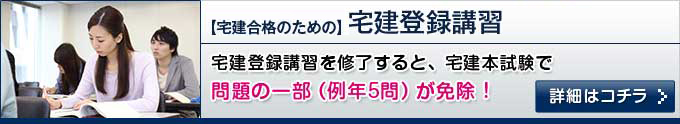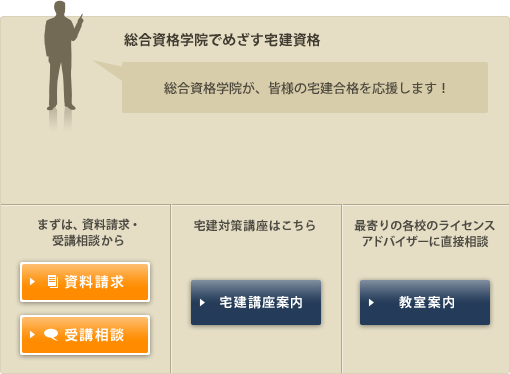令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月19日実施) 総評
総評
【出題内容】
令和3年度12月実施試験は、10月実施試験と同様に、「権利関係」を中心に新規の出題や応用力が問われる問題が目立ちました。一方、「宅建業法」では過去頻出項目からの出題が多く、これらの問題で得点できたかどうかが重要でした。
【出題形式】
「宅建業法」では、個数問題(※1)が10月実施試験と同様5問出題されたほか、組合せ問題(※2)が1問出題されました。また、「権利関係」では、10月実施試験と同様、判決文問題が1問出題されました。
※1:個数問題…「正しい(誤った)ものは“いくつ”あるか」と問われ、選択肢の中から正しい(誤った)選択肢の数を答える出題形式。すべての選択肢の正誤を判定できないと正解できないため、難度が高い。
※2:組合せ問題…「正しい(誤った)ものの“組み合わせはどれか”」と問われ、選択肢の中から正しい(誤った)選択肢の組み合わせを答える出題形式。1つの選択肢だけ正誤が判定できても正解にはたどり着かないため、難度が高い。
令和3年度12月実施試験は10月実施試験と同様に、「権利関係」を中心に初出題項目や細かい知識を問う問題が出題されたり、内容は基礎的なものでも問題の切り口や表現を変化させ、応用力や文章読解力を問う問題が出題されたりするなど、得点しにくい問題が見られました。
一方、特に「宅建業法」を中心に基礎知識や過去出題項目の学習によって確実に得点できる問題が出題されており、「宅建業法」を得点源にできたか否かが合否をわけたと考えられます。
全体を通して、過去出題項目やその周辺知識に関する問題で取りこぼしを最小限にとどめたうえで、初出題項目で得点をどれだけ積み上げられたかがポイントでした。
各科目の出題状況
(1) 権利関係
●10月実施試験同様【問1】で判決文問題が出題されました。一方、10月実施試験では出題された個数問題は見られませんでした
●過去問対策だけでは対応できない知識が問われたり、過去に出題された問題が問題文の表現を変化させて出題されたりするなど、解きにくい問題が多く出題されました。そのため、点数を取るべき問題でしっかり得点できたかどうかがポイントとなりました。
10月実施試験と同様に、【問1】で判決文問題が出題されました。民法改正を経て多くの判例が条文化されましたが、判決文問題は今後も出題されると考えられます。
一方、10月実施試験では、代理などの「民法総則」分野や抵当権などの「物権」分野からの出題は見られませんでしたが、12月実施試験ではこれらの分野からもバランスよく出題されており、こうした点で10月実施試験と異なる点が見られました。内容でも、【問1】自力救済、【問2】相隣関係、【問7】遺言・遺贈、【問8】契約の成立などで、過去に出題されたことがない内容が散見されたほか、【問11】借地で難しい判例知識が出題されたり、【問13】区分所有法で過去に出題されたときとは異なる切り口の問題文が正答肢になっていたりなど、解きにくい問題が多かった。そのため、確実に正解できる問題でいかに取りこぼしなく得点できたかが非常に重要でした。
(2) 宅建業法
●「宅建業法」の個数問題は5問で、10月実施試験と同じ出題数でした。一方、10月実施試験では出題されなかった組合せ問題が1問出題されました。
●初出題の内容を含む選択肢も若干見られましたが、他の選択肢の正誤を判断することで正解を導ける問題も多く、10月実施試験と比べても解きやすかったと考えられます。
問題形式としては、組合せ問題が1問出題されたものの、個数問題の出題数は10月実施試験と同様であり、解答にあたって特に混乱する点はなかったと考えられます。
内容としては、【問28】で平成19年以来となる「両罰規定」が出題され、【問39】で「保証協会の届出」が初めて出題されるなど、選択肢ごとに見るとやや細かい知識も出題されていましたが、全体を通してみれば、取り組みやすい問題が多かったと考えられます。近年の法改正に関する知識が【問35】や【問44】でしっかりと問われている点も含め、過去出題項目や法改正に関する知識を確実におさえて、「宅建業法」で得点を稼ぐことができたかどうかが今回の試験の合否のポイントになったと考えられます。
(3) 法令上の制限
●例年通りの出題構成であり、「国土利用計画法」も令和2年度試験、および今年度の10月実施試験と同様に【問22】で出題されました。
●近時の法改正からの出題はなかった半面、初出題の知識や過去出題時から問題の問い方を変化させた出題が散見されました。確実に正解すべき問題で取りこぼしがなかったかどうかが重要でした。
問題形式は例年通りであり、「都市計画法」、「建築基準法」から各2問、「宅地造成等規制法」、「土地区画整理法」、「農地法」、「国土利用計画法」から各1問が出題され、その他の法令上の制限は出題されませんでした。
内容としては、【問17】【問18】建築基準法で初出題の知識が多く問われ、また、【問22】国土利用計画法の正解肢の出題のされ方が過去に出題されたときと異なるものだったため、悩んだ受験生も多かったと考えられます。確実に正解すべき問題で得点を積み重ねることが重要でした。
(4)税・その他
●税と価格の出題項目は10月実施試験とすべて異なり、「登録免許税」、「固定資産税」、「地価公示法」が出題されました。
●5問免除科目は、統計に関する【問48】の出題に変化がありましたが、概ね過去出題項目の対策で正解できるものが多く、少なくとも4点は確保したい内容でした。
「税・価格」は、【問23】登録免許税、【問24】固定資産税、【問25】地価公示法と、10月実施試験とすべて異なる項目が出題されました。
内容としては、【問24】固定資産税がやや詳細な知識を問う問題だったものの、【問23】と【問25】は過去出題項目からの出題であり、確実に正解すべき問題だったと言えます。
5問免除科目は、【問48】統計の出題のされ方に傾向の変化があった点が特徴的でしたが、概ね標準的で、少なくとも4問は得点すべき内容でした。
令和4年度試験に向けた学習対策
近年の「権利関係」では、改正民法の知識も含め、過去に出題されていない内容や応用力を問う問題が比較的多く出題される傾向があります。一方で、「宅建業法」を中心に、過去出題項目に関する問題も多く出題されており、過去問対策の重要性に変わりはありません。このため、近年の試験対策では、基礎知識や過去出題項目を速い段階でおさえた上で、法改正の正確な知識をおさえ、アウトプットを通じて様々な応用問題・新傾向問題を解きこなすことが重要だと考えられます。
こうした点から、法改正など、最新の情報を入手することや新しい傾向の問題でアウトプットトレーニングを行うことが難しい独学での合格は難しくなっていると考えられますので、確実に合格をつかみたい方は、資格スクールのご利用がおすすめです。
総合資格学院では、受講生の理解度に沿った指導で、合格に向けて確実にステップアップしていける「令和4年度 宅建パーフェクトコース」の受講を受け付けております。令和4年度受験をお考えの皆さんは、ぜひ受講をご検討ください。
令和3年度 宅建本試験(12月19日実施) 『解答・解説書』

【先行予約受付中】
令和3年度宅建本試験を丁寧に解説した当学院オリジナルの「解答・解説書」。解答だけではなく、
全選択肢に専門指導校ならではの詳細な解説を掲載。正誤の根拠と本年度試験の出題傾向が正しくわかる教材を
応募頂いた方全員に無料でプレゼントします!
- ※プレゼントの発送は1月下旬以降となります。
- ※解答・解説書は当学院が独自に作成するもので試験実施機関とは一切関係ありません。
- ※写真はイメージです。
2022年度版 『実力確認模試』

2022年度合格のために厳選した問題で構成されたオリジナル模擬試験です。本試験と同様の形式で構成された模擬試験なので、初受験の方は宅建試験を知るために、受験経験のある方は、実力確認に最適です。
詳しい解説書付きで、正誤の根拠がしっかり理解できます。
- ※写真はイメージです。