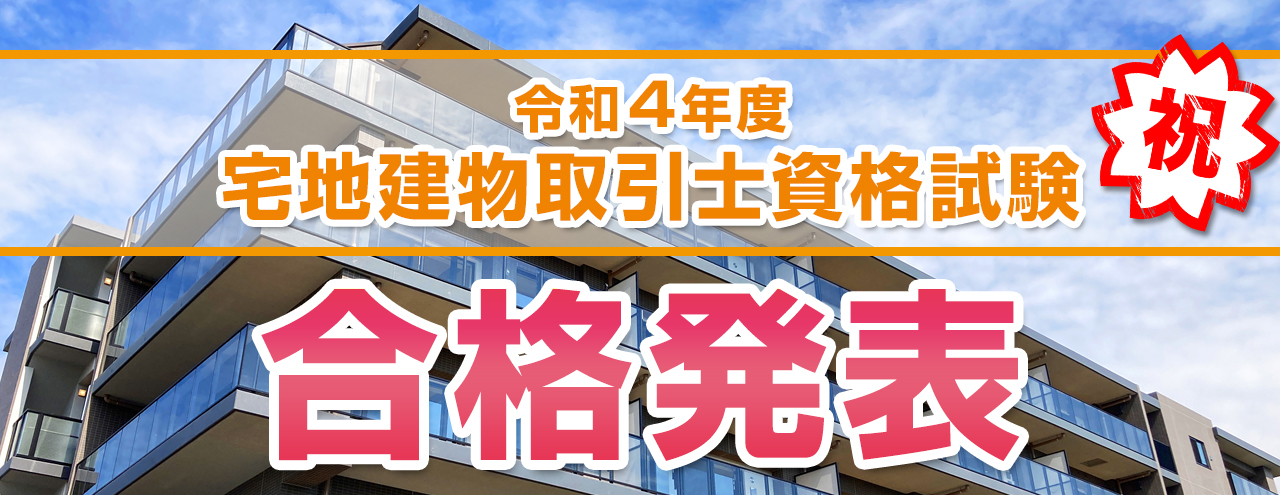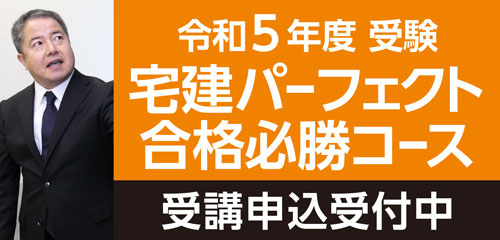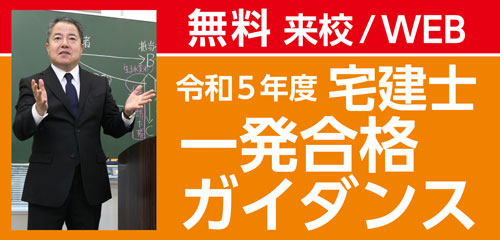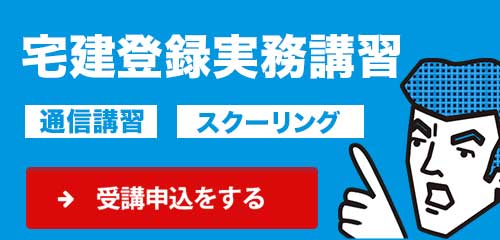令和4年度 宅地建物取引士資格試験 合格発表
令和4年11月22日(火)に、10月16日に実施された令和4年度宅地建物取引士資格試験の合格発表がありました。概要は下記の通りです。
| 全体 | 登録講習修了者 | |
|---|---|---|
| 受験者数 | 226,048人 | 47,000人 |
| 合格者数 | 38,525人 | 8,151人 |
| 合格率 | 17.0% | 17.3% |
| 合否判定基準 | 50問中36問以上正解 | 45問中31問以上正解 |
総評
10月16日(日)に実施された令和4年度試験について、受験者数は226,048人、 合格者数は38,525人となり、 合格率は17.0%でした。 合格判定基準は、50問中36問以上正解となりました。
- ※登録講習修了者については、受験者数47,000人、合格者数8,151人、合格率17.3%となり、合格基準点は45問中31問以上正解となりました。
全体の結果を令和3年度(10月実施試験)と比較すると、
合格率は0.9%低下し、
合格基準点は昨年の34点より2点高い36点となりました。
※(一般財団法人)不動産適正取引推進機構より、令和4年度試験の問48について、全ての解答を正解として取り扱う旨の発表がありました。以下に発表内容を掲載いたします。詳細は必ず、試験実施機関ホームページをご確認ください。
“※ 問48の選択肢4の記述中、「第1四半期から第4四半期まで連続で対前期比増となった」とありますが、令和4年9月30日国土交通省発表のデータ改訂に伴い、第2四半期の対前期比は同年8月31日発表の「+0.7%」から「▲(マイナス)0.0%」に改訂されており、問48は正解肢のない問題となっていることが判明しました。このため、問48については、全ての解答を正解として取り扱うことといたします。このような事態が生じたことをお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。”
試験の特徴
出題内容について、権利関係は例年同様に新規の出題が目立ちました。また、その他の科目においても近年の法改正や実務的な知識を問うものなど、過去問学習だけでは対応できない問題が散見されました。出題形式については、宅建業法の個数問題(※)は5問出題され、令和3年度の10月実施試験と同様の出題数となりました。また、権利関係でも個数問題が1問出題されました。その他の出題形式は例年通りとなり、権利関係の判決文問題も1問出題となりました。
全科目を通して、令和3年度と同様に、過去頻出項目やその周辺知識からの出題も見られた一方、改正法に関する知識や初めて出題される項目、細やかな知識が問われる出題など、得点しにくい問題も散見されました。また、民法の出題分野については出題傾向の変化が見られました。その他、内容は基礎的なものでも、切り口や表現が変えられて出題されるなど、応用力が試される出題がありました。特に宅建業法を中心に、きちんと基礎知識や過去出題項目を学習することで確実に得点できる問題が例年通り出題されました。
全体を通して、過去出題項目やその周辺知識を確実にした上で、改正法に関する知識や初めて出題される項目、及び応用力が問われる問題において、得点をどれだけ積み上げられたかがポイントとなりました。
- ※ 個数問題とは、「正しいものは“いくつ”あるか」と問われ、「1 一つ」「2 二つ」というように、正しい(誤り)選択肢の数を答える出題形式です。全ての肢を検討しなければならないため、一般的に難易度は上がります。
今後の試験対策
過去問からの出題など基本的な内容からの出題がみられる一方、法改正事項や実務的な内容からの出題もあり、また、出題形式に変化を加え、問題への対応力を問う問題が出題されています。このため、今後は、基礎知識や過去出題項目を早い段階でおさえた上で、法改正の正確な知識を習得し、アウトプットを通じて様々な応用問題・新規問題を解きこなすことが、ますます重要となります。
当学院講座について
当学院では、現在、令和4年度の出題傾向を踏まえ、令和5年度講座の受講生を募集しています。
【当学院宅建士講座の特徴】
◆試験前年の11月から早期対策講座(必修項目修得講座)で基礎固め!
◆基礎を学んだ後、本講座(宅建合格必勝コース)で本試験で出題される項目を漏れなく学習!
◆試験直前には、「演習講座」や「模擬試験」などで弱点の把握や知識の補強を行い総仕上げ!
◆教材・カリキュラムは、「毎年改訂」!令和2年の民法大改正を含む「直近5年間の主要な法改正点を網羅」!
過去問の習得はもちろんのこと、法改正や初出題を想定したオリジナル問題を多く出題し問題対応力及び得点力強化を徹底。また、実務的な知識も解釈・運用の考え方について宅建業法の法令集を用いて学習するなど十分な対応を行っています。 令和5年度に宅建士試験の合格をめざす方は、ぜひ受講をご検討ください。