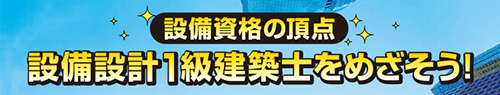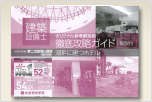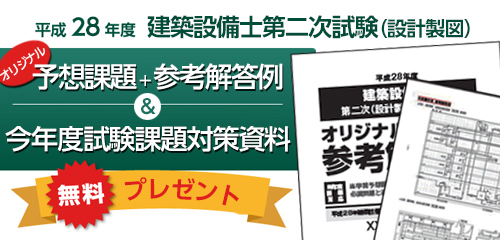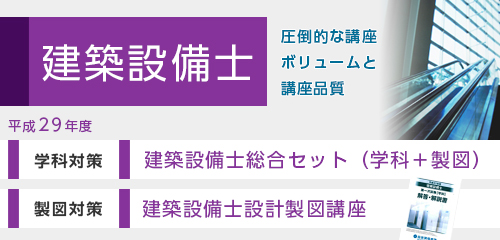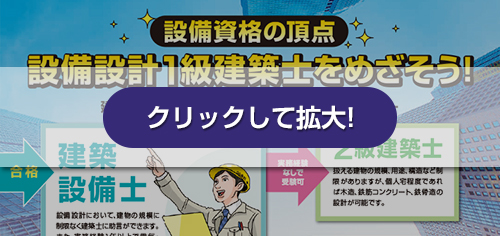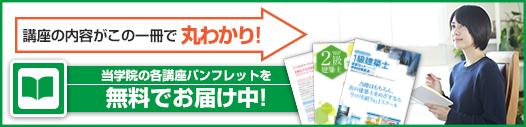����28�N�x ���z�ݔ��m ��j������ ���i���\
����28�N10��27��(��)�ɁA����28�N�x ���z�ݔ��m�����u��j�������v�i�v���}�j�̍��i���\������܂����B�T�v�͉��L�̒ʂ�ł��B
| ���Ґ� | 1,071�l (�O�N 1,061�l�A�ΑO�N 10�l��) |
|---|---|
| ���i�Ґ� | 601�l (�O�N 554�l�A�ΑO�N 47�l��) |
| ���i�� | 56.1���i�O�N 52.2���j |
| �̓_���ʂ̋敪 | �̓_���ʂɂ��ẮA��ʂ���]���`�A�]���a�A�]���b�A�]���c�̂S�i�K�敪�Ƃ���B�Ȃ��A�̓_�̌��ʁA���ꂼ��̊����́A���̂Ƃ����B
�]���`�F56.1�� �@�@�@�@ �]���a�F30.4���A �]���b�F9.5���A �]���c�F4.0�� |
| ���i� | �̓_���ʂɂ�����u�]���`�v�����i�Ƃ���B |
���]
10��27��(��)�@����28�N�x�@���z�ݔ��m�����(�v���})�̍��i���\������܂����B
���Ґ��́A1,071�l �ō�N��1,061�l���10�l�̑����A���i�Ґ���601�l�ō�N��554�l���47�l�̑����A���i����56.1���ƍ�N��52.2�����3.9���������܂����B
�̓_���ʂ̋敪�ɂ��ẮA�]���`�F56.1���A�]���a�F30.4���A�]���b�F9.5���A�]���c�F4.0���ł����B
���i�҂̑����ɂ��ẮA�E��ʂł́u�ݔ��֘A�E��v��4.1%�̑����A�Ζ���ʂł́A�u���z�v�������v�A�u���݉�Ёv�����ꂼ��3.3%�A1.6%�������܂����B�w�i�Ƃ��āA����27�N6���{�s�̌��z�m�@�����ɂ��A�y���זʐ�2,000�u���錚�z���̌��z�ݔ��ɂ��Č��z�ݔ��m�̈ӌ������Ƃ��w�͋`���z�ƂȂ������Ƃ��������܂��B2020�N�ɏȃG�l�@�ɂ��ȃG�l��K���`�����V�z���z���Ɋg�傷�邱�Ƃ��l������ƁA���ƊE�Ō��z�ݔ��m�̕K�v������荂�܂��Ɛ��@����܂��B
�u�N��ʁv�ł́A�u29�Έȉ��v�Ɓu45�Έȏ�v���������܂����B
�u29�Έȉ��v�̑����ɂ��āA�[��������Z�p�ҕs���̒��ŁA���Z�p�҂̈琬�͍������������g�݂ƂȂ��Ă���A���̎��g�݂��t���������̂ƍl�����܂��B�܂��A�����̊�Ƃ����Ј��ɑ����̎��i�擾��v�����Ă������Ƃ��w�i�Ƃ��čl�����܂��B
�u45�Έȏ�v�̑����ɂ��ẮA���擾�҂ɂ��āA��Ƒ����玑�i�擾�̗v��������Ă������̂ƍl�����܂��B���̌X���́A���z�m�A�{�H�Ǘ����i�ł��A���l�̌X�������Ď��邱�Ƃ���A���ƊE�S�̂ł̌X���ƍl�����܂��B
���i�擾�̃����b�g
�u���z�ݔ��m�v�擾�����b�g�̔w�i�Ƃ��āA2020�N�x�Ɏ{�s�\��̏ȃG�l�@�ɂ��ȃG�l��K���`�������������܂��B�ȃG�l������ɂ́A�l�X�Ȍ��z�ݔ������Đݔ��Ɩ�����舵�����Ƃ��ł���Z�p��m�����v������邽�߁A���ƊE�ɂ����āA���z�ݔ��m�̃j�[�Y�͍���A���܂��Ă����ƍl�����܂��B
�܂��A���z�ݔ��m�ɍ��i���邱�Ƃɂ��A�Q�����z�m�Ɠ����ȏ�̒m���y�ыZ�\��L����҂Ƃ��ĔF�߂��A�Q�����z�m�ɂ��Ă͎����o���Ȃ��ŁA�܂��P�����z�m�ɂ��Ă͂S�N�ȏ�̎����o����v���Ƃ��āA���i���t�^����܂��B����ɁA�ݔ��v�P�����z�m�u�K����u����ꍇ�A���z�ݔ��m�̎��i��L���Ă���A�u�`�y�яC���l���̂����A����z�ݔ��Ɋւ���Ȗڣ���Ə�����܂��B�܂��A���z�ݔ��m�Ƃ��āA���z�ݔ��̐v�E�H���Ǘ��ɂ����āA���z�m�Ɉӌ����q�ׂ�Ɩ����s���Ă���ꍇ�́A1�����z�m�ɂȂ�O�̓��Y�Ɩ��������o���Ƃ��ĔF�߂��܂��B
�i�����z�ݔ��m�̎��i��L���Ă��Ȃ��ꍇ�A1�����z�m�Ƃ��Ă�5�N�ȏ�ݔ��v�̋Ɩ��ɏ]������K�v����j
���ƊE�ł̃L�����A�A�b�v��A����̋ƊE�������l���Ă����z�ݔ��m�́A�擾�����b�g�̍������i�Ƃ����܂��B
���w�@�ł́A����29�N�x ���z�ݔ��m��u���̎�u�\�����t���Ă���܂��B
���|�I���i�����ւ�P���E�Q�����z�m��u���Ɠ��l�ɁA�w�ȁE���}�Ƃ��Ɂu���S�v�̏�ԂŎ����ɗՂ߂�u���ƂȂ��Ă���܂��B
�����l���̊F�l�̃��C�t�X�^�C���ɂ��킹���w�K�X�^�C��������Ă����Ē����܂��̂ŁA����29�N�x���i��ڎw�������́A����A��u�����������������B
�������(�v���})�̎������͂̓R�`��
���x�� �����v���[���g�I
�wH28 ���z�ݔ��m �����(�v���}) �I���W�i���Q�l��
�q�O��U���Łr�i11�����{�ȍ~�����\��j�x
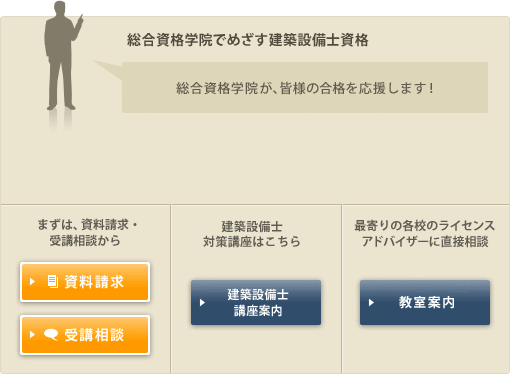
���z�ݔ��m�̎��i�擾�Ɋւ���^���s�����A�������i�w�@���������܂��B���w�@�̃��C�Z���X�A�h�o�C�U�[���A�L�x�Ȍo����w���m�E�n�E�Ɋ�Â��I�m�ɃA�h�o�C�X�������܂��̂ŁA���ЁA�������ƈꏏ�Ɍ��z�ݔ��m�̎��i�擾���߂����܂��傤�I