�ꋉ���z�m �������x��m�낤
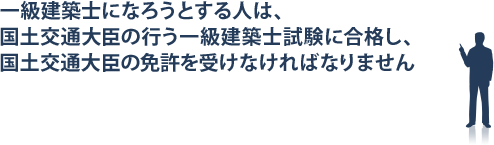
�ꋉ���z�m�����́A�u�w�Ȃ̎����v�Ɓu�v���}�̎����v�ɕ����čs���܂��B
�w�Ȃ̎����ɍ��i�����l�݂̂��v���}�̎������邱�Ƃ��ł��܂��B
���i
���z�m�@�̉����i�ߘa�Q�N�R���P���{�s�j�ɔ����A����ۂ̗v���ƂȂ��Ă��������̌o�����A�Ƌ��o�^�̗v���ɂȂ�܂����B
���\1. �ꋉ���z�m�����̎��i�i���z�m�@��14���j
| ���z�m�@
��14�� |
���z�Ɋւ���w�͎��i�� |
|---|---|
| ��ꍆ | ��w�A�������w�Z�i������w���܂ށj�ɂ����āA�w��Ȗڂ��C�߂đ��Ƃ����ҁi��1�j |
| ��� | ���z�m |
| ��O�� | ���y��ʑ�b����L�̎҂Ɠ����ȏ�̒m���y�ыZ�\��L����ƔF�߂�ҁi��2�j (�ߘa���N���y��ʏȍ�����752���ق�) |
- �i���j�u���y��ʑ�b����߂錚�z�m�@��14���O���ɊY������҂̊�v�Ɋ�Â��A���炩���ߊw�Z�E�ے�����\���̂������J�u�Ȗڂ��w��ȖڂɊY������ƔF�߂�ꂽ�w�Z�ȊO�̊w�Z�i�O���̑�w���j�𑲋Ƃ��āA������w���Ƃ���ꍇ�ɂ́A���z�m�@�ɂ����Ċw���ƔF�߂���w�Z�̑��Ǝ҂Ɠ����ȏ�ł��邱�Ƃ����邽�߂̏��ނ��K�v�ƂȂ�܂��B��o����Ȃ��Ƃ��́A�u���i�Ȃ��v�Ɣ��f�����ꍇ������܂��B
- ���P�j���E��w�̑O���ے����܂ށB
- ���Q�j���z�ݔ��m���܂ށB
- ���ڍׂ� (����)���z�Z�p���畁�y�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Ŋm�F���Ă��������B
�y���i�̊w��v���z
�Z�w�Z�̓��w�N������ 21 �N�x�ȍ~�̕��c
���y��ʑ�b�̎w�肷�錚�z�Ɋւ���Ȗځi�ȉ��A�u�w��Ȗځv�Ƃ����B�j���C�߂đ���
�Z�w�Z�̓��w�N������ 20 �N�x�ȑO�̕��c
����̉ے����C�߂đ���
�w��v���ɂ���
������21�N�x�ȍ~�̓��w�҂̏ꍇ
���� 21 �N�x�ȍ~�ɓ��w���Ă���҂��u�w��Ȗڂ��C�߂đ��Ɓv�����i�̏����ƂȂ�A�\2�Ɏ����w�Z���ʂɏC������w��Ȗڂ̒P�ʐ��ɉ����āA�Ƌ��o�^�̍ۂɏ���̎����o���N�����K�v�ƂȂ�܂��B�Ȃ��A�w��Ȗڂ̕��ނ��Ƃ̕K�v�P�ʐ��́A�\3�Ɏ����Ƃ���ł��B�܂��A�w�Z�E�ے�����\���̂������J�u�Ȗڂɂ��Ďw��ȖڂɊY�����邱�Ƃ��Z���^�[���m�F�����Ȗڂɂ��ẮA�i�����j���z�Z�p���畁�y�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�ɂ��m�F���ĉ������B
���\2. �w�Z���ʁA�K�v�Ȏw��Ȗڂ̒P�ʐ�
| �w�Z�� | �w��Ȗڂ̒P�ʐ��i���j | �������ɕK�v�ƂȂ�����N�� | �o�^���ɕK�v�ƂȂ�����N�� | |
|---|---|---|---|---|
| ��w�A�������w�Z�i�u�{�ȁ{��U�ȁv�̑��Ǝ҂Ɍ���B�j�A�E�Ɣ\�͊J��������w�Z�i�����ے��A�����ے����͉��p�ے��̑��Ǝ҂Ɍ���B�j�A�E�Ɣ\�͊J����w�Z�i���p�ے��̑��Ǝ҂Ɍ���B�j | 60 | 0�N | ���ƌ�2�N�ȏ� | |
| 50 | ���ƌ�3�N�ȏ� | |||
| 40 | ���ƌ�4�N�ȏ� | |||
| �Z����w�i�C�ƂR�N�ȏ�j���P�j | 50 | ���ƌ�3�N�ȏ� | ||
| 40 | ���ƌ�4�N�ȏ� | |||
| �Z����w�i�C�ƂQ�N�ȏ�j���Q�j�A�������w�Z�i�{�Ȃ݂̂̑��Ǝҁj�A�E�Ɣ\�͊J��������w�Z�i���ے��݂̂̑��Ǝҁj�A�E�Ɣ\�͊J����w�Z�i���ے��݂̂̑��Ǝҁj�A�E�Ɣ\�͊J���Z����w�Z | 40 | ���ƌ�4�N�ȏ� | ||
| ��C�w�Z | ���ے��ŏC��4�N�ȏ� | 40,50,60 | ���ƌ�2�`4�N�ȏ� | |
| ���ے��ŏC��3�N�ȏ� | 40,50 | ���ƌ�3�`4�N�ȏ� | ||
| ���ے��ŏC��2�N�ȏ� | 40 | ���ƌ�4�N�ȏ� | ||
�i���j�w��Ȗڂ̒P�ʐ��̏����́A�\3�Ɏ����B
���P�j���E��w�̂R�N�̑O���ے����܂ށB
���Q�j���E��w�̑O���ے����܂ށB�Ȃ��A���E��w�y�ѐ��E�Z����w�̑��Ǝ҂ɂ��ẮA�]���̑�w�y�ђZ����w�̑��Ǝ҂Ɠ��������ƂȂ�܂��B
���\3. �w��Ȗڂ̕��ނ��Ƃ̕K�v�P�ʐ���
|
�w�Z��
�w��Ȗڂ̕���
|
��w �� | �Z����w�i�C��3�N�ȏ�j�A��C�w�Z�i���ے��ŏC��3�N�ȏ�j �� | �Z����w�i�C��2�N�ȏ�j�A��C�w�Z�i���ے��ŏC��2�N�ȏ�j �� |
|---|---|---|---|
| (1)���z�v���} | 7 | 7 | 7 |
| (2)���z�v�� | 7 | 7 | 7 |
| (3)���z���H�w | 2 | 2 | 2 |
| (4)���z�ݔ� | 2 | 2 | 2 |
| (5)�\���͊w | 4 | 4 | 4 |
| (6)���z��ʍ\�� | 3 | 3 | 3 |
| (7)���z�ޗ� | 2 | 2 | 2 |
| (8)���z���Y | 2 | 2 | 2 |
| (9)���z�@�K | 1 | 1 | 1 |
| (1)�`(9)�̌v(a) | 30 | 30 | 30 |
| (10)���̑�(b) | �K�X | �K�X | �K�X |
| ���P�ʐ�(a)�{(b) | 60,
50, 40 |
50,
40 |
40 |
�i���j�w��Ȗڂ̕��ނ��Ƃɒ�߂�ꂽ�P�ʐ��y�ё��P�ʐ�(a)�{(b)�������Ƃ������ƂȂ�܂��B
������20�N�x�ȑO�̓��w�҂̏ꍇ
�u����20�N11��27���܂łɏ���̊w�Z�𑲋Ƃ��Ă���ҁv�y�сu����20�N11��27���܂łɏ���̊w�Z�ɍ݊w����҂ŕ���20�N11��28���Ȍ�ɓ��Y�w�Z�𑲋Ƃ����ҁv�ɂ��ẮA�������u����̉ے����C�߂đ��Ɓv�Ƃ����w��v���i�\4�j���K�p����܂��B
���\4. ����20�N�x�ȑO�̓��w�҂ɓK�p�����w��v��
| ���z�Ɋւ���w�͎��i | �������ɕK�v�ƂȂ�����N�� | �o�^���ɕK�v�ƂȂ�����N�� | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (��) | ��w�i������w���܂ށj | �ے� | ���z���͓y�� | 0�N | ���ƌ�2�N�ȏ� |
| (��) | 3�N���Z����w(��ԕ�������) | ���z���͓y�� | ���ƌ�3�N�ȏ� | ||
| (�O) | 2�N���Z����w | ���z���͓y�� | ���ƌ�4�N�ȏ� | ||
| �������w�Z(�������w�Z���܂�) | ���z���͓y�� | ���ƌ�4�N�ȏ� | |||
| (�l) | ���̑����y��ʑ�b�����ɔF�߂��(����20�N���y��ʏȍ�����745���ق�) | ����̔N���ȏ� | |||
- ���ڍׂ� (����)���z�Z�p���畁�y�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Ŋm�F���Ă��������B
������
�w�Ȃ̎����@�@�@ �E�E�E �ߘa5�N7��23���i���j
�v���}�̎��� �E�E�E �ߘa5�N10��8���i���j
�����̎���
- �w�Ȃ̎����E�E�E �ߘa5�N7��23���i���j
�w��II�i���E�ݔ��j20��@���H�w�A���z�ݔ��i�ݔ��@��̊T�v���܂ށB�j��
(1����45��)
(2����45��)
�w��V�i�{�H�j25��@���z�{�H��
- �v���}�̎����E�E�E�ߘa5�N10��8���i���j
�i6����30���j
- ���v���}�̉ۑ�́A �ߘa5�N7��21���i���j������(����)���z�Z�p���畁�y�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ���܂��B
���i�҂̔��\��
- �u�w�Ȃ̎����v�F�ߘa5�N8��30���i���j(�\��)
- �u�v���}�v�̎����F�ߘa5�N12��25���i���j(�\��)
�u�w�Ȃ̎����v�y�сu�v���}�̎����v�̎҂ɂ́A���ꂼ��A���y��ʑ�b�̍s�������ۂ̔��茋�ʂ��ʒm����A�s���i�҂ɂ͎����̐��т������Ēʒm����܂��B�������A���Ȏҁi�u�w�Ȃ̎����v�ɂ����Ă͈ꕔ�̉Ȗڌ��Ȏ҂��܂ށB�j�ւ͒ʒm����܂���B
�܂��A�u�w�Ȃ̎����v�ɂ����Ă͍��i�҂̎ԍ��ꗗ�\���A�u�v���}�̎����v�ɂ����Ă͍��i�҈ꗗ�\��(����)���z�Z�p���畁�y�Z���^�[�{���E�x���y�ѓs���{�����z�m��̎������Ɍf�������ƂƂ��ɁA(����)���z�Z�p���畁�y�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�ɂ��f�ڂ���܂��B
�������{�@��
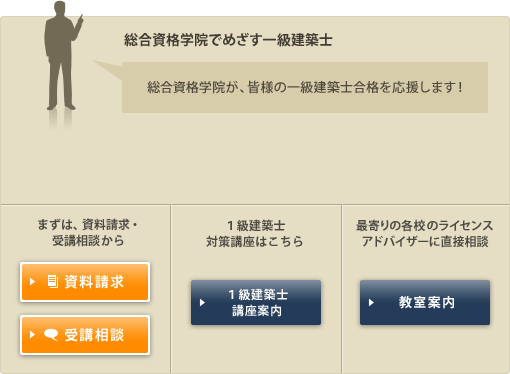
�ꋉ���z�m�Ɋւ���^���s�����A�������i�w�@���������܂��B���w�@�̃��C�Z���X�A�h�o�C�U�[���A�������̍��i����Ɋ�Â��I�m�ɃA�h�o�C�X�������܂��̂ŁA���ЁA�������ƈꏏ�Ɉꋉ���z�m���i���߂����܂��傤�I