- 令和3年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 伊木田 優衣さん
SPECIAL INTERVIEW
理解できないときこそ、いろんな建築物を見てよく知ることが大切
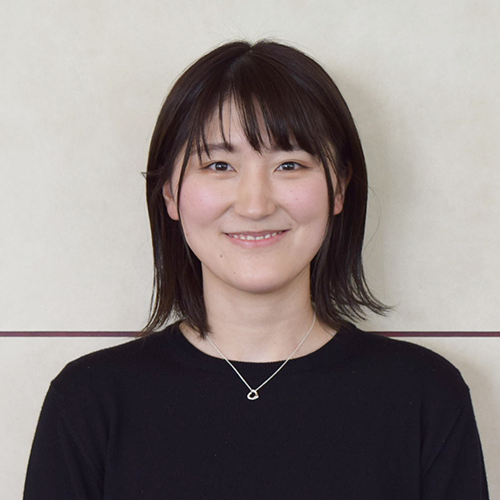
伊木田 優衣さん (23) 令和3年度 1級建築士合格
- 学歴:
- 高専
- 勤務先:
- プラント(意匠設計、積算・見積、工事監理)
- 教室:
- 熊本校
計画:13点 環境/設備:17点 法規:23点 構造:24点 施工:17点
受講講座
- 受験回数:
- 学科2回/設計製図1回
この仕事の道に進もうと思ったきっかけ
設計も積算も工事監理もやってみたい
高専入学時は、店舗のインテリアデザインや住宅の設計がしたいと思っていましたが、高専で建築を学んでいくうちに、RC造や鉄骨造の建築物に面白みを感じました。しかし就活時にやりたい仕事を決められず、設計・積算・工事監理などといった様々な業務を経験できるプラント会社に魅力を感じて就職しました。
1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
実務経験が少ないことが、なにより不安でした
いずれは1級建築士を取りたいと思っていましたが、上司が子育てしながら受験し、勉強時間がなかなか確保できない様子を見て、時間が取れる若いうちに資格を取得したいと思いました。会社の研修が落ち着いたころに総合資格に通い始め、社会人2年目の昨年初受験しました。実務経験が浅く、現場をあまり知らないことが不安でしたが、猛勉強すれば知識でどうにかなるということを2回目の受験で知りました。また、時期によって仕事量に波があるため、試験前は特に勉強時間を確保できるよう上司と相談して調整してもらいました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
すぐに質問できる環境と一緒に勉強する仲間が近くにいる環境が大事
総合資格は自宅から車で片道1時間、他の資格学校は職場と自宅の中間に校舎があり、他の資格学校のほうが通いやすいと思いましたが、各校を比較した際に、総合資格は直接講師から教わってすぐに質問できる環境があること、一緒に勉強する仲間が近くにいることが、分からないときや苦しいときに、より勉強する励みになると思い総合資格を選びました。
ご自身と独学者を比べてみて、一番大きな違い
多くの支えがあったから、やり抜けた
会社の上司が独学で試験に臨んでいましたが、スケジュール管理や勉強時間の確保の点で違いが大きいと感じました。独学と比べて、チューターやスタッフの方々にスケジュール管理してもらうことで、勉強に集中することができたと思います。また、毎週行う達成度テストや定着度テストで他の受講生との競争意識をもって勉強できることや、他の受講生の質問内容を聞いて自分では気付かなかった疑問点や不明点を知ることができることなど、学校に通うメリットはかなり大きかったと思います。
合格したからこそ言える失敗談や反省点、受験期間中の印象に残るエピソード
1級建築士試験は、チーム戦だと思いました
実務ではRC造やS造の設計がほとんどで、施工に関しては理解が不足していたため、学院で仲良くなった木造の現場で働く方に教えてもらったり、逆に得意な部分は教えたりしていました。製図試験では、講師や既受験の方に図面を速く描ける道具や見やすいエスキスの描き方を教えてもらったり、他の受講生とプランやエスキス、勉強方法について意見交換したりしました。この1年多くの人の力を借りながら、合格できたんだと思いました。
勉強時間のつくり方について、苦労した点・工夫した点
集中できる時間に何をするか計画する
終業後は地域の学習室で勉強していましたが、コロナで時短や一時閉館したことで、勉強場所が無くなったことが困りました。そのため、自宅で勉強できる環境を整えるのに試行錯誤しました。教材の持ち運びが大変なので、学科試験のときは昼休みに会社のPCでデジトレを行いました。製図試験のときは昼休みに講義資料の整理を行い、家でエスキスや作図を行うためのまとまった時間が確保できるように工夫しました。
当学院で学習した内容が、お仕事で活かせたエピソード
建築を理解することで、仕事の効率が上がった
今まで設備について漠然としか理解できていませんでしたが、学院で設備工事の基本を理解できたことで、基本設計の段階で設備計画も含めて自力で検討できるようになりました。それにより、実施設計に移行した際の配置変更や手戻りが大きく減り、業務がスムーズに進むようになったと感じます。
当学院指導の大きな特長である、講師によるライブ講義を受けて良かったこと
理解できるまで、熱心に教えてくれました
疑問に思ったことをすぐに講師に聞けて、効率的な勉強ができました。講義では受講生の理解度にあわせて講義を進めてくれたり、なかなか理解できない部分は理解できるまで熱心に教えてくれたりしたことが印象に残っています。
得意科目と苦手科目
得意科目
苦手科目
得意にできた理由、もしくは苦手科目の克服法
沢山の写真や映像を見て、苦手を克服しました
法令集は自分ルールで色分けし、何度も引けない条文にはインデックスを追加して自分だけの法令集を作り込みました。さらに、よく出る法令の内容を覚えたことで、見直しの時間を十分確保できるようになり高得点が取れるようになりました。施工は材料の特徴を覚えることが苦手でしたが、インターネットで現場の動画を見たり、各材料がどの建築に使用されているか調べたりすることで、材料や施工工程をイメージしながら解けるようになりました。
設計製図試験も見据え、学科学習時から正しく理解し、記述できるレベルまで実力を引き上げる指導から感じた効果
学科試験までのがんばりが製図試験で役に立った
学科試験から製図試験まで約2か月しかないため、作図やエスキス、プランニングの練習時間を取られ、記述の勉強時間がなかなか確保できませんでした。試験直前に記述の勉強を集中的に行った際、学科試験のときに構造や設備をしっかり理解できていたおかげで、短期間で記述を完成させることができました。学科試験のときのがんばりによって、不安なく製図試験を迎えることができたと感じています。
学科合格のポイント
学院を信じてやり抜いた通い始めたときは不安でしたが、学院を信じて宿題を欠かさず出し、模擬試験や毎週のテストで学院が掲げる目標点を達成できるよう、がむしゃらに勉強しました。成績が不調のときも学院を信じて勉強し続けたことが良かったと思います。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
法規の確認は段階ごとに確認する
最初は学院が教える順序通りにエスキスできず、法規の確認が抜けていたり、うまくプランが納まらなかったりしていました。講義や宿題をこなしていくごとに、課題文の読み取りや条件整理、見やすいエスキスの作り方が重要と感じました。また、他の受講生とグループ添削を行う際、プランで迷った点やエスキスの描き方などを意見交換することで、参考になることが多かったです。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
作図で手を止めないエスキスを作る
作図は得意な方でしたが、作図に移行する際の1/200エスキスの完成度によって、作図のスピードが大きく異なりました。そのため、作図で手を止めないエスキスを作ることを意識してエスキスの完成度を調整し、目標時間内にエスキスを完成させるよう心掛けていました。また、条件整理してもプラン変更に没頭してしまうと設計条件を忘れがちだったので、プラン検討時に確認しやすいよう描き方を工夫しました。
設計製図試験において、学科対策期間中からやっておいてよかった、あるいはやっておけばよかったこと
製図試験を意識して法規を学ぶ
高さ制限や採光、防火設備、歩行距離など製図試験で問われる法令をしっかりと覚えておけばよかったと感じました。製図の講義は学科で習った基礎知識があるのが大前提で講義が進むうえ、法令集の持ち込みができないため、曖昧に記憶していた法令でよく躓いていました。法規で一発不合格にならないよう、学科試験のうちから製図試験を意識して勉強することが大切だと感じました。
製図合格のポイント
他の受講生と意見交換グループ添削する際に、他の受講生とプランやエスキスを見せ合い、疑問に思ったことやエスキス中にどこで悩んだかなど、よく意見交換していました。また、勉強方法や悩みを他の受講生と話すことで、お互いに気持ちを共有することができ、きついときも最後までがんばることができたと思います。

-
アウトプット強化講座
1年目はアウトプット強化講座なしで講義の後、自習室で勉強していましたが、質問したいことがあってもアウトプット強化講座中は講師になかなか質問できず、躓いたらなかなか勉強が進みませんでした。その反省を生かして2年目はアウトプット強化講座を受講したことで、丸1日勉強する時間が確保され、すぐに講師に質問できる環境ができ、効率的な勉強ができました。
詳細はこちら -
デジトレ
以前は出張中や移動の際にも、教材や問題集を持ち運んで勉強していました。デジトレを使い始めてから、携帯やPCがあれば短時間でいつでも勉強できたので荷物も減り、とても重宝しました。また、模擬試験でよく間違える単元や正答率が低い問題を選択して出題範囲を絞り込んで解くことで、集中的に弱点を潰すことができました。
詳細はこちら -
グループ交換添削
講師や他の受講生に添削してもらうことで、自己採点では気づけなかったポイントを確認することができました。また、他の受講生の図面を添削する際には、採点者が見るポイントや、要求に対してどんな工夫をしているか知ることで、次回の作図の際に活かすことができたと思います。









