- 令和5年度祝賀会
- 2級建築士合格体験記一覧
- 加納 奈津花さん
SPECIAL INTERVIEW
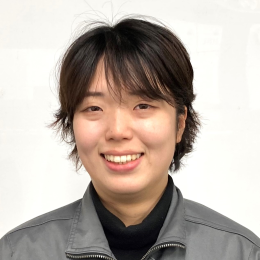
加納 奈津花さん (23) 令和5年度 2級建築士合格
- 学歴:
- 大学
- 勤務先:
- 建設会社(施工管理)
- 教室:
- 松江校
計画:19点 法規:20点 構造:19点 施工:16点
受講講座
- 受験回数:
- 学科1回/設計製図1回
現在の道に進もうと思ったきっかけ
日々変化し新しくなっていくものづくりが好き
小さいころから住宅広告のチラシを眺めたり、祖父と一緒に日曜大工をしたり、工作をしたりなど、ものづくりが好きでした。高校卒業後に、大学の建築学科に進学しました。そこで古民家リノベーションに携わる学生団体に所属し、リノベーションの現場が日々変化していくことの面白さを知り、卒業後も現場で工事に携わりたいと思い、建設会社の住宅工事部に就職しました。
卒業1年目で建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安なことやそれをどう克服したかお聞かせください。
逃してはいけないタイミング
仕事が忙しくなる前、勉強時間を比較的確保しやすい社会人1年目に受験したいと考えました。また、学費が高くついてしまうことが心配だったのですが、受講料が学割で安くなるということを、総合資格学院の説明会の際に教えていただき、この機会を利用するしかないと思い、卒業してすぐのタイミングで受験することを決めました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
一番身近な資格学校だったから
大学のすぐ目の前に学院の教室があり、説明会に行きやすかったり、何か気になることがあった際にすぐに相談させてもらえたりできたからです。
周り(会社の同期や身近の先輩社員)の2級建築士に対する学習状況
ほとんどの先輩が2級建築士の受験経験済み
先輩のなかには、過去に2級建築士の勉強をしていた方が多く、試験の話や学習時に苦労したことなどを教えていただき、とても参考になりました。1級建築士に合格された設計担当の先輩から製図道具を貸していただくこともでき、合格経験のある縁起のいい製図板で製図試験に臨めました。お守りのような存在で心強かったです。
学院で学習した内容が、実務で役立ったエピソード
就職後の現場や専門用語の理解に役立った
会社に入り、現場に出はじめて間もないころ、先輩社員や現場の職人さんの話している内容がほとんどわからず、わからないことすらわからないような状態でした。資格の勉強をしていくうちに、実務でも使う知識が身についていき、だんだんとわかることが増えていきました。勉強に出てきたものを仕事で実際に見たり、実例を見たりすることで、資格の勉強内容もイメージがしやすくなっていきました。仕事と学習と相互にいい影響が出たことはとても良かったです。
得意科目と苦手科目
得意科目
苦手科目
得意にできた理由、もしくは苦手科目の克服法
あきらめずに問題を解き続けてよかった
法令集に書かれている条文は普段使わないような日本語表現や、独特の言い回しがとても苦手でした。場合分けのような内容も理解しづらく、問題集を解いても間違えてばかりで自分のモチベーションがどんどん下がっていくのを感じました。でもこのまま法規ができずに不合格になったら、がんばっているほかの科目の勉強も無駄になってしまう、と思い、がんばって続けました。何度も法令集を開いているうちに、段々と条文の内容や問題のパターンがわかり、正解数が増えていきました。試験の結果は、苦手だったはずの法規がなぜかいちばん点が高く驚きましたが、あの時あきらめなくてよかったと心から思いました。
講義で一番役に立ったこと、助けになったことを教えてください。
重要なところをわかりやすく示してくれたこと
テキストの重要なところ、出題率が高くしっかりと理解しておくべきところを重点的に説明してもらえたので、手当たり次第に勉強する感じがなく、学習を続けやすかったです。
学科合格のポイント
問題集を解き続けること学院の問題集は過去の出題問題により構成されていて、出題傾向や問題の難易度なども明記されているため、効率よく勉強することができました。また、繰り返し問題に取り組むことで、問題文に対する慣れや答えのパターンも覚えていけるので問題に触れ続けていくことが重要だと思います。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
エスキスに対する苦手意識とトラウマの克服
大学の講義で住宅やオフィスビルなどの設計課題があったのですが、私はそのエスキスがとても苦手でした。いくら考えてもいいプランができず、迫ってくる提出期限に心身ともに追いつめられる……というのを毎回繰り返していたため、設計製図のエスキスにもはじめは苦手意識がありました。でも、エスキスの具体的なやり方を教えてもらいながら課題に取り組むうちに、コツがわかってきて苦手意識が消えていきました。最終的にはパズルのようにプランがカチッとうまくはまったときの感覚が好きになり、楽しんで取り組むことができました。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
作図の順番を覚えること
作図では効率よく描く順番を教えてもらい、それに従って描いていきましたが、はじめはその順番を覚えることに苦労しました。描き忘れて順番が入れ替わり、効率が悪くなったり、描いていないと減点されてしまうものを描かないまま先に進んでしまったりしていました。そういった失敗も練習のうちに自分で気づいたり、指摘してもらったりすることで、二度と同じことはしないと意識できるようになったので、だんだんと正しい順番で確実に描けるようになっていきました。
製図合格のポイント
毎日作図に触れること
短くても毎晩30分は作図をしていました。時間があるときは平面図と矩計図、疲れているときは文字トレや立面図だけ、など作図の教材を利用して手が描き方を忘れないように努めていました。疲れがたまってモチベーションが下がることもありましたが、学院に行って教務スタッフに励ましてもらったりすることで、継続して行うことができました。










