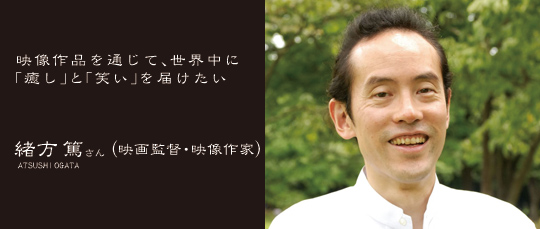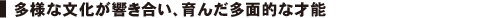
 2006年に製作され、今も世界中でたくさんの人を爆笑の渦に巻き込んでいる15分の短編映画があります。タイトルは「不老長寿」。新潟・十日町を舞台に、一人暮らしの老婆と“不老長寿の薬”を売りつけようとする詐欺師との騙し合いを描いたコメディです。
2006年に製作され、今も世界中でたくさんの人を爆笑の渦に巻き込んでいる15分の短編映画があります。タイトルは「不老長寿」。新潟・十日町を舞台に、一人暮らしの老婆と“不老長寿の薬”を売りつけようとする詐欺師との騙し合いを描いたコメディです。
監督の緒方篤さんは、日本・アメリカ・ヨーロッパでそれぞれ人生の3分の1ずつを過ごしてきた映像作家兼、映画監督。マサチューセッツ工科大学大学院で「アートとテクノロジーの融合」をテーマに研究し、ドイツ・ケルンのメディア・アート・アカデミーに才を見出されて客員作家となった後、映像作家として独立した奇才です。
「子どもの頃は自分が芸術家になるとは夢にも思っていませんでした。でも高校の時、父がくれたカメラで写真を撮るうちに興味が動画に移り、やがて映像の世界に進みたいと思うようになったんです」
客員作家時代はスペインからポーランドまでカメラ片手に回り、撮影・編集した作品を各地のビデオ・フェスティバルや美術館で上映。霧の立ち込める森など、魂を癒すような幻想的な映像が高い評価を経て、美術館やクラブなどからの委託制作、彫刻など異なるアートとのコラボレートの機会も広まっていきます。
しかし緒方さんの興味はさらに「映画」へ向かいました。ドイツ、オランダのテレビ局や映画基金から助成金を得て脚本家としても活動を始め、さらにはニューヨークで演技クラスを修了。オランダに戻ると、国営テレビのクイズ番組に俳優として出演するチャンスが待っていたのです。
「回答者に向かって日本語でわめく、いんちきスコア・キーパー役でした。2005年から3年間、金ピカスーツからスーパーマンまで、あらゆるコスチュームで出演して、オランダでは変な意味で知名度が上がりました(笑)」
映像作家・脚本家・俳優――型にはまらず活躍していた緒方さんを、映画監督としても一躍世界的にしたのが、新潟の「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」から委託を受けて制作した『不老長寿』でした。
「新潟・淡路大震災の時、ボランティアに交じって詐欺師まがいの人たちも被災地にやって来たと聞いて、アイデアが湧きました。また、したたかなおばあさんを描くことで高齢者に対する偏見や先入観を覆したかったんです」
絶妙なテンポで繰り広げられる老婆と詐欺師の心理戦は、数々の映画祭で上映され、スティーブン・スピルバーグらを輩出したニューヨーク近代美術館(MoMA)とリンカーン・センター共催のNew Directors/New Films映画祭2007に日本から唯一入選します。これを皮切りに、アメリカの7つの映画祭、バンコク国際映画祭 (タイ)やサンパウロ国際映画祭 (ブラジル)、ベルリン・ホット・ショッツ映画祭 (ドイツ) などで受賞が相次ぎました。
「普通、『笑い』は文化の影響を色濃く受けるので、コメディが他国で評価されるのは難しいんです。でもこの作品は、ニューヨークでもバンコクでも、はたまた秋田でも、観客が同じシーンで同じように笑ってくれました。特別意識したわけではありませんが、私自身が人生の3分の2を海外で過ごしてきたことと無縁ではないかも知れません」
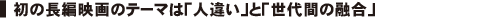
 拠点を日本に戻し、初の長編映画『脇役物語』の撮影を終えた緒方さん。世界各地での上映を通じて、プロデューサーや共同脚本家、スポンサーが続々と集まり、次回作のチームが編成されていった経緯を「人の縁の結晶」と語ります。
拠点を日本に戻し、初の長編映画『脇役物語』の撮影を終えた緒方さん。世界各地での上映を通じて、プロデューサーや共同脚本家、スポンサーが続々と集まり、次回作のチームが編成されていった経緯を「人の縁の結晶」と語ります。
キャストには益岡徹、永作博美、津川雅彦、松坂慶子など日本を代表する実力派俳優がズラリ。話題の作品になりそうです。注目のあらすじは……?「何かと人違いばかりされる万年脇役役者が、唯一自分を人違いしない女優の卵に恋をして、自分自身を見出していくロマンティック・コメディ」。そして前作と同じく、「高齢者を元気づけること」と「人違い」がテーマだそうです。
「ぼく自身、どの国に行ってもよく人違いされるんですよ。店に行けば従業員に間違えられ、自分が出品した映画祭に出席しても映画館スタッフと間違えられる。撮影現場でも配達の人だと誤解されました(笑)。そんな経験から生まれたのが『人違い』のアイデアです」
緒方さんは同時に、世代の断絶が叫ばれる世相の中で、70代、40代、20代の登場人物たちが心を通わせていく様を描くことで「世代を超えて楽しめる作品に」と願っています。
「殺伐とした世の中ですから、暗いものなんて描きたくない。映像を通じて、癒しや笑いを提供したいんです」
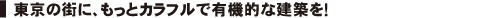
 一方、世界各地を住人として渡り歩いてきた緒方さんの目には、日本の建築はどのように映るのでしょうか?
一方、世界各地を住人として渡り歩いてきた緒方さんの目には、日本の建築はどのように映るのでしょうか?
「日本の家屋は、まず寒い(笑)! 断熱材や二重窓の使い方が甘いと思います。それに、空気を乾燥させてしまう暖房が多いのが残念です。ヨーロッパや北米では、ボイラーで温めた熱湯をパイプに流して室温を調整するセントラルヒーティングが一般的。これなら空気を汚さず、快適に過ごせます。またヨーロッパでは、室内に緑を植えて空気の循環を促したり、電車の駅で発生する熱をビルの空調に利用したりする『グリーン建築』が進んでいます。日本の気候・風土も利用しつつ、海外の良い部分は取り入れていけるといいですね」
また、独自の感性と色彩感覚で勝負するアーティストからは、東京の景観への厳しい意見が飛びました。
「東京はカチッとした直線や平面に囲まれていて、色もグレーが多く、殺風景。バロセロナにおけるガウディ作品のような、有機的な広がりのある建築がもっと生まれてもいいんじゃないでしょうか。またハード面だけでなく、パブリックアートなどソフト面を供給しつつ、幾何学的なものと有機的なものがうまく融合した空間が増えると、人の発想も豊かになると思います」
世界に認められた芸術家でありながら、周囲を笑わせずにはおかないユーモアとタレント性の持ち主である緒方さんが、その「東京」を舞台に撮った次回作『脇役物語』。私たちに次はどんな笑いを届けてくれるのか、楽しみに待ちましょう。

(取材・文/井田奈穂)