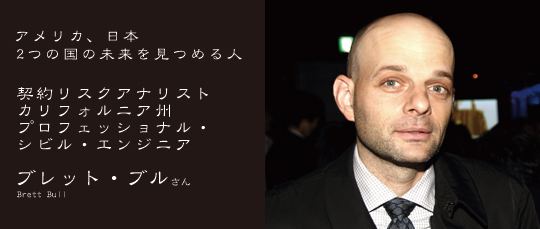アメリカで「医師」「弁護士」「公認会計士」と並ぶ4大公的ライセンスとして社会的に評価されている資格「プロフェッショナル・エンジニア(以下、PE)」。その資格を活かして活躍されていたブルさん。大学を卒業後に携わった代表的な仕事をあげてもらうと、サンディエゴにて公共貯水施設およびパイプラインの設計、カリフォルニア州湿地帯調査としてオックスナードとパームデールで地下水井戸の設置と監視調査、2000エーカー規模の公園の現地調査と注水パイプラインの再設計、1000戸相当規模の住宅地開発に関する建設費用見積…など幅広い。
そもそもPEとはどのような資格なのでしょうか?
「PEとはエンジニアリング業務を遂行するためのアメリカの公的資格です。1907年にワイオミングで『エンジニアは建築物に対する公共の安全・人命の尊重・社会の福祉に奉仕すべき』という理念の下に法制化され、全米へと広がりました。PEを保持していない技術者は、公共機関あるいは公共と私企業の顧客に提出す報告書、図面、見積書など技術文書にサインおよびシールをする事ができないため、アメリカの、特に公共の安全にかかわる業種や業務においてPE資格は不可欠といえます。PEを取得していないと業務ができない州や国もあることから、世界を舞台に活躍したい国際的エンジニアには必須の資格と言えるのではないでしょうか。なかでも、カリフォルニア州のPE試験には地震と土地測量の2つが追加で課せられるため、他の州に比べるとその試験は大変難しいとされています。」
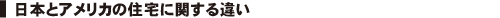
難関を突破してアメリカで、そして海を超えて世界でも大規模な土木建築などに関わってきたブルさん。日本に来てからは日本の住宅建築に興味を持ち始めたといいます。
「東京タワーのような有名なランドマークは知っていましたが、東京に来る以前は日本の建築物についてあまり知識がありませんでした。小さな頃に映画の中でゴジラが東京のビル群を破壊するのを見て面白かった…というイメージくらいでしたね(笑)」
実際に住んでみると住宅に関するアメリカと日本の価値観の違いに驚いたようです。
ロサンゼルスや他の大きな都市とその周辺部では多くの人が3LDKほどの一軒家に住んでいるため、「アメリカは全般的に居住スペースに恵まれている」と思われているようです。しかし、サンフランシスコやニューヨークの中心部のアパートメントの広さは日本のものとあまり変わらないのが現状です。居住スペースに関する悩みはアメリカも日本も同じと言えるのではないでしょうか。
「しかし、住宅に対する考え方の根本的な違いは感じます。アメリカでは住宅は将来への投資ですが日本ではそうではありません。アメリカでは住宅は100年以上使えるのが当たり前ですし不動産としての価値も上がります。日本では住宅の寿命は30年程度、通常は価値も上がりません。これらの違いに大きな驚きを感じました。」

 「外国人からは安藤忠雄さんの造った建物が人気です。しかし、私にとっては表参道ヒルズをはじめとする彼の建築にはあまり興味がなく、むしろ彼が神戸で作った狭小住宅に注目しています。」
「外国人からは安藤忠雄さんの造った建物が人気です。しかし、私にとっては表参道ヒルズをはじめとする彼の建築にはあまり興味がなく、むしろ彼が神戸で作った狭小住宅に注目しています。」
日本の住宅事情ゆえに誕生した「狭小住宅」が世界でも注目されはじめているといいます。アメリカのCBSニュースから取材を受けた経験もあるブルさん。PEとして最も興味を持ったのは日本の建築家たちの問題をクリエイティブに解決する力だそう。
「非常に狭い土地でいかにして居住スペースを確保するかというのが建築家にとっての問題ですが、それを解決するために非常にクリエイティブなアイデアを考え出していますね。狭小住宅のデザインには決まり事はほとんどありません。上から下まで流れる曲線の外観を持つものもありますし、壁と床の角度が90度以上になっているものも。また、屋根は平らである必要は無く、左右対称である必要もない。屋内の階段は螺旋階段になっていたり急傾斜になっていて下の階の天井の一部になっていたりします。それぞれのフロアーは広めの通路のようにならざるを得ないので手すりを備え付けるなど細部にわたりアイデアが感じられます。」
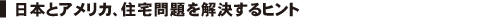
 また、ブルさんは「狭小住宅」という発想の中にアメリカにおける住宅問題を改善するヒントがあるといいます。
また、ブルさんは「狭小住宅」という発想の中にアメリカにおける住宅問題を改善するヒントがあるといいます。
「一般的にアメリカでも日本でも狭い家より大きな家が良いと考えられていますが、私はそうは考えていません。空間がどのように活用されているかが問題なのではないでしょうか。現在アメリカが抱えるサブプライムローンやそれに続くリーマンショックを引き起こした原因のひとつに、アメリカ人がより大きな家を追い続けてきたことがあげられます。日本における空間の有効利用のように住環境に対する考えを少しチェンジ出来れば、アメリカ人はもっと幸せになれるのだと思います。
また、日本におけるスクラップ・アンド・ビルドの考え方は無駄が多いと思います。
何世代にもわたって使われる質の高い建物は『歴史』を残しますし、なにより環境に優しいのではないでしょうか。
」
日本とアメリカはお互いに学びあえることがあるとはずと語るブルさん。今、自分たちを取り巻く環境に慣れ切ってしまった日本人に、そしてアメリカ人にとっても、独自の視点で彼が発信する言葉に耳を澄ます必要があるのかもしれません。
(取材・文/小林未佳)