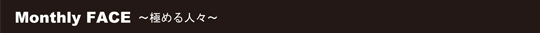ライターの道を開いたのは、雑用のアルバイトだった
「職業、ブックライター。毎月1冊10万字書く私の方法」など、数多くの著書を世に送り出し、ブックライターの第一人者として知られる上阪徹さん。そもそもブックライターとは、著者に取材を行い著者の代理で本を執筆する職業のことです。
現在は、雑誌の執筆や講演などの仕事もこなしながら1カ月に1冊の本を書き上げるという上阪さんですが、意外なことに「もともとは文章を書くのが大の苦手だった」と語ります。
「僕が就職した時は、糸井重里さんをはじめ、コピーライターが花形だった時代。アパレルメーカーに入社し、その後、広告に興味があってリクルートに転職しました。リクルート時代にメインで担当していた求人広告では、かっこいい言葉よりも、“内容を深く理解した上で読者にしっかり伝わる言葉”が求められた。最初はすごく苦戦して、300字を書くのに丸1日かかっていたほどです」
コピーライターとして「これ以上できない」というところまで努力を重ねるも、思うような結果が得られず、さらなる転職をした上阪さんですが、たった3カ月で転職先の企業が倒産。路頭に迷い追い詰められた末に、やむなくフリーランスの道を歩むことになります。28歳の時でした。

「地位も財産もすべて失って、何もないところからのスタートでした。失業時代、一番つらかったのは、誰にも必要とされていないこと。だから、どんなに小さい仕事でも声を掛けてもらえることが嬉しくて、必死にやりました。会社員時代は、うまくいかないことは上司とか会社とか“誰か”のせいにできたけれど、フリーになったらすべて“自分”の責任。それがむしろ、すがすがしくて、自分の性分に合っていたのかもしれません」
ひとつの転機となったのは、失業中に紹介されてやっていたリクルートの編集部門でのアルバイトでした。後に累計40万部のベストセラーとなったインタビュー集「プロ論。」(徳間書店)も、この時のパイプから生まれたものです。
「時給850円のアルバイトは誰でもできる雑用ばかり。でも、真面目に取り組んでいたら、その姿勢を見てくれていた編集者さんから『記事を書いてみる?』と声を掛けていただきました。一つ仕事をこなすと、また次の仕事が入る。そんなサイクルが自然と生まれ、気がついたら仕事がいろんな会社にも広がって、やがて書籍の仕事の依頼が舞い込んでいた。営業は一切せず、すべて人の紹介でいただいた仕事です」
「正しいゴール設定」と「心地よさ」から、いい仕事が生まれる
文章を書く職業は、記者、コピーライター、作家、コラムニストなど、多岐にわたりますが、上阪さんはそれらを「経済人」と「文化人」に切り分けて考えているといいます。
「クライアントからの依頼に応えるコピーライターやライター等は『経済人』、自身の感性を発揮する作家やコラムニスト等は『文化人』の仕事だと思います。私の仕事は経済人に当たるので、仕事の目的を明確にした上で、それを達成することに重きを置いています。それは、本でも雑誌でもWEBでも変わりません」
ゴール設定を正しく行うことに加え、上阪さんがもう一つ注力しているのが、関わる人たちにとって心地よいスタンスを貫くこと。
「仕事をご一緒する方々との細かい確認や、擦り合わせも怠りません。皆が心地よくゴールに向かっているかどうかが、仕事の良しあしを左右するからです」
文章を書く上では、「相場観の把握」や「うまく書こうとしないこと」も大事にしているという上阪さん。

「文章はただ書いてもダメ。誰に対しての何のための文章なのかを、いかに設計して届けるかが重要です。そのため、取材前にペルソナを細かく設定し、ペルソナが持つ相場観を把握するよう努めています。世間や会社など、文章を読む相手が、どのくらいの相場観を持っているかを知らなければ、彼らに届く文章が書けないからです。
執筆する際は、ペルソナが目の前にいると思って語りかけるように書いています。うまく書こうとすると文章が硬くなってしまうので、しゃべるときと同じぐらい自然体で書く。うまい文章より読者に伝わる文章を一番に意識しています」
固定概念を作らない。天井を決めた瞬間に可能性は尻すぼみする
上阪さんいわく、優れたライターは、得てしてビジネスパーソンとしても優れているのだとか。スキルはもちろんのこと、マインドも“熟して”いる。上阪さん自身もフリーランスになってからの24年間、一度も締め切りを破ったことがないそうです。
一つ一つの依頼に全身全霊で取り組み、クライアントの期待を決して裏切らない。そんな真摯(しんし)な姿勢が上阪さんのライター人生を形作ってきたに違いありません。「縁を紡ぐためにしていることは?」と問うと、「ひたすら目の前の仕事を一生懸命やるだけ」というシンプルな答えが返ってきました。
「私は任された仕事に対して、全力を注いでいるだけなんです。今この瞬間が一番大事。だから10年後にどうなりたいとか、そういった目標もありません。だって、明日のことさえ誰も分からないんですから。それより、目の前にあることを一生懸命やった方がいい。それが私の答えです」
最後に、上阪さんのような“売れっ子ライター”を目指す人に向けたアドバイスをいただきました。
「ビジョンを描いた瞬間、むしろ自分の未来に天井ができてしまうと私は思っています。私自身、24年前にフリーランスになった時、今こんなふうになっているなんて夢にも思わなかった。想像をはるかに越えた未来がやってきたのは、固定概念を持たなかったから。結局、人生を作るのは運と縁。世の中に対する飽くなき好奇心を持って、突き進んでください」
「今この瞬間に全力をかける」、それはどんな匠にも共通する「仕事観」と言えるかもしれません。


取材・文:小林香織
撮影:花村直親