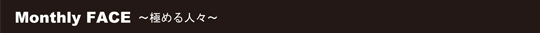福田監督が感じた、HKT48指原さんの“変化”
ドラマ「勇者ヨシヒコ」シリーズ、映画『HK/変態仮面』のほかにも数々の“笑える”作品を手掛けてきた、日本を代表する喜劇作家の一人・福田雄一さんの最新監督作『薔薇色のブー子』が、5月30日から公開されます。主演は、AKB48選抜総選挙(2013年度)で第1位に輝いたHKT48の指原莉乃さん。福田さんは、指原さんの連続ドラマ&映画初主演作となった『ミューズの鏡』のほかにも複数の作品で指原さんを起用。自身が構成・演出を務めるバラエティ番組「指原の乱」でもタッグを組んでおり、指原さんのさまざまな魅力を引き出してきました。そんな福田監督は、今作の撮影で指原さんの“変化”を感じたといいます。
「これまでは休憩時間になると端っこのほうに行って、一人で体育座りしながらスマートフォンをいじっているようなイメージだったんですけど、今回はほかのキャストさんやスタッフに積極的に喋りかけていました。クランクインして2日目くらいに『映画はたくさんの人が動くけど、その人たちは全員さっしーが良く見えるために頑張ってるんだよ』っていう話をしたんですけど、めずらしく真面目に話を聞いて(笑)、『わかりました』って。
出会って最初の頃は『映画はセリフを憶えないといけないし、つらいばっかでやだ』って言ってたんですけど、今回はそれが変わりましたね。スタッフはいい人だし、キャストもみんな面白い人たちで楽しい、って。でも、それは彼女が積極的にみんなに接することで感じられたものだと思うんですよね。だって、(ほかの作品でも)ずっと同じ撮影チームでやってるんですもん。もともと知ってるはずなんですよ、彼らを。当然、主演女優に話し掛けられたらみんな嬉しいから、現場はすごい楽しそうな雰囲気になっていました。だから、彼女自身も楽しかったんだと思います」
『薔薇色のブー子』は思い切った挑戦作

(C) 2014「薔薇色のブー子」製作委員会
『薔薇色のブー子』は、そんな撮影現場の楽しい雰囲気が伝わってくるようなコメディ作品。主演の指原さんをはじめ、ユースケ・サンタマリアさん、ムロツヨシさん、田口トモロヲさん、片桐はいりさん、佐藤二朗さんなど豪華キャストが勢揃いしています。
「不安だったんですよ。僕にとっては、久しぶりのストレートなお笑い映画だったので。かなり思い切った挑戦でした。というのも、最近は“カッコイイ感じで、とんでもなくくだらないことを言う”っていう作風で、ずっとやってきたんです。それって、作品を観た人が『かっこつけて何言ってんだよ!』とつっこむことで笑いが生まれるんですけど、今回は久しぶりに、その“ワンクッション”をなくしているんです。ストレートに笑いどころを見せるからには、ちゃんと笑えないとまずい。そうなると、やっぱり、自分の知っている方々の力が必要だなと。
みんな、僕がこれまでに仕事してきた人でもあるんですけど、『指原だったら面白い』と集まってくれました。マギーには、『これで映画の仕事を辞めるのかっていうぐらい、いままでのファミリーが勢揃いしてるよね』って言われたぐらい(笑)」
いまの自分は“ボケ”の前の“フリ”の段階
福田さんは、ドラマや映画の監督・脚本のほかにも、バラエティ番組の構成作家、舞台の劇作家・演出家として、さまざまなメディアで活躍。周りの人によく「手広いね」と言われるそうですが、「やっていることは一緒」と話します。
「メディアが違うだけで、“笑い”以外のことはしたことがないんです。たとえば、僕が情報系の番組とか、恋愛ドラマをやったりしたら手広いって言っていいと思うんですけど、“笑ってもらう”っていうことを起点にしたものしかやってないんで。そこ以外のものに手をつけたことは一回もないですし、たぶん、これからもないです」
そう話す一方で、胸に秘めている思いがあるといいます。
「僕が子供の頃から“創作の師”と仰いでいる、ザッカー兄弟とジム・エイブラハムズという人たちがいて、彼らは『裸の銃を持つ男』『フライング・ハイ』とか、くだらない映画ばっかりつくってきたのに、急に『ゴースト/ニューヨークの幻』(という恋愛映画)をつくったんです。…あれ、絶対に彼らの“ボケ”だと思ってるんですよ。『そんな映画つくるやつらじゃねーだろ!』と言われたくてやっているとしか思えないんですよ、僕には(笑)。でも、あれはいいボケだなと思うんですよね。いつしか自分もやっときたい、と思うんです。だから、いまは“フリ”の段階ですね。『あいつはくだらない映画しかつくらない』っていうことを世間のみなさんに知っていただいてから、『ゴースト』をやりたいですね」
舞台・ドラマ・映画・バラエティ番組――さまざまなメディアで、私たちに“笑い”を提供している福田さんが、“笑い”に重点を置いている理由を尋ねました。

「単純に、人に喜んでもらう手段として、笑い以外のことを知らないんだと思うんですよね。子供の頃から染み付いたものなんです。というのも、家庭がそうだった。小学生の頃から、クレイジーキャッツの映画を見させられるような家でしたから。あと、父は地方の新聞記者だったんですけど、家にお客さんが来ると、まあ親父がその人を喜ばせるんですよ。とにかく人を笑わせるのが得意で。そういう姿を見てきたから、それが一番のコミュニケーションツールだと思ってるんじゃないですかね、いまも。やっぱり、笑ってもらうのが一番だと。そこはたぶん、信じて疑わないんだと思います」