- 令和5年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 原田 康平さん
SPECIAL INTERVIEW
学科も製図も復習を徹底することが大事
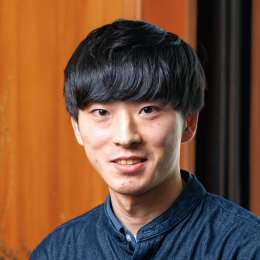
原田 康平さん (24) 令和5年度 1級建築士合格
- 学歴:
- 大学
- 所属:
- 大学院2年生(工学研究科)
- 教室:
- 名古屋校
計画:17点 環境/設備:18点 法規:28点 構造:28点 施工:19点
受講講座
- 受験回数:
- 学科1回/設計製図1回
現在の道に進もうと思ったきっかけ
昔からモノづくりをして遊ぶことが好きだった
小さいころ、ブロックなどモノづくり遊びが好きで、よく放課後に友達と一緒につくって遊んでいました。高校に入ってからも、何かとつくることに参加していると、その自分でつくったモノの役割が色々なことを担うようになって、「つくるって楽しい」と思ったのが、今の道に進んだきっかけです。
在学中で1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
大学院入試と1級建築士学科試験の出題範囲が重なっていた
学部生のころから、大学院に進学して修士号を取ること、1級建築士の免許を取ることを目標設定していました。学部2年生のときに、大学院入試の出題傾向をみた際に、その出題内容が、講義で習っていた内容と1級建築士学科の過去問とで構成されていることに気づき、同時に勉強した方が効率的だと思ったので、在学中の受験を決断しました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
復習カリキュラムが徹底されていた
記憶のメカニズムに合わせた復習カリキュラムが徹底されていた。学院は、予習、当日学習に加え、復習テストや模擬試験、各種テストが用意されており、それぞれ、翌日、1週間後、1カ月後、3カ月後に、精選された問題を適切なタイミングで復習できるようになっています。そのカリキュラムにとても共感を持てたので、学院で学ぶことに決めました。
同級生の1級建築士に対する学習状況
大学院に進学するまで周りで学習している同級生はいなかった
学習を開始した学部2年生のころ、周りで本格的に資格勉強をしている同級生はいませんでした。そのため、学習意欲が下がったときは、資格勉強をしている人が周りにいる、学院の自習室や図書館の自習室に行くことで、維持するように心がけていました。
当学院で学習した内容が、学校生活で活かせたエピソード
専門以外の分野の記事、論文が読みやすくなった
1級建築士の試験勉強では、計画、環境・設備、法規、構造、施工の基礎的な知識を、学部の講義より実務的で、幅広く体系的に学べるので、自分の専門以外の分野の記事、論文、講演会が読み聞きしやすくなりました。
当学院指導の大きな特長である、講師によるライブ講義を受けて良かったこと
教材だけでは学べない「センス」を養うことができる
初受験で何の経験もない自分にとって、何十年も資格試験に精通している講師陣の下で学べる環境は大きな支えでした。出題確率、 頻度に合わせた学習時間、労力の配分や、出題者の意図、問題のクセに合わせた頭の働かせ方など、教材だけでは学べない合格に必要な「センス」を講師の言葉を通じて養うことができたのが、ライブ講義を受けて最も良かった点だと思います。
得意科目と苦手科目
得意科目
苦手科目
得意にできた理由、もしくは苦手科目の克服法
復習時は法令集のつくり込みに徹する
法規をなかなか時間内に終わらせることができなかった時期に、講師から「法規はインデックス、 マーカー、 書き込みで法令集をつくり込むことが大事!」とアドバイスをくれました。それから復習はなるべく法令集のつくり込みに時間を割き、ライブ講義で教わったノウハウをもとに法令集つくり込みに努め、本番では1時間近くの見直し時間を確保でき高得点に繋がりました。
講義で一番役に立ったこと、助けになったこと
問題を解きながら講師の説明を受けられる講義システム
講義というとどうしても受動的になりがちですが、学院の講義では、プレテストと演習テストを用いて、自分で手を動かし、頭を働かせながら学べる主体的なシステムになっています。そのおかげで演習量にも不安を抱くことなく試験を迎えることができ、問題への対応力も発揮できたと感じています。
学科合格のポイント
間違えた問題の反復回数を増やす!間違えた問題に対して、学院の復習サイクルとは別に、少なくとも4回のタイミングで復習する学習方法を確立していました。私の場合は、A7のノートに日付インデックスをつけてポケットに入れて常に持ち歩き、間違えたらその内容と周辺知識をメモし、いつでも前日、1週間前、1カ月前、3カ月前に間違えたことを復習できるようにしていました。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
1/1000断面構成図のアレンジ
ライブ講義中に講師が「最終チェックで50分以上確保した人は80%以上の確率で合格している。」とアドバイスしてくれました。それを聞いて60分の最終チェック時間が欲しいと思った私は、読み取り、エスキス、中間チェックに割く時間を縮めるため、復習の解き直しを通してプロセス改善に努めました。1/1000の断面検討で階振分けを仮確定するように改善しました。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
作図手順、最終チェックのタイミング、内容の見直し
描き漏れ、読み違いを克服するためにやるべきことは、復習で自分のミス傾向に合わせて作図手順、最終チェックのタイミング、内容を改善することだと思います。私の場合は、断面作図前に法令9項目を先に描き終え、チェックもそこで済ませるようにしました。情報量が少ない段階で最終チェックをすることで描き漏れミスの発見率を向上でき、図面完成後に2巡目の最終チェックをすることができるようになりました。
製図合格のポイント
課題を解きっ放しにせず、復習!同じ課題を何回も解く!
学院の課題は、その年のビルディングタイプの実践演習を通して、過去に試験で問われた内容を出題確率、頻度に合わせて学べる精選された教材です。過去に解いた課題で学んだことや改善した点を思い出せないものは解きっ放しになっている証拠です。周りの受験生や、ほかの予備校の教材に惑わされず、繰り返し学院の課題を反復学習することが合格への一番の近道だと思います。

-
合格サイクル+継続学習
知識が大部分を占める試験で勝つために大事なことは、出題確率、 頻度に合わせて精選された問題を、適切なタイミング、回数で繰り返し復習することだと思います。精選された問題を適切なタイミングで復習できる学院のシステムがあったことで、学習計画を立てることに時間を割くことなく、演習に集中することができました。
詳細はこちら -
教務スタッフ、ライセンスアドバイザー
習ったことを習得できているか確認するために、問題を解く時は、問題用紙に周辺知識も含めて一通り書き出すようにしていました。繰り返し復習するために問題用紙をコピーしたいと相談すると、学院スタッフは、いつでも、 何回でも、快く応じてくれました。学院スタッフの手厚いサポートがあったからこそ、理想的な復習サイクルを維持できました。
詳細はこちら -
講師による添削
一度解いた問題も再度解き直し、復習をしていたので、講師には100枚近い図面を添削してもらいました。作図手順も曖昧で未完成図面を提出していた時期、最終チェックの時間が確保できず法令の不適合が多かった時期、読み取りミスが多かった時期、カリキュラム終盤の細かい間違いを直していく時期、常に習熟度に合わせて的確に指導してくれました。
詳細はこちら










