- 令和6年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 岩間 千帆美さん
SPECIAL INTERVIEW
最後まで諦めない!
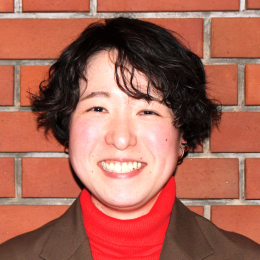
現在の仕事の道に進もうと思ったきっかけ
TV番組を観て
建築の道に進もうと思ったきっかけは、『劇的ビフォーアフター』を見ることが好きだったからです。お客さんの声をカタチにする匠(建築士)の方に面白さと憧れを持ち、建築学科の大学に進みました。大学3年次に、想像していなかった構造設計の道に興味をもち、将来は設計の道だと心に決めました。小学生のときに岩手県釜石市で震災を経験したことや、早いうちに地元を離れて生活したことから、岩手・東北に貢献したい思いが強くなり、岩手の設計事務所に就職しました。
1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
活躍するには必要不可欠な資格
設計事務所に就職することが決まってから、自分の幅を広げて活躍するには1級建築士は必要不可欠な資格だと思いました。新卒1年目で2級建築士、次の年に1級建築士を取得することを目標にし、社会人になると同時に1級建築士の講座まで一気に申し込みました。慣れない社会人生活のなかでの両立は大変でしたが、上司にも応援していただき、仕事を配慮してもらい、学習時間が絶対確保できる環境で取り組めました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
通いやすさと手厚いサポート
2級建築士の学科試験までは他の学校に通っていましたが、大学の同期が総合資格学院に通っていて手厚いサポートを受けていたことや通いやすさやを考慮して、2級製図試験対策から学院にお世話になりました。講師に直接質問しやすい環境や、他の受講生とコミュニケーションを取りやすい環境が一番良かったと思います。教務スタッフやライセンスアドバイザーの方も親身に話を聞いてくれて、自分にとって一番良い選択をすることができたと思います。
他講習と比較して、実際学院で学んでみていかがだったでしょうか
ライブ講義が良かった
映像も使いながらライブ講義を基本とする学院カリキュラムが自分に合っていたと思います。直接講師の声が聞けるので、納得のいくまで質問もできました。課題も他の学校より多かったかもしれませんが、かなり身になりました。
ご自身と独学者を比べてみて、一番大きな違いは何でしたか
環境と心構え
独学の方よりも「今年で絶対に取りきる」という覚悟が違っていたように思います。仕事以外の時間の使い方にもかなり差がありました。また、1人ではなく、同じ志をもった受講生の友達と勉強していくことが相乗効果に繋がり、モチベーションを保つことができました。
合格したからこそ言える失敗談や反省点、受験期間中の印象に残ったエピソード
自分を責めすぎず周りに相談する
学科、製図共に、うまくいかずに前に進んでいるように感じられない時期がありました。あきらめたくなる気持ちもありましたが、「自分ができないからこんなことに…」と自分を責めるのはむしろ逆効果かなと思います。周りの受講生に思いを伝えてみると、割とみんな同じ気持ちのことが多いです。「私だけじゃない!!」と思うだけで、元気になりました。
勉強時間のつくり方について、苦労した点・工夫した点
上司に受験することを伝える、学院に行く
一日の大半を仕事が占めるので、まずは会社の上司等に受験することを伝えました。試験が近づいたときは、仕事の調整をお願いしていました。また、1人だとだらけてしまったりするので、仕事終わりや休日は学院に行って学習時間を確保していました。それでもやる気が出ないことがありましたが、他の受講生と自習室で一緒に勉強する楽しみができるようになって、よりはかどったと思います。
当学院で学習した内容が、お仕事で活かせたエピソード
構造や様々な予備知識が身についた
組織設計事務所に勤務していることから、自分が所属している構造の仕事だけでなく、意匠や設備がらみの話や、また設計だけではなく監理での現場の話も飛び交います。最初は何を言っているのかさっぱりわからないなあと思うことが多かったのですが、こういうことだったのかと後からでも理解ができる予備知識がついたかなと思います。
当学院指導の大きな特長である、講師によるライブ講義を受けて良かったこと
不明点の即解決と良い緊張感
講義を受けていてわからないと思ったときに、即聞いて解決できたのがライブ講義でよかったと思う点です。また、高校や大学のように、同じ受講生が集まって、直接講師が講義を行うことで、良い緊張感もありました。集中するので、頭にも入りやすかったかなと思います。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
知識だけでなく、建築士としての感覚も問われた
3回受験した中で全てに共通して言えることですが、設計製図はただ知識をたくさん詰め込んでいればできるようになるものではなく、「建築士としての感覚」が問われるなと感じました。学科と違って、「必ず」が通用しないのが本当に苦労しました。必要な部屋がただ入っていればいいわけでもなく、「こうしたら利用者はこう思うな」という予測ができることや、臨機応変に対応できる力が大切になります。構造の仕事をメインでしているため、意匠設計をしている方々よりも感覚としてプランの良し悪しを考えることが苦手だと感じました。克服法は、実際に課題の建築物を見に行くことです。令和5年度の「図書館」、令和6年度の「大学」は受講生の友達と実際に建物の見学に行きました。実際にみると「確かに!」と思うことが多く、理解がとても深まりました。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
克服方法はシャープペンの芯
とにかく時間を速くすることを一番に、初期段階では作図練習をしていましたが、どうしてもスピード重視で雑になってしまうため、毎回の添削には「丁寧に描きましょう」と記載がありました。時間をかけてみたり、描き方を変えてみたり、試行錯誤した結果「シャープペンの芯を自分と相性が良いものに変える」ことで克服しました。関係ないだろうと思っていましたが、変えてみると全く見た目が違い、終盤には「本当に見やすくてきれいになった!なにを変えたの?」と講師の方々に言っていただけました。
製図合格のポイント
諦めない気持ちと向上心製図には合格するまで3回かかってしまいました。1年目は期間も短く、内容を理解しないまま試験を受けたのもありますが、2年目は内容も理解できるようになり、スピードも上がって上達したことによる気持ちの余裕が仇となってしまいました。「これなら受かるだろう」という自信が、気持ちに隙を作ってしまったように思います。悔しい気持ちを経験した3年目は、絶対はないということを胸に、できることはすべてしました。合格者に話をきいて、良いと思ったことは実践する。「こんなことまで?!」というものにも疑問を感じたら質問をする。そしてサプライズ対策として法規は絶対に落とさないことと、基本を忠実に復習しました。試験当日は中間チェックのしすぎで時間が無く、ぎりぎりまで作図し、補足も最低限しか記入できませんでしたが「絶対にあきらめない」という気持ちが合格できたポイントかなと思います。







