- 令和6年度祝賀会
- 1級建築士合格体験記一覧
- 渡辺 尚樹さん
SPECIAL INTERVIEW
最後に「やり切った」と言えるように!
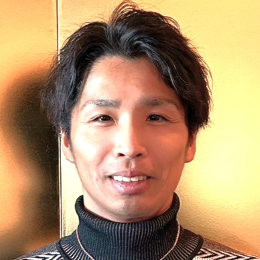
現在の仕事の道に進もうと思ったきっかけ
スキルアップのために
資格をめざすまでは、木造プレカットを仕事としていました。より深い建築の知識を得たいと思い、資格取得をめざすのとほぼ同時期に、構造設計の部署に異動しました。
1級建築士試験の受験を決断した理由・きっかけ、また受験を決める際に不安だったこととその克服法
仕事の幅を増やしたい、必要と思われる人材へ
将来への不安やコロナなどの世情もあり、国家資格である1級建築士をめざすことにしました。1級建築士を取得することで仕事の幅が広がり、必要と思われる人材へステップアップできると考えました。不安だったことは「自分がやり切ったと思えるだけの時間を確保できるか」です。会社や家族に公言することで、時間を確保できました。
独学または、他の学校利用ではなく「総合資格学院」に決めた理由
合格率の高さ
「他の資格学校より合格率が高い!」。それが自分にとっては最優先事項でした。また、時間確保のため、自宅から通いやすかった事も大きな理由です。
他講習と比較して、実際学院で学んでみていかがだったでしょうか
対面講義と練られた副教材
わからないことをその日の内に、講師に確認できたことは非常に良かったと思います。また、教室の雰囲気などを見ながら、説明の仕方をかえたり、図やイラストを描きながら説明してくれたのも、対面講義ならではの良さだと思います。毎講義用にテキスト以外の予習資料が配られ、予習の方法を迷うことなく効率よく行うことができました。
合格したからこそ言える失敗談や反省点、受験期間中の印象に残ったエピソード
仲間との会話も大切
特に製図試験対策では仲間と話す機会が増えます。試験予想などの話でついつい長くしゃべってしまったり、予想し合った話の残像が次の課題に残ってしまい、素直に課題に向き合えなかったりしたこともありました。「建築士試験だから、学部は建築学部かも?」と話したことが、本試験で出てビックリしました。
勉強時間のつくり方について、苦労した点・工夫した点
学習の習慣化
スケジュールを立て、いち早く学習を習慣化させました。仕事の都合などで予定がズレたときは、始業前の早朝や、昼休みなどの時間を使ってカバーしました。計算問題の公式などは自宅の壁に貼って、いつでも簡単に確認できるように工夫していました。スケジュールは日曜日の講義後すぐに立て、日曜の夜から実践しました。少し厳しいぐらいのスケジュールを立てて、絶対やり切るつもりで自分を追い込みました。
当学院で学習した内容が、お仕事で活かせたエピソード
建築に関する視野が広がった
職場は構造設計ですが、省エネ計算や、施工に関することなど、求められる意見は多岐にわたってきてます。建築士の学習は幅広く学ぶので、以前より社内や取引先と会話ができたり、曖昧だったことが整理できるようになったと思います。
当学院指導の大きな特長である、講師によるライブ講義を受けて良かったこと
わかるまで指導してくれる
わかるまで時間をとって指導していただいたり、教え方を工夫していただきました。話し方にもメリハリがあり、講義中は集中して学習ができました。講師とは、学科から製図までの間、質問したり、悩みを相談したりと学習の支えになっていただきました。
前期講座(実力養成講座)で、エスキス・作図・チェックなど、課題発表前に十分なトレーニングを行っていただきましたが、そのなかで成長したと実感されたことを教えてください。
6.5時間で終わらせるための時間管理
初受験時は6.5時間で終わるかどうか一か八かみたいな状況でした。2年目の長期製図に通うようになってから、多くの課題をくりかえし実践することで、6.5時間で終わらせるための時間管理能力がUPしました。そのおかげで、「途中の修正が間に合いそうなのか」「最終チェックの時間は確保できそうなのか」を常に考えながら取り組めるようになりました。
エスキスや記述(プランニング)で苦労した点や克服法、講義で役に立ったこと
廊下を通す、課題文の読み取りが重要
エスキスの特に1/400が苦手で、どの部屋からプランニングしたらよいのかわからず、時間だけが過ぎていくことが多かったです。廊下を極力シンプルに通す意識で取り組むようになってから、コツがつかめた気がします。記述自体に苦手意識はなかったのですが、課題文や作図との不整合に後から気が付くことがないように、条件整理の段階からメモを残すようにしていました。
作図で苦労した点や克服方法、講義で役立ったこと
作図中に考えない、手を止めない
作図の手順を全く知らなかったので、最初は何時間もかかりました。とにかく描いて手順を体に叩き込みました。作図中は手が止まってしまわないように、1/400のエスキスを適当にしないこともポイントだと思います。
製図合格のポイント
毎課題を丁寧に考えること講義後に解答例を見て一喜一憂しがちですが、「解答例がなぜそうなっているのか」「他の人と自分は何が違うのか」「その原因は何か、違うパターンだとどうなるのか」をできるだけ丁寧に考えることだと思います。一人では解決しないときは講師の方や、仲間に頼って積極的に意見交換できると尚良いと思います。

-
グループミーティング
お互いの良いところや、間違っていたところを共有することで、自分では気が付かなかったことにまで学習が進められました。
詳細はこちら -
オリジナル製図課題
様々なパターンの設計条件を学習できたことと、充実した課題数がよかったです。一つひとつを丁寧に解くことで、本試験での対応力が身についたと思います。
詳細はこちら -
自習室
休日も集中して学習できよかったです。必要な資料なども用意していただき、学習環境も良かったです。自習室で他の受講生を見る事で刺激にもなりました。
詳細はこちら -
総合資格学院ホームページ
合格者インタビューを拝見し、来年こそは自分も!!と奮い立たせていました。試験の速報や総評も見られたので、情報ツールとしても利用しました。






