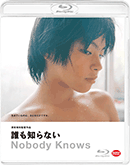京都府庁旧本館(日本~京都)
和洋折衷の美が光る、現役最古の官公庁舎

1945年8月、太平洋戦争末期。連合軍は日本に対して無条件降伏が記されたポツダム宣言の受諾を迫っていました。降伏か本土決戦か…。ギリギリの攻防を繰り広げる日本政府と若き陸軍将校たちの姿を追いながら、8月14日から玉音放送へ至る8月15日までの緊迫の24時間を描いた『日本のいちばん長い日』。原田眞人監督は1967年の岡本喜八監督版とは異なり、本木雅弘演じる昭和天皇を登場させ、天皇、総理大臣、陸軍大臣、若き将校らそれぞれの信念を貫く重厚な人間ドラマとして仕立てています。
本作で、役所広司演じる阿南惟幾(これちか)陸軍大臣の拠点である陸軍省本庁舎として使われたのが、桜の名所としても名高い京都府庁旧本館です。明治時代、文明開化の波とともに多くの洋館が建設されましたが、明治37年(1904年)12月20日に竣工した旧本館もその一つ。昭和46年に本館としての役割は終えたものの現在も執務室として使われており、現役の官公庁舎としては日本最古のものとなっています。重厚なルネサンス様式の建物は、東京駅の設計で知られる建築家・辰野金吾の弟子である松室重光によるもの。館内には、大正天皇即位の礼、および昭和天皇即位の礼に関する閣議も開かれた旧本館のシンボルである「正庁」、24人の知事が使用した「旧知事室」、府議会の議場だった「旧議場」などがあり、創建当時の姿を見ることができます。
洋館の見どころの一つといえば、和洋折衷の美。折上小組格天井(おりあげこぐみごうてんじょう)で仕上げた正庁、旧知事室の、見事な構成の格天井と重厚な廻り縁や、大理石にタイルを組み合わせた暖炉、アーチ型の曲線や蛇腹型の装飾を施した旧議場のしっくい壁のほか、「日本洋家具の父」といわれた杉田幸五郎の家具も置かれ、工芸品のような趣さえ感じさせます。また、館内にはギリシャ国花でもある「アカンサス」をモチーフとした装飾が随所に散りばめらています。劇中、会議に向かう阿南に向かって敬礼する将校たちの姿を捉えた階段のシーンの“手すり”にもご注目ください。
その決断に、すべての希望は託された。
■Introduction原作は昭和史研究の第一人者・半藤一利による大ベストセラー「日本のいちばん長い日 決定版」。監督・脚本は社会派ドラマ『クライマーズ・ハイ』や、家族の愛を描いた『わが母の記』でモントリオール世界映画祭審査員特別グランプリに輝いた原田眞人が務める。実在した陸軍大臣・阿南惟幾を役所広司が演じる他、昭和天皇役を本木雅弘が務める。さらに松坂桃李や堤真一、山﨑努ら実力派俳優陣が集結。
■Story太平洋戦争末期、戦況が困難を極める1945年7月。連合国は日本にポツダム宣言受諾を要求。降伏か、本土決戦か―。連日連夜、閣議が開かれるが議論は紛糾、結論は出ない。そうするうちに広島、長崎には原爆が投下され、事態はますます悪化する。“一億玉砕論”が渦巻く中、決断に苦悩する阿南惟幾陸軍大臣(役所広司)、国民を案ずる天皇陛下(本木雅弘)、聖断を拝し閣議を動かしてゆく鈴木貫太郎首相(山﨑努)、首相を献身的に支え続ける迫水久常書記官(堤真一)。それぞれが苦悩する一方、終戦に反対する畑中健二少佐(松坂桃李)ら青年将校たちはクーデターを計画。日本の降伏と国民に伝える玉音放送を中止すべく、皇居やラジオ局への占領へと動き始める。