
 “コンシェルジュ=ホテル宿泊客のあらゆる要望に応えることをモットーとした職務。または、種々の施設で同様の役割を担う者” 今でこそ日常会話の中で使われるようになったコンシェルジュという言葉ですが、因幡さんが会員制のコンシェルジュサービスを行う「プライベート コンシェルジュ」を設立した当時は、まだまだ耳慣れないものでした。
“コンシェルジュ=ホテル宿泊客のあらゆる要望に応えることをモットーとした職務。または、種々の施設で同様の役割を担う者” 今でこそ日常会話の中で使われるようになったコンシェルジュという言葉ですが、因幡さんが会員制のコンシェルジュサービスを行う「プライベート コンシェルジュ」を設立した当時は、まだまだ耳慣れないものでした。
「ネットワーキングなどで名刺交換をした際、『プライベートコンシェルジュ』って何?という反応がほとんどで、ビジネスコンセプトから説明しなければなりませんでした。当時は、同じ話を何百回も繰り返していたような気がします(笑)。ただし、“初めて知った”“珍しいね”ということで多くの方に興味を持ってもらえることができました。」
日本在住の外国人を主とした個人会員から、来日する企業のトップの秘書的業務をオーダーする外資系企業といった法人顧客まで幅広い顧客を持つ。バイリンガルの専属スタッフが、目的に合わせたレストランの提案・予約から、各種チケットや宿泊の手配、記念日のアレンジまで、彼らのあらゆるリクエストに対応します。実力と信用により確実な成長を遂げ、現在では世界の名だたるVIPが利用する日本でも屈指のコンシェルジュを専門とする会社となりました。
「京都での結婚式のアレンジを行ったことがありました。出席する外国人の男女30名あまりが着物で装うということになり、ホテルの美容院では手が足りないということで、電源などを増設、さらに着付けの先生や美容師さん外注で呼んだ、特設ビューティーサロンを作って対応したことがありました。着物を着た外国人が大量に京都市内を闊歩したということで、地元でも話題になったという話を後から聞きました。」
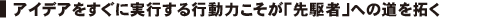
 日本初ともいえる会社の創始者は、なんと女性の2人組。いったいどんなきっかけで起業に至ったのでしょうか?
日本初ともいえる会社の創始者は、なんと女性の2人組。いったいどんなきっかけで起業に至ったのでしょうか?
「後にビジネスパートナーとなる高田歩さんとは、何か面白いパーティーを開きたいねと意気投合。友人たちを招待して“Lux and the city”というイベント開催していました。内容の斬新さとセンスが評価いただけたのか、参加した外資系企業で働く外国人たちから“イベント会社を設立すれば?”とアドバイスをもらっていました。しかし、小さなイベント会社では成り立たないという意識もあり、別の方法を模索。ある時、雑誌VOGUEでイギリスにあるコンシェルジュ会社の存在を知り、早速、日本で展開するなら手を組まないかと電話で連絡してみました。返事は“日本はユニークな国だから進出まであと3年はかかる”というもの。“つまり、私たちが今始めれば日本初になるんだ”と気付いたのが設立のきっかけです。」
普段から日本に在住する外国人との交流が深く、彼らのニーズを肌で感じていた経験があるとはいえ、会社設立には勇気が必要なのは明らか。電話で直接連絡するなど体当たりの行動力、決断力がなくてはなしえなかった偉業とも言えます。
そんな彼女たちがライバルとして意識していたのは、外資系で働いている秘書だといいます。
「秘書のいる人々はプライベートなことまで秘書に頼むことが多いという懸念がありましたが、蓋を開けてみると“公私をきちんと分けたいという考え方を持つ人々”からの支持を獲得することができました。設立当時、外国人向けのリロケーションカンパニーや個人で同様の仕事をしている方はおられたようですが、明確に競合他社と言える存在はありませんでした。純粋に日本で発生した会員制のコンシェルジュ会社の先駆者としての存在意義はしっかりと感じていましたね。」
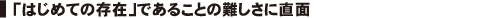
 競合他社がないということは、つまり明確なビジネスのモデルとなる存在がないことになります。その点でのご苦労について話をうかがうと…。
競合他社がないということは、つまり明確なビジネスのモデルとなる存在がないことになります。その点でのご苦労について話をうかがうと…。
「お手本とする存在は海外にしかなく、オペレーションの方法などは独自に編み出すしかありませんでした。会員制ということで契約書や会費などのルール設定も大変でしたね。特に苦労したのが価格設定で、似たようなサービスの課金体制を徹底的にリサーチすることでクリアしました。創業間もなく、アメリカのビリオネイヤーから問い合わせがあるというチャンスに恵まれましたが、問い合わせいただいた業務の料金を決定していなかったため大いに焦ったという経験もありました。」
「コンシェルジュサービスはお客様のリクエストから仕事が始まります。それ故、とにかく幅広く情報を収集する能力が試されます。また、お客様からの信頼を勝ち得るという面からも、信用するに値する優秀なサプライヤーのリスト化にも時間がかかりました。新しい会社であり新しいビジネスであるうえお付き合いする範囲も広い…とにかく面識を持ち、送客した時にきちんと抜かりなく対応してもらえるような関係性を構築することにもエネルギーを注ぎました。」

 今では、30カ国以上に顧客とネットワークを持つ「プライベートコンシェルジュ」。彼らのニーズを的確に捉える能力を持った彼女ならではの空間や建築の在り方についてうかがうとこんな意見が飛び出しました。
今では、30カ国以上に顧客とネットワークを持つ「プライベートコンシェルジュ」。彼らのニーズを的確に捉える能力を持った彼女ならではの空間や建築の在り方についてうかがうとこんな意見が飛び出しました。
「プライベートコンシェルジュにとって関わりの深い空間や建築とは、レストラン、旅館、パーティー会場となります。ここでは、外国人ならではの特徴を強く感じられます。例えば、日本人はレストランで個室を好み、旅館では部屋食をセレクトしがちです。よりプライベートが約束される空間を好むということですね。対照的に、外国人の多くは、レストランでは周りにお客様がたくさんいる賑やかなテーブルを好み、旅館では部屋食よりもダイニングエリアでの食事を好むなど、“食事をする場所”と“寝る場所”は別にしたがる傾向があります。食事をする場所ひとつをとっても個室至上主義の日本人と外国人との価値観に顕著な違いがありますね。」
「また、パーティー会場を選ぶ際に外国人の顧客からリクエストが多いのが、通常は飲食できないような場所。美術館や京都の寺院などを会場としてアレンジしたところ大変好評でした。しかし、パーティー会場を想定していない箱=空間では、人が集い飲食するには不便が多いのが実情です。これから作られる全ての施設には、想定外を想定した機能性をどこかに付加していただけたらいいですね。ひとつの空間にひとつの目的・機能をもたせるのではなく、できるかぎりのあらゆる可能性を付加していただけたら『プライベートコンシェルジュ』としては嬉しい限りです。」
最後に因幡さんに次なるビジョンについてお話しいただきました。
「日本人のquality of life向上のためのお手伝いがしたいですね。日本人はなんでも自分でこなしてしまう器用な人が多い。しかし、多忙でプライベートな時間を作れない日本人こそ、外国人のように人を上手に使って、忙しいなかにも自分の時間を捻出することが必要とされるのではないでしょうか。また、お客様の代わりに色々な事を代行していると、カスタマーフレンドリーではないサービスが多いと感じざるを得ません。サービスの番人というか、お客様が辟易するようなトランザクションが存在していないかウォッチして、改善させるようなコンサルティングにもトライしてみたいですね。」
“コンシェルジュ”を極める因幡さん。今後はホスピタリティ目線を重視した施設の開発などにも携わってみたいといいます。一体、次はどんな面白いチャレンジをされるのか、今後も目が離せない存在です。
(取材・文/小林未佳)






