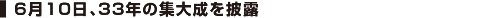

歌手の吉幾三さんのコンサートツアーをはじめ、NHK紅白歌合戦、NHK歌謡コンサートなど、数々の舞台や番組に出演する津軽三味線奏者の福居幸大さん。演奏歴33年、これまでにのべ100人以上の弟子を育ててきたベテラン奏者です。6月10日(日)には、これまでの活動の集大成として、浅草公会堂で「福居幸大 津軽三味線 絆 演奏会」を開催。その意気込みを次のように話します。
 「今回の演奏会は3部構成でお届けします。第1部『故郷へ〜北前船の旅』では、江戸時代にさまざまな物資とともに民謡を各地に運んでいた北前船(きたまえぶね)の航路をたどり、九州から北海道までの各地の民謡を演奏。第2部『津軽へ〜芸の伝承』では、私の家元であり、師匠である福居典大が率いる福居流社中とともに演奏し、第3部では私が参加する邦楽音楽ユニット『龍人』の楽曲を披露します。33年間、津軽三味線を弾き続けられたことへの感謝の思いを民謡や演奏を通じて表現し、聴きに来られた方との絆を結べることができればと思います」
「今回の演奏会は3部構成でお届けします。第1部『故郷へ〜北前船の旅』では、江戸時代にさまざまな物資とともに民謡を各地に運んでいた北前船(きたまえぶね)の航路をたどり、九州から北海道までの各地の民謡を演奏。第2部『津軽へ〜芸の伝承』では、私の家元であり、師匠である福居典大が率いる福居流社中とともに演奏し、第3部では私が参加する邦楽音楽ユニット『龍人』の楽曲を披露します。33年間、津軽三味線を弾き続けられたことへの感謝の思いを民謡や演奏を通じて表現し、聴きに来られた方との絆を結べることができればと思います」
「感謝の思い」というのは、津軽三味線の奏者としてだけではなく、2005年に創業した「和えん亭吉幸(きっこう)」のオーナーとしての思いでもあります。同料亭は、日本の四季折々の料理を味わいながら、津軽三味線の演奏を楽しめる「和の空間」。日本人はもちろん、外国からの旅行客にも人気を博しています。
「『吉幸』という名前は、私が25年間専属奏者として舞台を務めさせていただいている、歌手の吉幾三さんが名付けてくださいました。吉さんの『吉』と、私の『幸』という名前を合わせたものなんですよ」
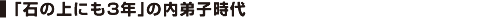
 現在、約1000人規模の会場で公演を行っている福居さん。三味線の道を歩み始めたきっかけは、「一番の応援者だった」と話す父親の存在があります。
現在、約1000人規模の会場で公演を行っている福居さん。三味線の道を歩み始めたきっかけは、「一番の応援者だった」と話す父親の存在があります。
「私が津軽三味線を弾き始めたのは、高校生の頃のこと。なにか楽器をやってみたいと思っていたところ、父が趣味でしていた三味線が家にあったんです。それで試しに弾いてみたところ、興味が出てきまして。それから、『どうせやるなら、ちゃんと習ったほうがいい』という父のススメもあって、高校2年生の時に、福居典大師匠の元で津軽三味線を習い始めました。そして、高校を卒業するのと同時に、師匠の元で内弟子として修行を始めたんです」
 内弟子になるというのは、師の元に住み込みで修行するということ。つまり、芸の道で生きていく決断をしたということです。
内弟子になるというのは、師の元に住み込みで修行するということ。つまり、芸の道で生きていく決断をしたということです。
「実は、それも父の提案がきっかけでした。『目標も持たずに、ただ4年間大学に行くだけなら、典大師匠のところで修行してみればいい。周りが卒業する頃には、ある程度のものになれるんじゃないか。手に職をつけるのも一つの生き方だぞ』というわけですよ。普通は、私のほうが『芸の道に進みたいんです』と言って、『何言ってんだ、ばかやろー!』となるのが、よくあるパターンじゃないですか(笑)。でも、そうじゃなかった。僕も『それも一理あるよな』と妙に納得して、深く悩むこともなく今の道に進みました」
3年間に及ぶ内弟子時代は、掃除や車の運転などの家事手伝いをしながら、三味線の稽古に励みました。しかし、その間には年頃の若者が抱えがちな悩みや葛藤から、「辞めようと思ったこともある」といいます。
「僕の実家と住み込みで働いていた師匠の家は近かったので、戻ろうと思えばいつでも戻れる距離でした。でも、一度も帰りませんでしたよ。それはやっぱり、兄弟子たちの姿を見て、自分もなんとか一人前になろうと決めたからです。正月になると、兄弟子たちが着物を着て、奥さんと一緒に師匠の家にあいさつに来るんですよ。で、私といえばジャージ姿で縮こまっていて……。『おれも兄弟子のようになるんだ!』という気持ちでがむしゃらに頑張った、正に『石の上にも〜』という諺がピッタリの3年間でしたね。師から「福居幸大」の名取りを授けられたのは、内弟子期間を終えた4年後の1987年でした」

その後は浅草の「民謡酒場 追分(おいわけ)」というお店のステージに出演するようになった福居さん。同店は、民謡の生演奏を聴きながらお酒が飲める店で、プロとして活躍する人のほかに、プロを目指す芸人が日夜演奏を行っています。民謡界の登竜門的な存在として知られており、三味線ユニット「吉田兄弟」の兄、吉田良一郎さんも同店に出演していました。「追分」でのステージをはじめ、さまざまな舞台への出演を重ねていった福居さん。昔も今も変わらない心得は「一生懸命であること」だと話します。
「演奏を聴いてくださる人に対して、一生懸命自分の三味線を弾くんです。お金や時間を掛けて演奏を聴きに来てくださっているわけですから、こちらはそれに応えなければ。
そう思うようになったのは、内弟子になる時に『何事も一生懸命やりなさい』という言葉を掛けてくれた父の存在が大きいです。父は、舞台に立つ時など、なにかある時には必ず駆けつけてくれました。そんな父の前で、いい演奏を見せたかったんです。私が30代の時に亡くなってしまいましたが、一番の応援者でした」」
「一生懸命」の日々を駆け抜けて33年。この道を極めんと、今も試行錯誤を続けていると福居さんは話します。
 「『これでいい』という答えなんて、ないんです。自分の演奏に対して、絶えず新しい試みに挑戦しています。最終的には『自分らしくやる』ということに行き着くと思いますが、私にとってのそれは『日々の努力の積み重ね』。自分が今まで培って来た技術をもって演奏し、聴きに来てくださる人に満足してもらう。ただ、それだけです」
「『これでいい』という答えなんて、ないんです。自分の演奏に対して、絶えず新しい試みに挑戦しています。最終的には『自分らしくやる』ということに行き着くと思いますが、私にとってのそれは『日々の努力の積み重ね』。自分が今まで培って来た技術をもって演奏し、聴きに来てくださる人に満足してもらう。ただ、それだけです」
取材時に「一生、津軽三味線を弾き続けます」と話した福居さん。その長く続くであろう道のりを思い浮かべるように、「自分はまだまだ」と話を結びました。常に自分に挑戦し続けるからこそ、円熟味を帯びるその音色。終わりなき芸の道を、三味線を片手に歩み続けます。
(取材・文/石川裕二)






