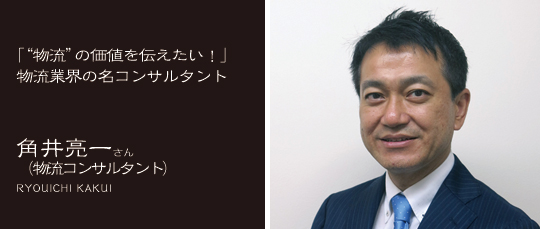経済・サービスと人をつなぐ“物流”

「“物流”がなければ、消費者はコンビニエンスストアでモノを買えませんし、その他のさまざまな店舗でもサービスを享受することができません。企業間でも、商品の納品が行われなければ経済が成り立たない。物流は、とても大事な存在なんです」
角井亮一さんは、通販物流の業務を代行している「株式会社イー・ロジット」の代表。同社のチーフコンサルタントとして、物流業界の人材教育研修・コンサルティングなどを手掛けています。
倉庫・運搬業を営む家に生まれた角井さんは、いわば生粋の“物流っ子”。学校が休みのときには家の仕事を手伝い、高校受験時には家業を継ぐことを意識して「経営について学べる学科を探していた」といいます。
「兄弟がいたら違っていたかもしれないですけど、一人っ子でしたから。自然とそういう考えになっていました」
高校卒業後は上智大学の経済学部でマーケティングを学び、渡米。ビジネスに特化したゴールデンゲート大学の大学院に進学し、MBA(経営学修士)を取得します。帰国後は「いろいろな経営の現場を見たい」と、経営コンサルタントで知られる船井総合研究所に入社。酒のディスカウントストアの出店計画や、店内のレイアウトづくり、酒蔵の商品開発や通販業務などに携わります。
物流に、より多くの知恵と資金を

その後、不動産会社を経て、家業である物流会社に入社した角井さんは「ゲインシェアリング」と呼ばれる、成功報酬型の物流委託業務を日本で初めて達成。東証一部の企業の物流改革を行い、年間で約2億円のコストダウンを実現するなど、コンサルタントとしての手腕を発揮します。そして、2000年にはイー・ロジットを設立。インターネットの普及とともに需要が増えているネット通販業界を中心に、豊富な知識と経験によって業務をサポート。スムーズな物流システムをつくりあげることで、業界の成長の一翼を担っています。
一方で、物流に関する著書の執筆も精力的に行っている角井さん。国内はもちろん、著書は米国・中国・韓国・台湾でも出版されており、手掛けた書籍の数は13冊に上ります。2014年には、角井さんが監修を務めた書籍「図解 基本からよくわかる物流のしくみ」(日本実業出版社)が出版。モノ・サービス・情報・お金の流れすべてに関わる、物流の機能や仕組みについて図解したもので、書籍の執筆などを通じて、物流の啓蒙(けいもう)活動に取り組んでいます。
「“物流”は、私たちの暮らしにおいて欠かせない存在であるにもかかわらず、人材やお金のリソースが割かれていないのが現状。物流の大切さを広めることで、業界により多くの知恵や資金を掛けてもらえればと思っています」
物流の価値を伝えるための活動
物流には、どうして人材やお金が投資されていないのか。角井さんは、次のように話します。
「そもそも、大学で物流のことを教えていないんですよね。物流の大切さを知らないんです。逆に、その価値をわかってもらえれば、学生が経営者になったときに、物流を重視してもらえるのでは」

そんな考えのもと、角井さんは現在、多摩大学大学院で客員教授として“ロジスティクスビジネス”を教えています。ほかにも「運送業界から日本を元気にしたい」という思いのもとに集まった運送事業各社による団体「DNA(一般社団法人ドライバーニューディールアソシエーション)」では、理事に就任。同団体は、2015年2月にイベント『第2回トラックドライバー甲子園アワード』(会場:よみうりホール)を開くなど、業界の抱える問題を解決し、よりよいものにしようと活動しています。
「2014年に開かれた『第1回トラックドライバー甲子園アワード』でも語られたように、物流業界ではトラックドライバーをはじめ、人材不足が大きな問題になっています。
ドライバー不足の話題もそうですが、先日は経済誌で物流ビジネスについての特集が組まれるなど、以前と比べて物流に注目が集まっているようにも感じます。東日本大震災や2014年の関東甲信地方の大雪では、コンビニエンスストアなどの商品が品薄になったことから、物流の大切さを感じた方も多いのではないでしょうか。ネット通販の普及によって、これまで以上に物流に触れる消費者の方が増えたことも、一つの要因でしょうね。
とはいえ、まだまだ物流への注目は足りていません。もっと多くの人が物流に目を向けて、価値を感じてもらえるようにしていきたいと思います」