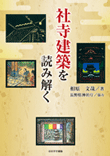『社寺建築を読み解く』
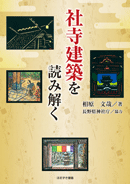 古くから身近な存在である神社ですが、その建築について一般的にはよく知られていません。本書は、全国各地の社寺を巡り、その建築を研究してきた著書が、神社の成り立ちから建築にかかわるさまざまな形態に至るまでを詳細に解説しています。神社と言えば本殿、幣殿、拝殿、鳥居、手水舎など多くの建築物で構成されていますが、例えば本殿の形式や造りが各神社によって違うのはご存じでしょうか。外見・屋根の形態で造りを分類すると、切妻造、平入、素木造、棟持柱があり、高い床に縁側を巡らして高欄を設けている伊勢神宮に代表される神明造、出雲大社のように田の字構造で中央に「心の御柱」のある大社造、その他、大鳥居造、住吉造、春日造、流造、八幡造、権現造、浅間造、入母屋造、日吉造、祇園造、見世棚造など実に多様です。もちろん、その他の建築物にもそれぞれの成り立ちに生じた様式が存在しており、知れば知るほど社寺建築の奥深さを知ることができる内容となっています。
古くから身近な存在である神社ですが、その建築について一般的にはよく知られていません。本書は、全国各地の社寺を巡り、その建築を研究してきた著書が、神社の成り立ちから建築にかかわるさまざまな形態に至るまでを詳細に解説しています。神社と言えば本殿、幣殿、拝殿、鳥居、手水舎など多くの建築物で構成されていますが、例えば本殿の形式や造りが各神社によって違うのはご存じでしょうか。外見・屋根の形態で造りを分類すると、切妻造、平入、素木造、棟持柱があり、高い床に縁側を巡らして高欄を設けている伊勢神宮に代表される神明造、出雲大社のように田の字構造で中央に「心の御柱」のある大社造、その他、大鳥居造、住吉造、春日造、流造、八幡造、権現造、浅間造、入母屋造、日吉造、祇園造、見世棚造など実に多様です。もちろん、その他の建築物にもそれぞれの成り立ちに生じた様式が存在しており、知れば知るほど社寺建築の奥深さを知ることができる内容となっています。
『神社の本殿 建築にみる神の空間』
 古くから身近な存在である神社ですが、その神社本殿の実態について多くを答えられる人はあまりいないでしょう。例えば、現在では日本の伝統的な社寺建築が完成していますが、そもそも神社本殿と寺院本堂は全く異質の建築物であった事をご存知ですか。実は平安時代中期以前の神社と寺院は高床式と土間式、掘立てと礎石立て、板壁と土壁、切妻造と寄棟造など多くの特徴を持っていました。これらは神社本殿が日本古来の宮殿建築が祖型であるのに対し、寺院本堂が中国の宮殿建築を祖型にしているためです。しかし、時代の経過とともに両者がお互いに接近し、双方の優れた点を取り入れて日本の伝統的な社寺建築が完成したのです。本書では、このような「人目に触れない本殿の内部はどうなっているのか」「神社に本殿はいつから何のために建てられるようになったのか」などの基本的な疑問に答えながら、神社建築の意匠の豊富な事例を読み解いています。神社本殿の建築的特質に迫っていく一冊です。
古くから身近な存在である神社ですが、その神社本殿の実態について多くを答えられる人はあまりいないでしょう。例えば、現在では日本の伝統的な社寺建築が完成していますが、そもそも神社本殿と寺院本堂は全く異質の建築物であった事をご存知ですか。実は平安時代中期以前の神社と寺院は高床式と土間式、掘立てと礎石立て、板壁と土壁、切妻造と寄棟造など多くの特徴を持っていました。これらは神社本殿が日本古来の宮殿建築が祖型であるのに対し、寺院本堂が中国の宮殿建築を祖型にしているためです。しかし、時代の経過とともに両者がお互いに接近し、双方の優れた点を取り入れて日本の伝統的な社寺建築が完成したのです。本書では、このような「人目に触れない本殿の内部はどうなっているのか」「神社に本殿はいつから何のために建てられるようになったのか」などの基本的な疑問に答えながら、神社建築の意匠の豊富な事例を読み解いています。神社本殿の建築的特質に迫っていく一冊です。