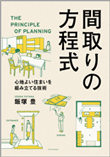『日本の名作住宅の間取り図鑑』
 日本の住宅は地域ごとの気候風土や生活習慣に合わせて、さまざまに発達してきました。特に明治時代以降、西洋文明が入ってくると純和風の住宅から、一部洋風、和洋折衷などさまざまな形が見られるようになります。各時代の間取りを見ていくと、社会や生活の変化が間取りに大きな影響を与えていることがよく分かります。例えば、江戸時代に造られたかやぶき屋根が美しい純和風の民家「旧渋谷家住宅」は、当時の水廻りのあり方を伝える貴重な資料ですが、明治に入り、養蚕で生計を立てるようになってからは、2〜3階へ光と風を呼び込むために「高八方」という造りへと改築されました。また、明治期に造られた「旧松本家住宅」は典型的な和洋館並列型の住宅でありながら、それまでの“洋館で接客を行い、和館で生活を送る”といった住まい方ではなく、洋館に寝室や勉強部屋などが作られ、生活の中心が洋館へと移っています。このように江戸時代から昭和に至るまでに造られてきた名作住宅を見ながら、その変遷を分かりやすく解説しています。
日本の住宅は地域ごとの気候風土や生活習慣に合わせて、さまざまに発達してきました。特に明治時代以降、西洋文明が入ってくると純和風の住宅から、一部洋風、和洋折衷などさまざまな形が見られるようになります。各時代の間取りを見ていくと、社会や生活の変化が間取りに大きな影響を与えていることがよく分かります。例えば、江戸時代に造られたかやぶき屋根が美しい純和風の民家「旧渋谷家住宅」は、当時の水廻りのあり方を伝える貴重な資料ですが、明治に入り、養蚕で生計を立てるようになってからは、2〜3階へ光と風を呼び込むために「高八方」という造りへと改築されました。また、明治期に造られた「旧松本家住宅」は典型的な和洋館並列型の住宅でありながら、それまでの“洋館で接客を行い、和館で生活を送る”といった住まい方ではなく、洋館に寝室や勉強部屋などが作られ、生活の中心が洋館へと移っています。このように江戸時代から昭和に至るまでに造られてきた名作住宅を見ながら、その変遷を分かりやすく解説しています。
『間取りの方程式』
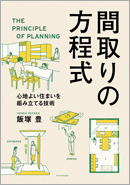 本書は、実際に大学の建築学科で教えている著者が、「○LDK」という鋳型にはめ込むだけの間取りとは一線を画すために使っている個性的な手法などを紹介しています。ステップは全部で4つ。最初ステップ「四角形から始めよう」では、敷地、要望、規模や形状といったよい間取りをつくるための“よいかたちの建物”について述べています。ステップ2の「礼儀作法を身につけよう」では、駐車場、建物、庭の配置や、動線、寸法といった日常生活に支障をきたさないための家づくりの決まりごとを紹介。ステップ3は「間と間のあいだを操ろう」と題し、間の取り方や間のデザインの仕方を取り上げ、間仕切りの考え方、抜けとたまりの作り方などその家の個性を出すテクニックが挙げられています。そして、「高さのリズムを奏でよう」とした最後のステップでは、天井の高さや階、層などについて触れています。心地よく、そして楽しく暮らすために欠かせない間取りづくりを、プロの視点からセオリー化。25の方程式が、それぞれ著者のユニークな言葉でまとめられています。
本書は、実際に大学の建築学科で教えている著者が、「○LDK」という鋳型にはめ込むだけの間取りとは一線を画すために使っている個性的な手法などを紹介しています。ステップは全部で4つ。最初ステップ「四角形から始めよう」では、敷地、要望、規模や形状といったよい間取りをつくるための“よいかたちの建物”について述べています。ステップ2の「礼儀作法を身につけよう」では、駐車場、建物、庭の配置や、動線、寸法といった日常生活に支障をきたさないための家づくりの決まりごとを紹介。ステップ3は「間と間のあいだを操ろう」と題し、間の取り方や間のデザインの仕方を取り上げ、間仕切りの考え方、抜けとたまりの作り方などその家の個性を出すテクニックが挙げられています。そして、「高さのリズムを奏でよう」とした最後のステップでは、天井の高さや階、層などについて触れています。心地よく、そして楽しく暮らすために欠かせない間取りづくりを、プロの視点からセオリー化。25の方程式が、それぞれ著者のユニークな言葉でまとめられています。