『昭和元禄落語心中①』
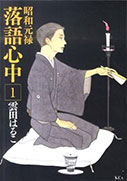 満期で出所した模範囚・与太郎は、真っ先に寄席へ向かう。刑務所の慰問で聴いた八代目有楽亭八雲の「死神」が忘れられず、落語家として生きる覚悟を決めた与太郎。彼は八雲の下へ押しかけて、弟子入りを申し込むのだが…!?本作は、落語好きの雲田はるこ氏が、寄席を舞台に描いた人情物語です。2011年に発売され、第17回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、第21回手塚治虫文化賞新生賞を受賞。2016年にはテレビアニメ化、2018年にはテレビドラマ化され、若い女性を中心に落語ブームを巻き起こすきっかけにもなりました。粋な師匠と弟子とのからみにニンマリさせられたと思いきや、早世した伝説の天才落語家・助六と、彼の影を追いながら一人落語界に残された八雲との知られざる因縁にドキドキ、八雲と養子縁組した助六の娘・小夏の複雑な心境にハラハラと、物語そのものが一本の“噺”のようで、1巻を読み終えたら2巻、3巻と、ページをめくる指が止まりません。そしておまけページがまた一興で、1巻には本編の番外編として「寄席に来ないか」を収載。「寄席とは?」から「寄席の醍醐味」、「寄席の味わい方」まで、初心者にうれしい寄席のいろはを雲田氏がラフなタッチで分かりやすく紹介しています。ページを閉じる頃には、きっと寄席に足を運んでみたくなっていることでしょう。
満期で出所した模範囚・与太郎は、真っ先に寄席へ向かう。刑務所の慰問で聴いた八代目有楽亭八雲の「死神」が忘れられず、落語家として生きる覚悟を決めた与太郎。彼は八雲の下へ押しかけて、弟子入りを申し込むのだが…!?本作は、落語好きの雲田はるこ氏が、寄席を舞台に描いた人情物語です。2011年に発売され、第17回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、第21回手塚治虫文化賞新生賞を受賞。2016年にはテレビアニメ化、2018年にはテレビドラマ化され、若い女性を中心に落語ブームを巻き起こすきっかけにもなりました。粋な師匠と弟子とのからみにニンマリさせられたと思いきや、早世した伝説の天才落語家・助六と、彼の影を追いながら一人落語界に残された八雲との知られざる因縁にドキドキ、八雲と養子縁組した助六の娘・小夏の複雑な心境にハラハラと、物語そのものが一本の“噺”のようで、1巻を読み終えたら2巻、3巻と、ページをめくる指が止まりません。そしておまけページがまた一興で、1巻には本編の番外編として「寄席に来ないか」を収載。「寄席とは?」から「寄席の醍醐味」、「寄席の味わい方」まで、初心者にうれしい寄席のいろはを雲田氏がラフなタッチで分かりやすく紹介しています。ページを閉じる頃には、きっと寄席に足を運んでみたくなっていることでしょう。
『六代目圓生コレクション 寄席切絵図』
 落語家の高座は今と昔では形や姿がすっかり変わっています。現代では大きな会場で行われるホール落語があれば、飲食店の二階で行われるような小さな落語会もありますが、戦前までは落語家が落語を演じる場所といえば寄席が当たり前でした。令和になった今、上野の鈴本演芸場、新宿末広亭、池袋演芸場、浅草演芸ホールが民間の寄席の定席として知られていますが、かつて江戸東京では町々に寄席があり、庶民の娯楽の場として大いににぎわっていたといいます。本書は、明治・大正・昭和と多くの寄席に出演してきた名人・六代目圓生が、寄席が繁盛した時代の記憶を語り下ろしたもの。東京・横浜の詳細な寄席切絵図を33枚も挿入した、落語史の資料としても貴重な一冊です。日本橋からはじまり、両国、人形町、京橋と、各地の寄席のそれぞれの特徴、雰囲気、周辺の街並みはもちろん、心に残る芸人や芸談、逸話までを克明に紹介しています。特筆すべきはその語り口。聞き手である落語研究家・山本進氏の手によって、粋でユーモアあふれる圓生の語り口そのままにつづられており、語りの妙をたっぷり堪能できます。最後の章で解説を担当した落語評論家の寺脇研氏によると、当時に比べると寄席の数はグッと減ったものの、現在では落語家の数も寄席の観客数も増加傾向にあり、寄席はなかなかの活況ぶりなのだそう。本書で「いま残っている寄席だけでもいいから、こののちすこしでも永く続いてもらいたいものだと思います」と書き記した圓生は、現代の落語ブームをどう見るのでしょうか。
落語家の高座は今と昔では形や姿がすっかり変わっています。現代では大きな会場で行われるホール落語があれば、飲食店の二階で行われるような小さな落語会もありますが、戦前までは落語家が落語を演じる場所といえば寄席が当たり前でした。令和になった今、上野の鈴本演芸場、新宿末広亭、池袋演芸場、浅草演芸ホールが民間の寄席の定席として知られていますが、かつて江戸東京では町々に寄席があり、庶民の娯楽の場として大いににぎわっていたといいます。本書は、明治・大正・昭和と多くの寄席に出演してきた名人・六代目圓生が、寄席が繁盛した時代の記憶を語り下ろしたもの。東京・横浜の詳細な寄席切絵図を33枚も挿入した、落語史の資料としても貴重な一冊です。日本橋からはじまり、両国、人形町、京橋と、各地の寄席のそれぞれの特徴、雰囲気、周辺の街並みはもちろん、心に残る芸人や芸談、逸話までを克明に紹介しています。特筆すべきはその語り口。聞き手である落語研究家・山本進氏の手によって、粋でユーモアあふれる圓生の語り口そのままにつづられており、語りの妙をたっぷり堪能できます。最後の章で解説を担当した落語評論家の寺脇研氏によると、当時に比べると寄席の数はグッと減ったものの、現在では落語家の数も寄席の観客数も増加傾向にあり、寄席はなかなかの活況ぶりなのだそう。本書で「いま残っている寄席だけでもいいから、こののちすこしでも永く続いてもらいたいものだと思います」と書き記した圓生は、現代の落語ブームをどう見るのでしょうか。








