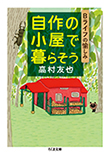『小屋1』
 ひとえに小屋といっても、その形態、利用目的はさまざま。とはいえ、本書には冒頭から「ピグミー族の母親が過ごす小屋」なるものが紹介されていて本書の“マニアック度”がうかがえます。コンゴ共和国のピグミー、エコンダ族の村には、初産を終えた母親が俗世を離れ、赤ん坊と一緒に小屋で隔離された生活を送るという伝統儀式があるそう。最長5年という長い隔離期間を過ごす小屋は、一つの空間をついたてで仕切ったような簡易的な形態でありながら、色鮮やかな布が壁に掛けられていたり、さまざまな工夫が見られます。次に紹介されているのは「ビーチハット」と呼ばれる日本の海の家のようなもの。日本では、海開きに合わせて作られる仮小屋ですが、欧米のビーチハットは簡単な造りではあるものの、恒常的な小屋が多いそう。本書ではオーストラリアやイギリス、アメリカ、オーストラリアなど各国のビーチハットが紹介されていますが、どれも決まってカラフルにペイントされており、海に向かって並ぶ姿がとてもいとおしく見えます。また、世界中の小屋を巡り、“住む人の暮らしに寄り添う建築”をモットーとする建築家・中村好文氏のインタビューとともに、実際に氏が建築した小屋も写真付きで紹介。好文氏が小屋にひかれる理由について迫ります。そのほか、国内にとどまらず世界中の小屋にまつわるコラムが全編カラー写真付きで展開されており、パラパラとページをめくって眺めるだけでも楽しめる一冊です。
ひとえに小屋といっても、その形態、利用目的はさまざま。とはいえ、本書には冒頭から「ピグミー族の母親が過ごす小屋」なるものが紹介されていて本書の“マニアック度”がうかがえます。コンゴ共和国のピグミー、エコンダ族の村には、初産を終えた母親が俗世を離れ、赤ん坊と一緒に小屋で隔離された生活を送るという伝統儀式があるそう。最長5年という長い隔離期間を過ごす小屋は、一つの空間をついたてで仕切ったような簡易的な形態でありながら、色鮮やかな布が壁に掛けられていたり、さまざまな工夫が見られます。次に紹介されているのは「ビーチハット」と呼ばれる日本の海の家のようなもの。日本では、海開きに合わせて作られる仮小屋ですが、欧米のビーチハットは簡単な造りではあるものの、恒常的な小屋が多いそう。本書ではオーストラリアやイギリス、アメリカ、オーストラリアなど各国のビーチハットが紹介されていますが、どれも決まってカラフルにペイントされており、海に向かって並ぶ姿がとてもいとおしく見えます。また、世界中の小屋を巡り、“住む人の暮らしに寄り添う建築”をモットーとする建築家・中村好文氏のインタビューとともに、実際に氏が建築した小屋も写真付きで紹介。好文氏が小屋にひかれる理由について迫ります。そのほか、国内にとどまらず世界中の小屋にまつわるコラムが全編カラー写真付きで展開されており、パラパラとページをめくって眺めるだけでも楽しめる一冊です。
『自作の小屋で暮らそう ─Bライフの愉しみ』
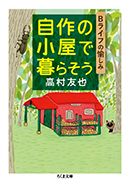 「Bライフとは、安い土地でも買って適当に小屋でも建てて住んじゃおうという、言ってしまえばそれだけのライフスタイルだ」―。そう記すのは著者の高村友也氏。高村氏は東京大学哲学科卒業、慶応義塾大学大学院哲学科博士号課程単位取得退学という輝かしい学歴を持ちながら、誰にも文句を言われずにいつまでも寝転がっていられる生活を目指して山梨の雑木林に小屋を建て暮らし始めた、“Bライフ創始者”です。本書は「Bライフってなんだ?」と題された第1章から始まり、「ドキュメント―Bライフ」「準備・計画・予備知識」「Bライフ再論」の全4章から成り、「BライフのBはBasicのB」と著者がいうように、100万円ほどの初期費用により月2万円程度で維持できる“必要最低限の生活”について書かれています。それは、10平米ほどの小屋を建てるところから始まり、電気・水の確保、風呂トイレ問題、税金や社会保険の減免についてまで、実際にBライフを送るための情報が事細かに説明されています。著者がBライフを選択した理由は前述の通りですが、「Bライフを続ける理由」においては、単に寝転がっていたいからという理由ではなく、非常に哲学的な著者の考えが垣間見えます。奥深い“Bライフの世界”をのぞいてみてはいかがでしょうか?
「Bライフとは、安い土地でも買って適当に小屋でも建てて住んじゃおうという、言ってしまえばそれだけのライフスタイルだ」―。そう記すのは著者の高村友也氏。高村氏は東京大学哲学科卒業、慶応義塾大学大学院哲学科博士号課程単位取得退学という輝かしい学歴を持ちながら、誰にも文句を言われずにいつまでも寝転がっていられる生活を目指して山梨の雑木林に小屋を建て暮らし始めた、“Bライフ創始者”です。本書は「Bライフってなんだ?」と題された第1章から始まり、「ドキュメント―Bライフ」「準備・計画・予備知識」「Bライフ再論」の全4章から成り、「BライフのBはBasicのB」と著者がいうように、100万円ほどの初期費用により月2万円程度で維持できる“必要最低限の生活”について書かれています。それは、10平米ほどの小屋を建てるところから始まり、電気・水の確保、風呂トイレ問題、税金や社会保険の減免についてまで、実際にBライフを送るための情報が事細かに説明されています。著者がBライフを選択した理由は前述の通りですが、「Bライフを続ける理由」においては、単に寝転がっていたいからという理由ではなく、非常に哲学的な著者の考えが垣間見えます。奥深い“Bライフの世界”をのぞいてみてはいかがでしょうか?