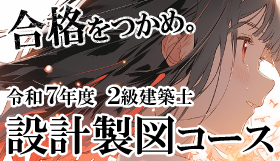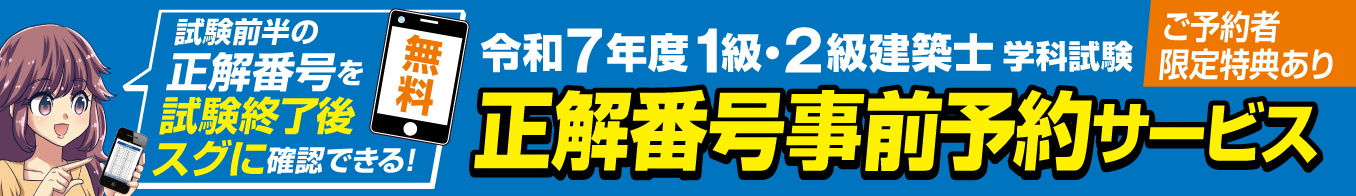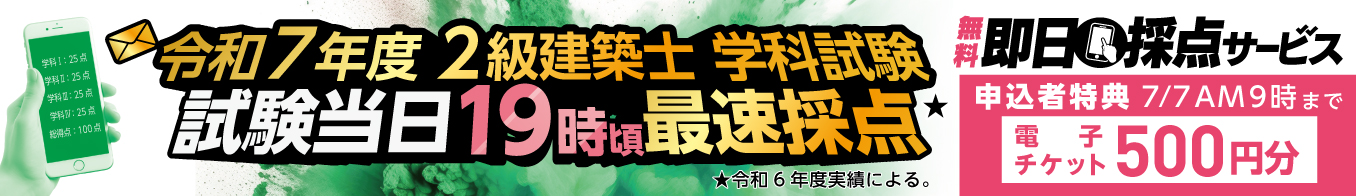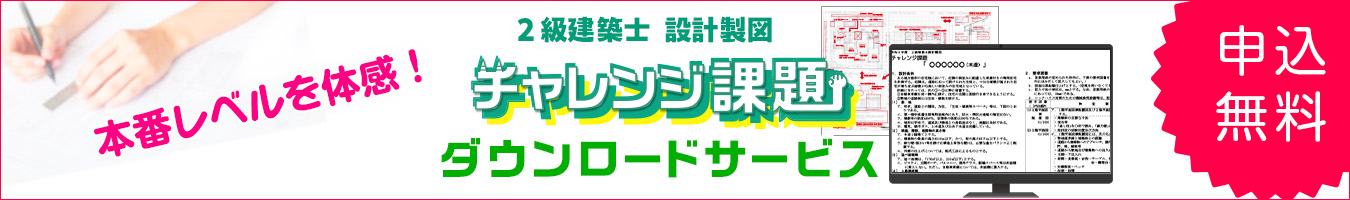二級建築士試験の
試験内容について
- TOP
- 二級建築士
- 二級建築士試験・試験情報
- 二級建築士試験の試験内容について
学科試験について

二級建築士になるためには、都道府県知事が行う二級建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受ける必要があります。
二級建築士試験は、 「学科の試験」と「設計製図の試験」が行われ、「設計製図の試験」は「学科の試験」に合格しなければ受験することができません。
【TOPICS】令和2年度から新しい建築士試験がスタートしています。
- ・建築士試験の受験資格の変更
- ・学科試験免除の仕組みを変更
- ・建築士資格に係わる実務経験の対象実務の変更
01学科試験はどのような試験ですか?
二級建築士「学科の試験」に出題されるのは、「建築計画」「建築法規」「建築構造」「建築施工」の4科目。各科目25点満点、4科目合計100点満点の試験で、出題形式は5肢択一のマークシート方式です。試験時間は「建築計画」「建築法規」が合わせて3時間、「建築構造」「建築施工」が合わせて3時間、合計で6時間の試験となります。また、合格をするためには、合格基準点(全科目合計の合格ライン)と科目基準点(それぞれの科目の合格ライン)の双方をクリアする必要があります。
02学科試験の対策として、どのような学習が必要ですか?
二級建築士「学科の試験」に出題されるのは、「建築計画」「建築法規」「建築構造」「建築施工」の4科目となります。
学科Ⅰ(建築計画)
建築計画は、「計画原論」「計画各論」「建築設備」「建築史」の4つの分野から出題されます。
「建築史」については、まずは過去に出題された建築物について、過去問われた事項とその関連事項を、確実に暗記することを優先して学習する必要があります。
「計画原論(環境工学)」については、新規出題の比率が高い状況です。これまでとは言い回しを変えた問題などが増えているので、過去問の暗記だけではなく、
その現象のイメージを図解や表で把握し、その現象が起こる原理や理由をしっかりと理解することを心がけた学習が大切です。
「計画各論」については、過去に出題された「用語」「数値」を中心に問われる問題構成でした。車椅子使用者に配慮した計画(数値)や、案内用図記号(ピクトグラム)など新傾向の出題もされています。
「建築設備」については、設備に関する機器・方式などの用語の定義を中心として、環境・省エネルギーの観点など幅広い知識が要求されるようになってきています。
正解するためには幅広い知識とともに、過去に出題された設備の用語と共にその原理や仕組みをしっかりと理解し、その上でその周辺知識についても理解することを意識して学習することが大切です。
学科Ⅱ(建築法規)
建築法規は、「建築基準法」「その他関係法令(「建築士法」「バリアフリー法」「長期優良住宅普及促進法」「耐震改修促進法」「住宅品質確保法」
「都市計画法」「建設業法」「省エネ法」「その他の関係法令」)」から出題されます。
計算問題について、特に過去問を確実に得点するためには、公式等を暗記し、法令集を開かなくても解けるようになることが大切です。
文章問題については、長文化の傾向がある問題文の中から、解答に必要な条件と必要ではない条件を区別して考えることが大切です。
また選択肢の中だけではなく、前提文に条件が示される設問が多く出題されており、留意が必要です。
近年の法改正を受け、設問中に新規出題のキーワードが多くみられます。また、過去よく出題されていた項目であっても、法改正により諸条件が追加されたり、
これまでとは異なった問われ方に変更されているため、最新の法改正情報を取り入れた学習が必須となります。
「関係法令」では、毎年2問出題される建築士法は必ず攻略する必要があります。建築士法の条文は、自身の業務や状況と建築士法の条文を関連付けて学習すると理解しやすく効果的です。
学科Ⅲ(建築構造)
建築構造は、「構造力学」「一般構造」「建築材料」の3つの分野から出題されます。
例年多くの受験生がこの学科を苦手としていますが、その理由は「構造力学」という分野に対する苦手意識を克服できないからです。
自分は以下のどのパターンにあてはまるのかを考えて学習計画を立て、学習を進めることが大切です。
数学が苦手な方
力、力の分解、力のつり合い、反力を理解できるまで徹底的に学習しましょう。
構造力学の問題を解答するための最低限必要な知識を初期段階で身につける必要があります。一次方程式、直角三角形の比(【例3:4:5】)は特に重要となります。
数学は理解できるが構造力学を初めて学ぶ方、または構造力学が苦手な方
「反力」までを徹底的に学習する必要があります。構造力学の問題を解くための基本中の基本です。「反力」を理解できないとその後の構造力学の問題ができません。
参考書でしっかり理解してから、問題集にじっくり取り組みましょう。理解できた人は、「構造力学」の残りの分野(応力、トラス、断面の性質、座屈、応力度)に挑戦してください。
構造力学は得意だという方
参考書で、確実に自分の知識として定着していなかった部分を再確認してください。
特に構造力学が得意な人は、問題練習を何度も繰り返して解読手順を完璧に習得すれば、自信を持って試験に取り組めます。
「構造力学」以外の分野は、学科Ⅰ(建築計画)や学科Ⅳ(建築施工)と同じく暗記中心の学習になるので、学習時間をしっかり確保することが大切です。
学科Ⅳ(建築施工)
建築施工は、「計画・管理」「各部工事」「その他(積算・見積など)」の分野から出題され、各分野をまんべんなく理解していないと試験に対応できません。
「計画・管理」の分野は比較的得点しやすい分野ですので、しっかりテキストなどの内容を理解することが大切です。ネットワーク工程表や、各種材料の保管方法など、頻出の内容を中心に学習することが大切です。
「各部工事」は「鉄筋工事」「型枠工事」「コンクリート工事」「鉄骨工事」「木工事」など、建物の構造となる分野がメインになり、これらの分野が一番難しく感じる方が多いです。
テキスト等でこの分野を一通り熟読し、工事の流れのイメージをつかんだ上で用語・数値を覚えることを推奨します。
「その他」の分野は、用語に注意しながらしっかりと学習すれば理解しやすい分野です。
学科Ⅳ(建築施工)は、覚えなくてはならないことがたくさんあります。まずは、用語の理解から始め、テキストを熟読し、図など見ながらイメージをとらえることが大切です。
普段、街を歩いていると建築の施工現場があるはずです。その時にきっと、「あれがテキストに載っていた〇〇なんだ」というものに遭遇すると思いますので、意識して街を歩いてみるのも学習法の一つです。
設計製図試験について
01設計製図試験はどのような試験ですか?
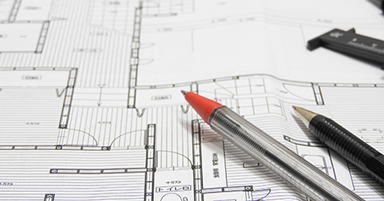
設計製図試験は事前に課題名、要求図書、注意事項等が発表されます。
試験当日は、事前に発表された課題に基づいた問題が出題され、その問題に対して要求図書を、制限時間内に完成させる試験です。設計条件等の詳細は試験当日までわからないため、課題のタイトルから想定される様々なパターンの準備をしておく必要があります。例年、平面図、立面図、断面図、伏図、部分詳細図(矩計図)、面積表、計画の要点などから6~9種類程度が要求されます。
受験者の図書類は、採点によりランクⅠ~Ⅳに区分され、ランクⅠが合格となります。
02設計製図はどのような「課題」がでますか?
令和7年の課題は、「シェアハウス(木造)」となりました。
現在、課題分析をこちらで公開しておりますので、ぜひ、ご覧ください!
| 年度 | 課題名 | 構造 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | シェアハウス | 木造 |
| 令和6年度 | 観光客向けのゲストハウス (簡易宿所) |
RC造 |
| 令和5年度 | 専用住宅(木造) | 木造 |
| 令和4年度 | 保育所 | 木造 |
| 令和3年度 | 歯科診療所併用住宅 | RC造 |
| 令和2年度 | シェアハウスを併設した高齢者夫婦の住まい(木造2階建て) | 木造 |
| 令和元年度 | 夫婦で営む建築設計事務所を併設した住宅(木造2階建て) | 木造 |
| 平成30年度 | 地域住民が交流できるカフェを併設する二世帯住宅 | RC造 (ラーメン構造) |
| 平成29年度 | 家族のライフステージの変化に対応できる三世代住宅 | 木造 |
| 平成28年度 | 景勝地に建つ土間スペースのある週末住宅 | 木造 |
| 平成27年度 | 3階に住宅のある貸店舗 (乳幼児用雑貨店) |
RC造 (ラーメン構造) |